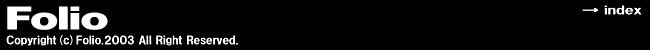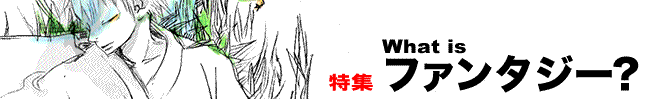| 1/3 |
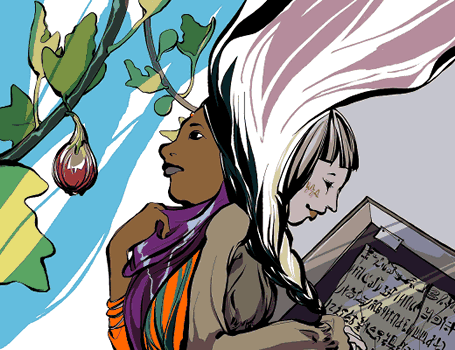 |
| イラスト 甲斐 |
砂煙に黄色く煙る、強い風が吹き付けている。 それが分かるのは、窓の外で天高く舞った風が心元なく軋む銀翼を包み込んでいるからだ。隔離された小さな空間から見下ろす、その翼の下には、茶色く広がる大地と区別のつかない色に染まった街が、一塊になって広がっていた。 日本から、直行便で行きは八時間。だが帰りは十九時間もかかってしまうほど時差のある場所に、つまり現在においても時の流れの違う場所に、その国は在る。 モカッタムの丘。飛行機から降りてすぐに目に付くのは、空港のほぼ真南に広がる絶壁だ。そこは、かつて「太陽の丘」と呼ばれ、神話に語られるこの世で最初に生まれた大地「原初の丘」に比せられた。 だが、時差と長時間のフライトの後、ふらふらしながら空港に降り立った異邦人にとっては、丘を眺めて感傷に耽るだけの余裕は無い。 空港はちっぽけで、薄暗く、空気を包み込む風と同じく黄色い砂埃に占領されている。欧米人向けに売店で売られる安っぽいコーヒーの匂いと、派手な色合いでコミック調に描かれた、スフィンクス柄のシャツの悪趣味なピンク色とが、いやに目鼻についた。 「ヘリオポリス国際空港へようこそ」腕を広げて私を出迎えてくれたモハメッドは、ニヤリと笑ってそんなジョークを言った。普段ならニヤリと返せたものだろうが、疲れていた私は、力なく笑い返すしかなかった。 「どうも、飛行機のエコノミー席というやつは好きになれないね」モハメッドの用意した車に乗り込みながら、私はぼやいた。 もっとも、あの、発狂しそうなくらい狭い席に二十時間近くも閉じ込められることが好きな人間など、いるとは思えないが。 車が動き出し、やっと人並みにくつろげる広さのシートを手に入れた私は、ため息まじりに強張った足を伸ばしながら、遅ればせに窓の外の景色を去ってゆくオベリスクに気づいた。 現在、「カイロ国際空港」と呼ばれている場所、――かつて、そこは、ギリシア人をしてヘリオポリス<太陽の街>と呼ばしめた太陽信仰の中心地の果てに当たる。 彼らは、この地に立つ太陽を崇める巨大な柱をオベリスク<針>と呼んだ。 今見ているものは、古代と言われる時代に立てられ、唯一、現代まで残された遺物である。かつて趨勢を誇った時代の最後の一本は、変わらぬ強い陽光の中、真新しく白く輝く表面を天に向かって誇らしげに突き立てている。 遠ざかりながらも街並みの向こうに見え続ける、巨大な<針>は、この場所が今なお、遥かな古代と繋がっていることを感じさせるモニュメントなのだ。 想像して欲しい――、約三千年ほど前、そこは、穏やかな流れ行く大河のほとり、河べりに数キロに渡って広がる豊かな堆積土の上に築かれた街だった。 今から三千年ほど昔、その風景のどこかで、名の知れぬ一人の男が、ひそかに恋歌を書き残した。 そう、これは、俗に言う古代エジプトでの話である。 くだんの恋歌の書かれたパピルスを発見したのは、フランスやアメリカやイギリスが、繰り返し送り込む発掘調査隊のいずれかだったと思われる。 黄ばんで端のぼろぼろになっているパピルスは、元は白または薄いベージュのような色だったに違いない。紙は河べりに生える葦科の植物の三角形をした太い茎を薄く切って水に晒し、その後、縦横に交互に並べて強く叩いて作ったもので、薄くて白いものほど高価だった。 |
||