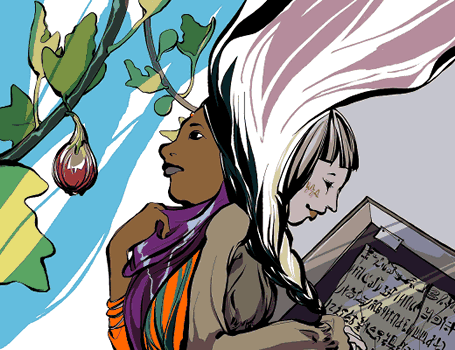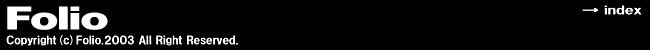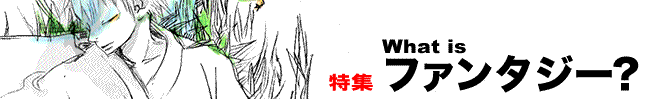「書記とは、パピルスの巻紙を司祭と決め、書版を彼の愛する子とすることを決めたもの」と、この恋歌の書かれたと同時代の書物は言う。
子孫を残し、家系を繋いでゆくのと同じように、書記たちは文字を書き記すことで、それを伝えてゆく。町はいずれ消え、巨大な建造物すら崩れさる時がやって来る。だが、存在自体が消えうせてなお、人々の記憶に残すものは何か? それは文字である。文字こそは永遠に通じるものである。過去の偉大な王たちでさえ、記録文字なくしては、その存在をこの世に留めおくことすら出来ないではないか。…と。
だが、恋歌が戯れに書かれたものであることは事実だし、それが、数千年もの時を越えて存在するのは、当人の意図した結果ではないだろう。
王たちが、自らの名を永遠にするために、朽ちない石に刻みつづけた自らの名と業績、その多くが失われた数千年後の時代に、朽ち行くはずの言葉は残された。
愛は永遠だ、などと、使い古された言い回しで格好つけるつもりは無い。
事実、人間は変わり行くものだし、変わらずにいられる人間は存在しない。当然、愛の形も意味も、変わり行くものである。
だからこそ、私は知りたい。
三千年前の文字で書かれた、その恋歌が、「当時」どんな意味を持っていたのかを。
書き手の名は、もちろん分からない。何しろ、そのパピルスには自分の名前は書かれていなかった。
当たり前だ。こっそりメモ帳に書いた「好きだ、○○」という落書きに、自分のサインを入れる人はいない。
彼の名はアメンエムハトだったかもしれないし、ラーウセルだったかもしれないし、ホルネフェルだったかもしれない。だが、モハメッドやムスタファといった名前でなかったことは、確実だ。
古代のこの国の人々は、だいたいにおいて、名前に信仰する神々の名前を入れた。プタハヘテプ、プタハ神を満足させる者。メルネイト、ネイト女神に愛されし者。だから、その手紙が、ここ、ヘリオポリス(古代のこの国の名前では、イウヌと呼ぶ)で書かれたものだとしたら、男の名には、街の主神の恩恵に授かろうと、「ラー」とついていたのではないかと思う。
だから私は、彼をヘヌトラー、と呼ぶことにした。もしかしたらヘヌゥトレー、と呼ばないと本人も気がつかないのかもしれないが、彼を目の前にして呼びかけることは無いだろうから我慢してもらおう。
その男は、実は年寄りだったかもしれないし、本当は恋人なぞ居なかったかもしれない。
それは今は亡き恋人に宛てた悲しい手紙だったかもしれないし、まだ思いを告げられずにいる思い人への満たされぬ思いを綴ったものだったかもしれない。
真実は決して分からないだろう。だからこそ、想像してみる。
ヘヌトラーは、今、なめされたばかりのパピルス紙を膝の上に広げ、眉間にしわを寄せながら、書くべき言葉を思索している。 恋歌は、ヒエラティック、通称「神官文字」と呼ばれる筆記体で書かれていた。神官文字とは言うものの、実際は神官だけが使っていたものではなく、元の象形文字を速記のために崩した簡略文字のことだ。
かつての気温は今よりも高く、空気は今よりも乾燥していたが、体感温度はかなり高かったに違いない。そのため身に着ける衣服は男も女も最低限で、家の出入り口にはドアなど無く、泥レンガを積み上げて作った家の中は洞窟と同じく、風通しの良い、ひんやりとした空間を形作っている。一人で物思いに耽るには、もってこいだ。
少し風が出てきたようだ。
彼はふと顔を上げ、しばし、目の前にいない恋人に思いを馳せる。
黒髪豊かな彼女が、編んだ髪を振って振り返り――もしかしたら金だったかも、亜麻色だったかもしれないが――彼に向かって微笑みかけるとき、その瞬間を想像するだけで、彼の心は浮き立ち、震え、どんな苦難も溶けてなくなるように思えたのだろう。
紙の上に手を伸ばしては、ためらいがちに一節。それから、しばし目を上げ、戸外のまぶしさに目を細め、視界の向こうに広がる輝く水の流れに目を留めて、何かを思いつき、また一節。
”この河の流れが、二人を隔てても…。”いやいや、河だけは二人の障害になるには物足りない。河といえば、河馬か鰐がいるものだ。雌の河馬は女性たちの守り女神だが、雄の河馬は乱暴で煩いだけ。鰐はがつがつして、水の底からいつも獲物を狙っている。そう、河の真ん中には、恋人たちの仲を嫉妬する大きな鰐が邪魔をしているのだ。そういうことにしよう。
気もそぞろに綴られる、いじらしいほど密やかなメッセージは、やがて体の内から湧き上がる願望となって、紙の上に黒々とした文章を結んでゆく。
古代エジプトにおける女性の地位は、他の古代社会と比較して例外的に高かった。
現代であれば当たり前かもしれないが、多くの古代社会では、女性は男性の「所有物」であり、男は一方的に愛を迫ることが出来た。また女性は、最初は家長である父の「所有物」であり、父が死ぬと兄または弟、結婚すれば、夫の「所有物」であった。
古代エジプトではそうではなかった。女性であっても、人はひとえに「己自身」のものであり、「両親のもの」、また「神々のもの」であった。
恋人は、彼女自身のものであり、彼女の両親のものであり、河と、大地と、天と、風と、その他すべての、生命を育む神々の娘である。だからこそ男は、控えめに、自分にとって、より近しい肉親と同じように、妻や恋人を「妹」と呼ぶことが多かった。実際に血のつながりはなくとも、二人手を取り合えば、血のつながりある家族と同様に、家の一員となるのだ。
彼は実際に、想い人に妹と呼びかけたかもしれないし、実際に呼びかけることを思い、僅かに顔を赤らめていただけかもしれない。
”彼女のために寝床をしつらえるとき…”
ああ、その日の来るのを何度夢見たことか。
ただ手を取り合うだけで満足できるほど幼くはない、
かと言って行いの「結果」だけ誇らしげに書くほどに大人でもない。
さても、ヘヌトラーは情熱を込めて、音になった言葉として本人に伝えるのではなく、自分の想像の中でのみ恋人の姿を思い描いて、恋人には読めない文字で想いを綴ることしか出来なかった。
NEXT
|