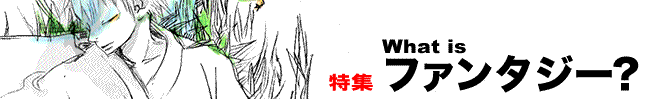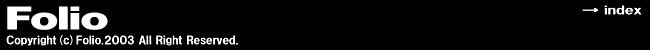序 狂言回し
それほど昔の話でもありません。ある森の奥深くに「白鳥の湖」と呼ばれる静かな湖水がありました。
その畔には古い城があり、厳めしい貌をした悪魔が棲んでおりました。窓に鉄の格子が掛けられているのは、悪魔が気に入りの姫君をさらってきて閉じこめておくためでした。
そこには美しい姫君がひとり囚われておりました。白い衣装がよく似合う姫君で、呼び名も白鳥姫というのです。姫は朝が来ると、悪魔の力によって白鳥の姿に変えられてしまいます。日がな一日湖水に映る自身を眺めて過ごし、夜になるとようやく、人の姿に戻ることができるのです。
さて、ある夜、人の姿に戻った白鳥姫を目にした王子がおりました。王子はひと目で白鳥姫に恋をしてしまいました。自分の愛の真実にかけて、白鳥姫を悪魔の手から救い出すと誓いをたてたのです。
ところが、真実とは、ひたむきであればあるほど欺きの罠にかかるものなのです。王子がまさに白鳥姫への誓いを成し遂げようと決意していたその夜、悪魔の娘、黒鳥姫が、王子の目の前に現れました。白鳥姫にまるで生き写しの黒鳥姫は、王子の前でそれは美しく踊ってみせ、まるで焔のように王子を幻惑するのです。
と、ここまでは、皆様にもおなじみのお伽話。彼等の綾なす心の糸は、ここからどんな具合に、もつれてゆきますことやら。
1.悪魔
私のことを悪魔と…白鳥姫がそう呼んでいるのは知っている。実際、何不自由なく暮らしていた住まいから彼女を無理やりに連れだし、湖畔の小部屋に閉じこめたのは私なのだから。それだけではない、昼間には羽ばたくことも逃げ出すこともできないよう、彼女の手足を拘束し、夜になれば寝床に忍び入り、拘束を解いてやるかわりに、その身体を自らの所有物でもあるかのように侵食した。自分の中の最も卑猥な願望を彼女の肌に塗りたくるようにして、欲しいまま貪った。
こうして並べ立てると、まさに悪魔の所行だな。
ただ、一つだけ言っておこう。弁解などではなく、そこに存在した、変えようもない事実として。
最初に見えない境界線を壊し、私を招き入れたのは白鳥姫のほうだ。あの真白い部屋で、女として、男である私を乞うたのは。そうでなければ私もいくぶん冷静に、彼女を商売道具のひとつとして手元に置いておくだけで済んだろうに。
彼女は渡り鳥の群に見捨てられ、独り湖畔に取り残された哀れな白鳥だった。湖水に映る自身の姿以外に、輪郭を描くものは何もない。耐え難い心細さを忘れるために、彼女はある夜、とうとう自身を投げ出したのだ。
「あたしをさらっておいて、なぜ欲しがらないの…こんなの、残酷すぎるわ」
彼女は私を詰り、私はそれに対する理屈を持たなかった。こんな状況に置かれても、求められているという実感が欲しいのか。面倒な女だ。煩わしさに溜息が漏れ、ほとんど憂鬱すら覚えたが、それでも自分の中の下劣さは冷静さに勝っていた。自分ではそんな欲望は超越したと思っていたのに、実際に彼女に触れてみると、尽きない水のように悦びは溢れ出してきた。男にしろ女にしろ、感情というのは厄介な代物だな。
私は確かに彼女の弱さに付け込んだ。だが、私を責める前に、彼女に会って、その眼を見つめてみるがいい。澄み渡った水の清廉と、突き抜けた裏側に映る淫蕩のコントラストに、逃れようもなく幻惑されるだろう。絹の肌から立ちのぼる香に包まれ、甘やかに絡みつく声を聴いてみれば、拒絶するほうが余程の残酷だと解るだろう。悪魔と呼ばれ、完璧な冷徹を自負している私ですら、憐れみと、同じ重さの残酷さに駆り立てられて、何度となくあの部屋へ通ったのだ。
毎朝、彼女を哀れな白鳥の姿にいましめながら、私は彼女に囁きかけた。
「白鳥姫、私も本当は、こんなことはしたくないのだ」
それは私の本音だった。出来ることなら彼女を包むように慰めてやり、その瞳が安堵に和らぐ様を見たいと、本気で願うこともあったのだ。だが、私は、彼女にとって悪魔だった。
悪魔というのは全てを手にしているようで、実際は損な役まわりだ。無意識の中に押し隠した人間の欲望を煽り、そこへ身を任せるよう唆しながら、一方では全てを見越し、醒め切っていなければならない。優しさも執着も、たとえ感じても露わにするわけにはいかなかった。
私自身も矛盾に苦しんだのだから、彼女も同じように苦しんだのだろう。私を憎み、憎んでいる男に抱かれる意外に、此処に囚われている自分自身を確かめる術がなかったのだから。その苦しみも含めて彼女が私を求めていると思い込んだのが、私の唯一の誤算であり、過ぎた自惚れだった。
やがて、夜毎に深まる矛盾に耐えきれなくなったとき、彼女は私の眼を盗み、別の男を懐に招き入れた。真剣で、誠実で、どこまでも彼女に忠実で、理想に燃える若い男を。彼は白鳥姫を真摯に愛し、必ず此処から連れ出すと誓いを立てた。
嫉妬しないのかと? まさか。こちらはそれほど暇な身分ではないのでね。
彼女の眼には、どこぞの高貴な王子と映るらしいが、私に言わせれば、しょせん哀れな若造だ。奴がどれだけ真実を込めて愛撫しようと、彼女の身体に、私の触れなかった部分はどこにもない。奴は躍起になって、私と白鳥姫がたどった軌跡を後追いしているに過ぎんのだ。だからこそ私は、白鳥姫とあの王子が抱き合っているのを目の当たりにしても、こうして笑っていられるというわけさ。
さあ、もういいだろう。もともと彼女を占有するつもりもなかったし、占有されることなど…よけいに御免だ。それ以上は彼女自身から聞くがいい。白鳥姫本人の口から、彼女が私を悪魔と罵るのを聞くがいい。
2.白鳥姫
あたしは悪魔に囚われて、ただひとり、森の奥の湖に住んでいます。与えられているのは、裾の長い白い衣装と、同じように白一色でしつらえられた、簡素な部屋がひとつだけ。
夜明けとともに、あたしは白鳥に姿を変えられてしまいます。ほんのひと言、ふた言、悪魔が呪文を唱える短い間のことなのですけれど、それは苦しい思いをします。自分の手脚が融けた蝋みたいに形を変えて、白い羽根に覆われた鳥の姿に変わっていく、その苦痛と恐ろしさは、何度同じことをされても軽くなることはありません。
あたしの腕が不自然に反り返って身動きを奪われるさまを、悪魔は傍らに立って見下ろしています。まるでそれをが義務だとでもいうように、屹とした冷静さを保ちながら。全てが終ると、悪魔はあたしの上に身をかがめて囁きます。
「白鳥姫、私も本当はこんなことはしたくないのだ」
だが、こうしないと、お前は逃げてしまうだろう? その声はぞっとするほど優しいのに、見下ろす眼は相変わらず氷のよう。その瞬間、引き裂かれるような、どうにも割り切れない気持ちになります。あたしはこの悪魔を憎んでいるはずなのに、同時に彼に愛されていないことに、とても傷ついているのです。
あたしをさらって、ここへ閉じこめておきながら、ろくに顧みようとはしてくれない。愚かなことと笑われるかもしれませんけれど、終いにはあたしのほうが、あの人があたしの側に少しでも留まってはくれないかと、そればかりを願うようになってしまったのです。
ここへ閉じこめられて、どれほどの日が経ったでしょう。三日月が裂けた口唇みたいに世界を嘲笑う闇夜に、彼はとうとう、足音もさせずにあたしの部屋を訪れました。
その夜悪魔は、陽が落ちてもなお、あたしにかけた呪縛を解いてはくれませんでした。あたしは真夜中まで白鳥の姿にいましめられたまま、ぐったりと疲れきって、目を閉じていたのです。
「済まなかった。ずっと用があって、解いてやることができなかった」
ようやく現れた悪魔は、抑えた声であたしに詫びました。その声は、月光の魔術のせいか、いつもよりも低く、わずかな感情の陰影がありました。たったそれだけ、その僅かな優しさが、あたしの心に思わぬ波を立てました。それは細波のように、一瞬で指先にまで響いてきたのです。
あたしはようやく解かれた手を伸ばし、悪魔に触れました。乾いた手を取り、自分の胸もとに導きさえしたのです。言葉では表せない感情を、少しでも悟ってほしかったのに、彼は狼狽する素振もみせずにあたしの手を払いました。なんて拒絶。惨めさがつのって涙がにじみ、あたしの声は震えました。
「ひどいわ…」
「そう思うか?」
悪魔は無表情のまま問い返しました。これ以上にひどいことを、自分はいくつも知っているとでもいうように。けれど、あたしが待っているのは、まさにその「ひどい」ことだったのです。
「あたしを欲しがらないなら、何故さらったの…こんなの、残酷すぎるわ」
そのときあたしは…彼に触れてほしくて気が狂いそうでした。身体の内側にぽかりと黒い洞穴が空いたようで、すべてがバラバラに壊れてしまいそうだったのです。その空洞は深く、穏やかな優しさを注がれるだけでは到底満たされそうもありませんでした。
返ってきたのは、怖いほどの無言。闇を探るような無表情は、まるで、あたしが堕落という淵に墜ちる小さな音を聞き取ろうとでもしているようでした。やがて彼は、薄く開いた唇から、焦らすように、永い息を吐いて。それからようやく、あたしに触れました。
彼は服を着たままベッドに入ってきて、あたしに身体を沿わせました。口づけには、よく知らない薬品と煙草の匂いが混じっていました。まるで、後悔でもさせたがっているような執拗さで、あたしの口唇を濡らしていきます。思わず、息が乱れて、細い笛のような音が漏れました。
「静かに」
悪魔は抑えた声であたしに命令し、手のひらで口を塞ぎました。そうしておいて、あたしをベッドに押さえつけ、自らも息を殺すようにして、抱いたのです。
彼の触れ方は静かで、けれど痛いほど強引で支配的でした。身体と魂に杭を打ちつけるように、あたしを捕らえ、繋ぎ止めていきます。それは初めての感覚でした。有無を言わせない力で翻弄され、身動きすらかなわないはずなのに、同時に、とても自由な場所へと、解き放たれた心地がするのです。
待ち望んでいたのはこれだったのだと思うと、涙だけが止めどなくあふれてきます。眼を閉じて、身体に焼き付けられていく感覚だけを味わいながら、あたしは祈ることしかできませんでした。あまりに安らかで、残酷な、この時間が終わるまえに、壊れて消えてしまいたいと。
悪魔との関係は一度では終わりませんでした。あたしを愛し、ここから救うと約束してくれた恋人ができてもなお続いたのです。そんなあたしの不実を、黒鳥姫は嘲り笑いました。彼女はいつも、あたしが悪魔にめちゃくちゃにされた朝、居たたまれないような後悔に責められているときばかりを狙って枕もとに現れるのです。
「また、彼に遊んで貰ったのね。良かったでしょう?」
「やめて…」
「ひどい顔よ。青ざめて、憂鬱で、そのくせ卑猥。その顔で王子様に会うつもり?」
黒鳥姫は悪魔の娘で、あたしでも見惚れるほどに綺麗なひとでした。立つ姿にも、声にも、しなやかな熱と艶があり、その肌といえばまるで、アンティーク・ローズの花弁のようでした。瑞々しく輝いているのに、その色合いには時間を超えた、理屈抜きの美しさがあるのです。
人はあたしたちを生き写しだというけれど、あたしに言わせれば全くの正反対です。それでも周囲の人たちに言わせれば、全く見分けがつかないようでした。だからあたしたちは、時にはそれを利用しました。黒鳥姫に頼んで、あたしの代わりに王子様に逢ってもらうこともあったのです。
善か悪か、光か影か。そんなことはどうでもいいのです。彼女はあたしの理想でした。自由で、したたかで、思った事を怖れず、欲しいものは欲しいと口にするだけの強さがあって。
彼女のようになりたいと、あたしはどれだけ願ったことでしょう。
NEXT
|