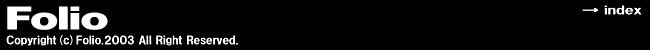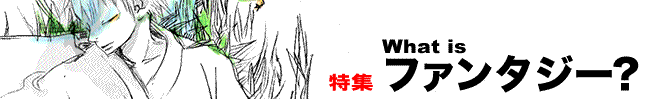| 1/2 |
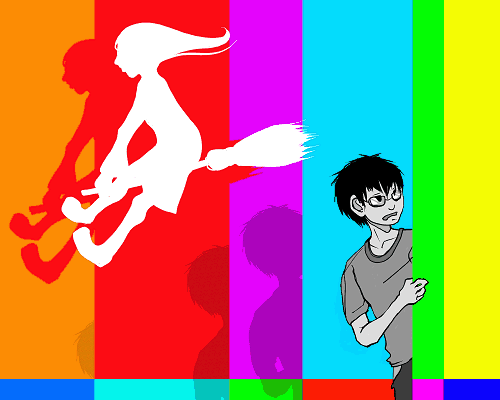 |
| イラスト 甲斐 |
夜の風が吹いた。虫の声が高くなり、部屋の気温が少し下がったようだったので、俺は後ろを振り返った。カーテンがひらひらと揺れている。その隣、月光を背負って、窓際に影が座っていた。 「こんばんは」と少女が言った。 「こんばんは」俺は視線を机に落とした。「アンタが誰だか知らないし、どんな用かも分からない。どうやってその窓に辿り付いたのかも興味ない。不法侵入で訴えたりもしないから、帰ってくれないか」 時計を見ると、時刻は午前一時を回ろうとしていた。軽く舌打ちして、数学の問題集に頭を切り替える。あと三十分で一ページこなさないと、筋トレの時間に間に合わない。高校に進学するつもりはなかったが、人並みの学力もない自分なんてごめんだった。 「ずいぶんマイペースだね」 どこがだ。震えるシャープペンシルを見つめながら深く息を吸い込んだ。見ろ。こんなにも気が散っている。三階にある俺の部屋の、それも鍵のかかっていた窓を音も立てずにこじ開けて、挙句の果てに忍び込んできた見知らぬ女を気にしない人間がこの世に存在するものか。 「気にならないの、私のこと」 俺は諦めて振り返った。少女の長い金髪が秋の夜風に揺れていた。 「気になるね。大いに気になる。どうやってこの部屋に入ったのかももちろんだけど、特に」と俺は少女の手元を指差した。「そのセンスのない法衣みたいな服と、手にもってる箒の用途が非常に謎だ」 少女は声を上げて笑った。それから俺に向かって、おもしろいね、君、と笑いかけた。 「部屋にはね、空から飛んできて窓の外から鍵を外して入らせてもらった。法衣着用は規則。私はもっとかわいい服の方がいいんだけど。箒は空を飛ぶのに必要だから持ってる」少女はニッコリ笑う。「他に質問は?」 「沢山ありすぎて困るくらいだけど、とりあえず三つだけ聞きたい」俺は頭を抱えた。「これは夢? 俺は正常? アンタは何者?」 「現実。ちょっとひねくれてるっぽいけど正常。私はただの魔法使い。名前はサリー」 「なるほど、夢か」 サリーという名前の魔法使いだなんて、どう頑張っても笑ってしまう。どこのアニメだ。テクマクマヤコン。 「夢じゃないって。ほら」と言って、サリーは箒にまたがった。「ね、飛べるでしょ?」 確かにサリーの体が窓の外に浮いているようだったので、俺はほっぺたをつねってみた。痛い。そうすると、少なくとも夢ではなさそうだ。 少し考えてから、とりあえずコイツは魔法使いなのだと結論する。そうすると一番シンプルに理解できそうだ。俺がいるくらいなんだから、広い世界に魔法使いがいてもそこまで不思議じゃない。 「分かった。理解した。で、魔女が俺に何の用?」 「魔法使いと魔女は同一じゃないんだけどね」とサリーは不満そうに目つきを鋭くした。「別に用事なんてないよ」 「用事がない? ふむ。ということはアンタは平日の午前一時過ぎに何の関係もない善良な中学三年生の部屋に遊び半分でおしかけてきたわけだ」 「あ、もしかして明日学校? ダメじゃん、夜更かししちゃ」 論点が違う、と怒鳴りそうになるのを辛うじて堪えた。 「俺は学校には通ってないからいいんだよ。自分で言うのも変な話だけど、いわゆる引き篭もりってやつ。で、遊び半分ならそろそろ帰ってくれないか。勉強の途中なんだけど」 サリーは唇を尖らせた。 「遊び半分っていうか、間違えただけ。私、ちょっとした仕事してるんだけど、この辺から嫌なオーラ感じたんだよね。だから近くに飛んできたわけ。そしたら途端にオーラがすごく弱くなって見分けがつかなくなっちゃった」 「それで?」 「頑張って探ってみたら、この部屋から変なオーラが少しだけ漏れてたから来てみた」サリーは俺の部屋を見回して嘆息した。「でも、君は普通の人みたいだから、間違えたんだなって。でもおかしいなあ、何か変な感じなんだけどな、君」 コイツは本当に魔法使いなんだろうと確信した。 「ところで、君って本当に引き篭もりなの? 何で? 体格も悪くないし、勉強もちゃんとしてるみたいだし、顔だってそこそこイイ線いってるじゃん。ちょっと性格ひねくれてるけど、普通に話せるし」 「引き篭もりだからって向上心がないわけじゃない。勉強もするし筋トレもする。俺は人と話せないだけ。そもそもこんなに人と話したのだって久しぶりだ。周りに言わせれば対人恐怖症に入るらしい」 そこで気付いた。俺はどうしてこんなに普通に喋っていられるんだ。 「そうは見えないけど」とボヤくサリーの姿を見ると、やっぱり無色だった。信じられない。さらに目に力を込めて凝視しても、サリーの体にはやっぱり色がなかった。無色の人間を見たのは初めてだった。 「え、ちょっと待って」 サリーが慌てたように俺に近づく。視線を絡め取られる。サリーの青い、きれいな虹彩が俺の目を覗きこんでいる。 「これ、天然もの? だよね、うん。そっか、目がイってるんだね。ははあ、だから引き篭もってるのか。すごいよ、君。日本人の異能者なんて滅多にいないんだから。なるほどねえ、だから変なオーラが出てるのか」 「は?」 「君の目って変な力持ってるでしょ。透視能力? 千里眼? まさかメドゥーサの眼力ってことはないよね? バロールだったら私、君を捕獲しなきゃならない」 見抜かれてると思った。やっぱりサリーは魔法使いだった。 「そんな大したモンじゃない。アンタの言ってることの半分も俺には理解できない。ただ」自分の瞼に触れてみる。「色が見えるんだ。相手の考えてることが色で見えるだけ。敵意は赤、同情は紫、愛情は青」 「ふーん。識別眼の一種か。あ、私の色は見えてないでしょ? いちおう、それなりの防御してるからね」 俺から離れてサリーは笑った。 「じゃ、もう行くね。久しぶりに人と話せて楽しかったでしょ?」 俺は答えなかった。何を言っても嘘になるような気がした。 「またねー」 サリーは手を振りながら箒にまたがり、窓から出て行った。時計を見ると、二時を回っている。俺はため息をつきながら今夜の分の筋トレを諦め、電気を消してベッドの中にもぐりこんだ。 「そういえば」俺は呟いた。「またねって、また来るのか、アイツ」 毒づきながら、なぜだか悪い気分にはならなかった。 チャイムが鳴ったのは翌日の正午過ぎだった。両親ともに働いているので、家には俺しかいない。俺は食べかけのラーメンから箸をあげて、インターフォンを取った。幸いなことに電話やインターフォンでの会話ならば色が見えないので問題ない。
|
||