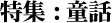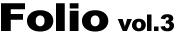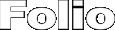ひとりは色白で、どこか夢見がちな眼をして、ちょっと落ち着かないようすでしきりに帽子に手をやっている。もうひとりはよく陽に灼けたようなカフェオレ色の肌をして、大人びた--あるいは大人っぽさを努力して装ったようなふてぶてしさで宙をにらんでいる。ときどきいつもの癖で、座った両足を前に投げ出しそうになるけれど、それを実際の所作に移すまえに、ぎくりと顔をこわばらせて両膝をかかえ直す。
今、二人は、橋のちょうど真ん中の窪みに引っ込んで、日除けのあずまやの下に隠れている。周りが暗くなって、人の気配がなくなれば、外に出ていくこともできるかもしれない。けれど、今はだめだった。ほとんどぴったりくっつきあうようにして、じっと身をひそめているしかなかった。それでも、橋の下を流れる川が、さらさらと心地よい音を奏で続けていてくれるので、ことさらに息を殺さなくてもよかったし、小声で話をしようと思えばすることもできた。
まだ、日が落ちるにはだいぶ時間がある。夢見がちな目をした少年は溜息をつく。二人は知り合ってからまだ間がない。このあずまやで偶然出会って、それからなんとなしに一緒にいる。さっきチラリと横目でうかがったとき、カフェオレの肌をした少年が怪我をしているのが見えた。服の脇腹に滲んだ血。それを覆い隠すように、なかば背を向けて身体を堅く丸めている。夢見がちな目をした少年は、首をひねって、浅黒くなめらかな顔をのぞき込んだ。
「痛くないのか?」
「痛いさ」
カフェオレの肌をした少年は短く応え、少し顔をそむけるようにした。夢見がちな目の少年は、拒絶されたことに傷つかなかったふりをした。
「名前を教えろよ」
「嫌だね」
「名乗るのが嫌ならイニシアルでもいい。僕はR、アールだ。君は」
「…ジェイ」
日が落ちるまでは、ここにいるしかない。「君」と馴れ馴れしく呼ばれるのが不愉快で、ジェイは短くイニシアルを告げた。アールは声を穏やかに落としてジェイに呼びかけた。
「怪我を見せろよ」
「余計なお世話だ。大した傷じゃない」
「そう思ってると、あとから命取りになるんだ」」
ジェイはきっと、自分に身体を触らせはしないだろう。アールは身体の脇に置いていたナップザックをジェイに渡す。大した備えはないけれど、消毒薬とガーゼくらいなら入っている。
「使っていいから、自分で手当しろよ」
ジェイは不審そうに袋を眺めるが、やがてひったくるようにそれをつかんだ。アールに背を向けて自分のシャツをはだけ、消毒薬を含ませたガーゼを傷口に押し当てる。陽に当たっていないところの肌も、遠火でじっくりと焦がしたソースのように香ばしい色をしている。
透明の消毒薬は肌に触れると微かに泡立ち、止まらない血液と混じって流れ落ちた。こんなもんじゃまるで効きやしないと無言で思ったが、それ以上の手厚い処置をアールに期待するわけにもいかなかった。ガーゼを強く押しつけて、そのままゆっくりと背を倒すと、やがてこわばった背中が、アールの背にこつんと触れた。ふたりは背中合わせに座ったまま、ただ川の流れる音を聞いている。
| 1 / 3 | Next |