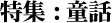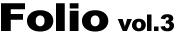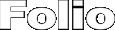規則正しいリズムに、むかし学校で見たメトロノームを思い出す。音楽室のピアノの上においてあった角錐形のオブジェ。重りを下げると触れ幅が小さくなり、刻まれるリズムはどんどん速くなっていった。ラルゴ、アンダンテ、アレグロ、プレスト。この鼓動はどのくらいの速さだろう。
ふいに、アールの背中が小さく震えた。漏れてくる息の音で、笑っているのだとわかる。笑われてようやく、自分がむかし習った歌をハミングしていたのだと気がついた。
「その歌、知ってる。アヴィニョンの橋で、踊るよ、踊るよ」
ジェイはきまり悪くなって口をつぐんだが、アールは全く気にしていない様子でつづきを歌いはじめた。
「兵隊さんが通る お坊さんが通る 」
若い娘が通る、楽士が通る、酔っぱらいが通る…
アールは歌うのをやめてひとつ息を吐いた。
「昔、その歌を描いた絵本を持ってた。アヴィニョンの橋は本当にあるんだと思ってた。世界のどこかに、年がら年中お祭りみたいに陽気にしてる橋があるんだって…」
それは時代がかった跳ね橋で、普段はよそよそしく両岸に離れて上を向いている。一日のうち一時間だけ橋が降り、人々はそこを通ることができる。渡りきるのに、まっすぐ歩けばせいぜい数分しかかからないだろう。でも、アールの想像の中では、その橋をまっすぐ抜けていく者はいなかった。
だって、その橋の上にいる間は、誰もがまったくの自由だから。金持ちも貧乏人も、主人も使用人も男も女も。陸の上でどんなしがらみに絡まれているもの同士も、ここでは争う必要がない。憂き世の身分は全部忘れて、楽士のアコーディオンが奏でる旋律にあわせて踊っていられる場所があると信じていた。
「ずっと行ってみたいって思ってたんだ。いつの間にか忘れたけど」
夢見がちなアールの眼が、さらにけむって雲を追う。その表情は見えなかったけれど、ジェイは間をおかずにアールの空想を一蹴した。
「馬鹿馬鹿しい。ガキみたいなことを」
「ガキの頃を思い出してるんだから、当然だろ。なあジェイ、僕たちはいつ童心を失ったんだろう?」
「考えたこともないね」
「それでもさ、昔は、ジェイだってあったんじゃないのか? 童話を読んでもらって…夢みたいな世界が、世界のどこかにあるんじゃないかと信じていた頃が」
「さあ、どうだっけな。あったとしても、そんなもんは早く捨てたいと思ってたからな」
いつから自分が子供じゃなくなったかって? 苛立ったジェイはひとつ舌打ちした。それは多分、人の世話がなければ生きられない幼な子であることを止めて、すぐのこと。集団の中に放り込まれ、強さと冷静さと判断力、そして我を殺すことを要求された。まわりの子たちが親を恋しがって泣くのを嘲るように見下ろしながら、ジェイは自ら進んで、少しずつ自分の童心を殺していった。
だからといって、それはそんなに悲しむべきことなのか? ジェイはあきれ半分で嘆息する。今までくぐり抜けてきた人生の過酷さを思っても、自分が致命的な何かを失い、不都合を被ったことはなかった。
「子供時代なんて、むしろ時間の無駄じゃないのか? お伽話なんか信じていられるのは、生まれてからせいぜい数年だろ。その後は…」
その後は、うんざりするような反証の繰り返し。奇跡は決して起こらないし、自分が英雄や主人公になることはありえない。幻想は打ち消され、夢は現実に上書きされる。優しい声で物語を聴かされる幸福な時間は、喪失と幻滅のための下準備でしかなかったのだ。
「だとしたら、そんな時間、最初からないほうが合理的じゃないか」
なんで自分はこんなに必死に自分の主張を通そうとしているんだろう、奇妙な息苦しさに耐えながらジェイは思った。黙って眼を閉じていたほうが楽なのに、こんなにむきになって、何にすがりつこうとしているんだろう?
いつまでも夢なんか信じているのは、弱くて愚かな奴らばかりだった。必要なのは一日も早く現実に順応し、大きな機械をスムーズに回していくための部品になることだった。何も考えるなと繰り返し言い聞かされ、その上で新しい知識とイデオロギイを詰め込まれる。今のいままで、それが成長することなのだと信じていた。
| Back | 2 / 3 | Next |