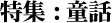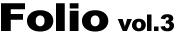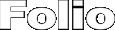波、といっても砂地に這いつくばってずるずると海へ連れ戻される薄くて貧相な波ではない。深く豊かな黒い海が空気に触れて大きく深呼吸する、海に被さる海のことだ。ゆっくりと立ち上がる、真っ白なしぶき、波の音、黒々とした溶液の中で無数のイオンが掻き回される、揺れる音、次々と、無限の広がりで海は波を奏で続ける。
彼女は目を閉じて波の音を聞いていた。彼女の頭の中には巨大な一塊の黒い液体が体をくねらせて躍っている映像がありありと再生されていた。何度もこの音を聞いているせいだろう、彼女には波の上に降り注ぐ日光の量まで想像できた。
彼女はこのCDを、古びた電気屋のガレージセールで手に入れた。まるでゴミ捨て場のような一角。風にさらされ放置されたワゴンの中から、たまたま手に取ったCDがこの「波の音」だった。たまたま―――このことは、彼女にそのCDを買わせるのに充分な理由だった。
一昔前に流行った、イヤシミュージックという代物だ。水の音や鳥の声を録音して、クラッシック音楽と合わせたりするやつ。彼女はすすけたプラスチックケースを手に取ると、ジャケットの写真をじっと眺めた。絵葉書のような外国の海がプリントしてあった。裏返す。楽器の紹介などは書かれていない。演奏者の名前もない。波以外の音は入っていないのだろうか、南の海で録音しました、というアバウトなキャッチ文句が書かれていた。彼女はコイン一枚でそれを買って帰って来ると、恋人の帰りを待って、恋人と一緒にそのCDを聞いてみた。彼女の恋人の反応はイマイチだったが、彼女はすぐにこのCDを気に入った。
こんな単調な音を聞き続けていたら頭が変になりそうだ、と彼女の恋人は言った。こんなもの買ってこなくても、うちに何でもあるじゃないか、とも言った。ポップミュージック、エンヤ、ボサノバ、ジャズ、ロックミュージックだってある。しかし、彼女は首を振った。
「向こうに誰かがいるのは駄目なのよ」
「そう?」
と、彼は首を傾げて、明日も早いから寝る用意をしようと言った。彼女がCDを止めると、彼は歯磨きをしに立って去った。
2.失った声
彼女は波の音を聞きながら、冷めていくクリームシチューの二つの皿を横目で眺めていた。テーブルの上のクリームシチューは既に湯気をたてるのを止め、表面が白く固まりつつあった。しかし、冷めていくことが問題ではない。また温めなおせばいいだけだから。問題は、いつ温めることができるかだった。
部屋には彼女一人だった。ようやく、夜になったと彼女は思った。彼女は闇に沈んだ窓の外を眺める。向かいのマンションの階段に設置されたオレンジ色のハロゲンランプが、まるで月のように光っていた。本物の空はここから見えない。
彼女は壁際に配置されたベッドに膝を立て、壁にもたれて座っていた。彼女の頭の上にはアルミ色の平たい時計がぶら下がっていて、カチカチと時を刻んでいる。と同時に、部屋の中は圧倒的な海の音に支配されていた。
カチカチ
彼女はしばらくの間、首をひねり頭の上の時計を眺めていたが、いくら見上げ続けても動く気配を見せない怠惰な針たちにうんざりして眺めるのをやめた。彼女は時計を眺めるのをやめたが、かといって他にすることもなかった。折畳まれた携帯電話を広げて、画面を見るともなしに見て、再び閉じた。それから途方に暮れた彼女は、自分の膝に顔をうずめてじっとしてみた。彼女の長い髪の毛が彼女の肘をさらさらと撫でていく。彼女の髪と彼女の首筋の間に大切にこもっていた熱がふわりと彼女の鼻先から逃げていった。目をつむる。うねる波、躍る海。
向こうに誰かいるのは駄目なのよ、と彼女は頭の中でもう一度自分のセリフを繰り返した。CDの向こうで、誰かが魂を込めて聴衆のために歌っている、演奏している。わたし以外の、多くの聴衆にだ。わたしは、彼らの演奏を受けとめられる気がしない。聞く資格がないのかもしれない。彼らの才能溢れる演奏はまるで何も持っていないわたしを責めているようにさえ聞こえる。だけど、少なくとも海は、わたしのために歌っているのではない。わたしがここにいようがいまいが、海は海で相も変わらずどこかで波を奏でているのだ。
波の音は部屋中に満たされているが、彼女の体の中は空っぽで彼女はその空白を埋める術を知らなかった。このまま寝てしまえれば、楽なのだけれど、と彼女は膝の内側で呟いた。眠ることさえできれば時間をショートカットできる。一人でいる時間なんて少しもいらない。早く過ぎてしまえばいい。彼女は足を動かし、少し姿勢を変えた。そして膝の上に額を乗せたまま、眠ろうと努力した。彼女が呼び続けても眠りはなかなか訪れてくれない。眠ろうと努力して眠れない時間は、いっそうのろのろと過ぎる、と彼女は感じた。まるで時間が彼女の無駄な努力を見ているのに飽きて代わりに眠り込んでしまったかのような停滞っぷりだ。
そのとき、時間がようやく置きあがり、体を伸ばしてあくびをした。彼女は顔を上げた。彼女の携帯電話が鳴っていた。
「ごめん、もう少しかかる。今日は外で食べるから、先に食べてて」
電話の向こうで彼女のいとしい恋人の、忙しそうな声がした。彼女は生温い海から岩に上がり顔を出すと、重い体を引きずりながら陸によじ登る。彼女は肺を突き刺すほどに冷たい大気をいっぱいに吸って、静かにゆっくりと吐いた。それから、携帯電話を握りなおし、なるべく快活に聞こえる声で答えた。
「ええ、分かったわ」
彼女の失った方の声は彼には届かないのだった。
3.陸へ上がる
彼女にとって彼に会うために飛行機に乗ったことは、たとえば海で暮らしていた人魚姫が陸に上がることを決意したようなものだった。もちろん、いくら彼女が片田舎からトーキョーへ出て来たからといっても、海から陸へ上がる人魚姫のカルチャーショックとは比べようもないけれど。でも、勤め始めて一年足らずの仕事を辞め、今まで住んでいたワンルームを引き払い家具も一切処分して、友人にも親にも黙って暮らし慣れた地を旅立った彼女は、もうもとの海に戻る気はなかったし、陸での幸せな生活だけを夢見ていた。
突然身一つで現れた彼女を、彼女の恋人は優しく抱きしめた。彼女の行動に驚いてはいたが、帰れとは言わなかった。彼女は彼の部屋に居候することになった。
居候を始めて3日目、彼女は、ベランダで洗濯物を干しながらふと、恋人が帰れとは言わなかったけれどよく来たねとも言わなかったことを思い出した。
| 1 / 3 | Next |