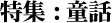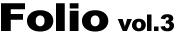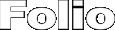彼女は彼の部屋からほとんど外へ出ることはなかった。夕飯の買物のために外へ出たとしても、他の主婦たちのようにカゴを片手にぶら下げて棚の商品を品定めしたりしない。俯いたまま、適当な野菜と肉と牛乳と、自分の食べる分のカップラーメンをカゴいっぱいに詰め、早足でレジまで行く。それからビニール袋いっぱいの商品を両手に提げて、人目を避けるように早足で部屋へと帰る。これで四日は外に出なくて済む。
「せっかく東京に来たんだから、どこか遊びに行けばいいのに」
ある夜、彼女が一歩も家から出ないのに見かねて彼女の恋人は言った。
「一人じゃどこに行ってもつまらない」
と、彼女は言ってしまってすぐに後悔した。彼の顔が明らかに曇ったからだ。
「俺は忙しい」
「ええ。もちろん、知ってるわ。言ってみただけよ。どこに行ってみようかしら」
彼女は観光で頭がいっぱいになったふりをした。これ以上愚痴を言うと言ってはならない言葉が口を出そうになったからだ。
―――せっかく来たのに。
彼は何と言うだろう? 来いなんて頼んでない、と? そうなれば彼女の物語はここで終わりだった。
彼は安心したように微笑んで、トーキョーの名所を数え上げた。彼女は上の空で、楽しそうな彼の顔を眺めていた。もちろん、彼女が一人でそれらの場所へ行くことはなかったけれど。
彼女はもともと特に室内が好きという性質ではなかった。トーキョーに出て来たばかりのときは、近所をうろうろして古ぼけた電気屋で例のCDを手に入れたり、電車に乗って人込みの中へ出かけたこともあったのだった。しかし、あるとき、突然自分が世界から切り離されたような思いに襲われた。目の前の光景が白く煙り、騒音が遠く溶けていった。突然彼女を襲ったその思いは、彼女をパニックに陥れた。心臓がどきどきと高鳴り、額からは暑くもないのにだらだらと汗が噴き出した。彼女は人込みを避けて歩道の隅に座り込む。落ちつけ、落ちつくのよ、と彼女は自分に言い聞かせ、ふっと体の力を抜いたその瞬間、
―――わたしはここで何をしているのだろう?
と、思った。気がつくと、周りは他人で溢れていた。彼女はここでは何者でもなかった。彼女の名前を知るものはいない、彼女の名前はこの土地のどこにも刻まれていない。彼女はコートの衿で顔を隠すようにして街を飛び出すと、電車に乗って彼女の恋人の部屋に戻った。鍵を掛けて、洗面台の蛇口をいっぱいにひねり、手を洗い続けた。それから、少し落ちついてCDプレーヤーのボタンを押してCDを再生した。スピーカーからは単調で何の意志もない波の音が繰り返され始める。
彼女は、それ以来外へ出るのに相当な努力が必要になった。出歩くことが苦痛だった。しかし、彼女が外に出れない理由を彼女の恋人は決して理解できないだろう。なぜなら、彼はこの場所で既に名前を刻み物語を始めているからだ。彼女は歩くたびに痛む足を彼から隠しながら、バイトを見つけたら? 就職活動は? 何か習い事でもしたら? という彼の言葉に、失った声で答え微笑むしかないのだった。
5.波の音−2
波の音は始まりも終わりもない。一つの終わりは次の始まりに滑らかに続いている。視界の続く限り広がる波が月明かりの中、上下する。彼女は目をつむって波の音を聞いている。波の音に包まれたこの部屋は海に浮かんだ船のようだった。
6.失った声−2
彼女の恋人は彼女が作った夕飯を食べることがほとんどなくなっていた。最近は電話の連絡すらない。彼女は一人分の食事を作るのも億劫だったので、レトルト食品やカップラーメンで簡単に一人で済まして、空いた時間はひたすら彼を待ち続けた。
彼女の恋人は大抵、深夜過ぎに帰って来た。酔っているときもあった。彼女の恋人は、部屋の真ん中で座っている彼女を見ると、「今日もどこにも行かなかったのか?」と尋ねた。彼女が肯くと、時間の浪費だ、と呟いた。それから明日も早いから、と言ってシャワーを浴びに浴室へ行き、湯気の立つ体で素早く身支度を整えるとベッドに潜りこんだ。彼女も彼の隣に潜りこんだが、彼の手が彼女の体に伸びてくることはなく、直に軽いいびきが聞こえてきた。
―――わたしはただ、あなたと一緒にいたいだけなのに。
と、彼女は叫んだ。しかし、これも失った方の声だったので彼には届かなかった。
7.陸に上がる−2
彼女はぼんやりとテレビを眺めていた。今まではテレビなんてまともに見たことはなかったが、一旦スイッチを入れてしまえば街の騒音と一緒、消す必要性すら感じないほどのただの背景だった。その代わりに彼女はCDを止めた。
テレビは刻々と姿を変えてあらゆるものを映し出す。人間が立ち代わり現れたり消えたりしては、笑ったり泣いたり怒ったりした。それが16インチの箱の中で演じられる。彼らは、別にわたしのために笑っているのではないのだろう、と彼女は思った。彼女はテレビの画面に波の音と同じ安堵感を覚えた。
確かに、彼の言うことは正しい、家にこもっているから余計に寂しくなるのだ、と彼女は思った。テレビの中の小さくて均一な世界を見ていると、彼女は少し勇気が出てきた。彼の言うように何かをするべきだ、と思った。彼女は彼から借りているだぶだぶのジャージを脱いで、自分の服に着替えた。髪を整えて、化粧をしようとして、化粧は止めた。すぐ近所に行くだけだ。
彼女は部屋を出ると、エレベーターから1階に降りた。それから5分歩いてコンビニエンスストアの自動ドアをくぐった。いらっしゃいませ、こんばんは、と店員が彼女に向かって笑いかけ、彼女は慌てて奥へ進み棚の影に隠れた。彼女は、文房具の棚を何度も行き来して履歴書の用紙をようやく見つけ出した。そして雑誌コーナーで、適当なアルバイト情報誌を手に入れた。ありがとうございました、またお越し下さい、という声に送られて彼女はコンビニエンスストアを出る。コンビニエンスストアの店員は24時間同じ文句を繰り返し続けるのだろう。彼らにとって、相手が何者でもないことなんて関係ない。不時着して地球に辿り着いてたまたま立ち寄った宇宙人にさえ、彼らは躊躇なくまたお越し下さい、と言うのだろう、と彼女は思った。
家に帰った彼女は、ベッドに座ってアルバイト情報誌を広げると、ぱらぱらと眺め始めた。ページをめくっているうちに、気がつくと募集のページは終わっていた。次にもう少し気合を入れて詳しく眺めた。しかしどの情報も黙って俯いたまま彼女の前を通り過ぎるだけだった。彼女は雑誌を放り投げかけたが、もう一度だけ開いた。そして今度は、彼が帰って来るかもしれない時間に被らないような、もっと言えば彼が帰って来たときに夕飯が準備できている状態に間に合うような時間帯に限定して、機械的に情報を選別した。それから、彼と一緒に過ごすことのできる日曜日と祝日に入らなくてはいけないバイトをその候補の中から消した。最近は日曜日も仕事だと言っては出かけ、彼女の恋人が彼女と過ごすことは滅多になかった。が、それは考えないようにしなくてはいけない、と彼女は自分に言い聞かせた。彼は忙しいのだ。彼女は、残ったものの中から一番近いところにある仕事を選び出して、蛍光ペンで丸をつけた。
彼女はさっそくその会社に電話をした。受けつけは20時まで、とあって、まだ15分の余裕があったからだ。電話には、忙しそうな中年の男の声が出て、事務的に彼女の名前を尋ね、面接の日時を決めて、履歴書を持参するように、とだけ言った。彼女は何か喋ろうとしたが、電話はすぐに切れてしまった。彼女はツーツーと鳴り続けている携帯電話のボタンを押して、音を止めた。とにかく、面接の日時を決めた。次は履歴書だ。彼女はビニール袋から履歴書の用紙を取り出してみて始めて、証明写真を撮る必要があったことに思い当たった。証明写真? 今じゃ街のいたるところに設置されている証明写真機で簡単に取ることができるけれど、いざ必要となったら、どこにあるのか少しも思い出せない。
彼が帰って来たら聞こう、と彼女は思ってみて、微笑んだ。彼が帰って来てお風呂に入って、一息ついた頃に、何気なく思い出したみたいに彼女は尋ねるのだ。
「ねえ、証明写真の機械がどこにあるか知らない?」
彼は、なぜそんなものが必要なのか彼女に尋ねるだろう。そして彼女がアルバイト情報誌を手に入れ、その中から一つの会社に電話し、面接の日時を取り付け、3日後に面接に行くということを聞くだろう。彼女にはそのときの嬉しそうな彼の顔がありありと想像できた。
彼女は履歴書の用紙を注意深く取り出すと、ボールペンで与えられた欄を埋めていった。住所の欄は開けておいた。これも後で彼に聞かないといけない。テレビはさっきからずっと喋り続けているが、彼女には風の音ほどにも気にならないようだった。
彼女は彼が帰って来るのがいつもよりいっそう待ち遠しかった。しかし、その夜、深夜を過ぎても、彼女の恋人は彼女の待つ部屋に帰って来なかった。
| Back | 2 / 3 | Next |