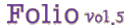ある日テレビが唐突に映像を流し始めた。
嘗てないほどの鮮明な画像だった。以前と同じように、リポーターがマイクを持って、ある宗教団体がテロを起こして、数百人の死者が出たと報道していた。嘗てない惨事です。これほどの大勢の命が失われたことはありませんと興奮気味の推定38歳の女性レポーターに、背後から男が近づいてくるのが見えた。背後は人が固まった様子で、そこで何が行われているのかは判別がつかなかったが、騒がしい様子だけは見てとれた。男はレポーターに近づくとにやりと画面を見て笑った。そして、レポーターの頭部に銀色の物体を押しつけた。衝撃音がカメラを伝わった。レポーターの頭部が破裂して身体が崩れ落ち、その銀色の物体は銃だったのだと遅れた思考が認識した。それは一瞬の出来事だった。途端、カメラが揺れて、映像は流れた。カメラは地面に放り出されたようだ。テレビの中でカメラマンが地面に横たわる瞬間が映し出された。
一瞬のブラックアウトに続き、テレビはスタジオの様子を映し出した。慌てた様子のコメンテーターがテーブルで二人、大変なことになりました。大変なことになりましたと、繰り返した。これは戦争ですと言った。市内で反乱が起きています。レポーターの柴崎さんは、暴徒に殺されてしまいました。ご冥福をお祈りいたしましょうと、繰り返すが、突然に映像は砂嵐に戻り、Aは捨て置かれた。
このMの外ではこのような事件が起きているのだろうかと想像した。唐突に途切れてしまう映像が憎たらしく、すべてを教えてくれと願い、そしてもう映らないテレビを蹴りつけ痛みに苦しんだ。かなりの強度で足を打ち付けたのだろう。小指が痛い。折れたのかもしれない。Aはベッドの上で足を抱えて苦しみ、それ以降歩くに不自由をするようになる。
AはいつしかMから救ってくれる誰かを希求していた。それはきっと無駄な望みだったのだろう。部屋の中は相変わらずにかわりばえはしない。調度といえるものは映らないテレビと、ベッドだけだ。部屋の隅に食べた跡の食器が積み重なり、汚れが乾いて醜くく臭った。Aは長い思考を中断して食器を割った。破片で窓の下の壁に傷を付け始めた。どれほど厚さの壁だろうかと考える。掘って向こう側に脱出できるかも知れないと願う。食器の破片は壁を掘り進めるのと同時に自らの手を傷つけて、痛さをこらえつつ古い映画で地面に穴を掘って収容所を抜け出す行為を描いたのがあったのを思い出す。同じ破片で喉咽を掻き切ることもできた。だが抜け出したい。ただ、その一点でAは生きながらえることを望み、たとえそこが戦場になってしまったのであったとしても、外の世界を見たいと希求した。
壁の穴への従事は飽きるほどの閑居と低回しがちな思考からAを開放した。作業は一向に進んだ様子はなかったが、ただ無心になれればよいのだとAは考え、苦行僧が一心に仏像を彫るのと同じように壁を掘り続けた。その間に、幾分かの記憶が蘇ってくるのがわかった。どこかの喫茶店だか料理屋のテーブルで、見知らぬ女性とAは対峙していた。あなたとわたしはまるで違うのよ、とその女性が答えていた。違う。なにが違うのだろう。Aは違ってもいいと答えたはずだった。だが、いいえ、あなたはあなたしか見ていないのよと答え、Aはそんなことはないと答えた。あの答えは正しかったのだろうか、とAは煩悶する。いや、認知論において、自己の主体が認識しているのが、その主体にとっての世界なのだ、と言い放つ余裕はなかった。たぶんAはその女性を必要としていた。必要としていることを言い表すすべをAは有していないのだ、と悲しみながらそう言いもし、だからこそこのような部屋に送り込まれたのではないか、と妄想した。
別の記憶はAは砂漠の中で放浪していた。遠くの蜃気楼以外は何も見当たらない灼熱の砂の地平でAは何かを探していた。探していたものは何だったのだろうかとAは考えるが、考えが及ばないこと/ものだったのだろう。遠くにあり、蜃気楼の彼方にそれは存在していたのかも知れない。必要としているものから遠ざけられた時に人は孤独を感じるものだ。必要とする行為が孤独を生むと思い、だが、それはテレビで映されたドラマに過ぎないのかも知れないとも考える。どう生きたいのだと問う質問さえ、この部屋のテレビからから与えられた情報なのかとAは考え、どれほどの時間が経過したのか分からないと感じ、冷静に感じる意識と、混乱した意識の狭間に思考が落ち込んだ。この世のすべからく誰も分かりあえない。誰も何かを理解することはない。孤独で成り立つ世界なのだ。AはMの中にいて、そして、永遠にこの場所に繋ぎ止められれるかも知れないと思うと、身体が震える程の恐怖を感じ、もし現実にAの身に起こった出来事がこの部屋に辿り着くために仕組まれたことだったとすると、AはMの中でなくても孤独なのだ。
そう考えが及んでしまうと、現実に誰かXが必要なのかとも思う。あらゆる人と人との間には、このような白い壁が存在していて、ひたすらそれぞれの主体は壁を掘り続けるしかないのかも知れない。そしてAは壁を掘り続けるほかにすることもなかったのではないか。永遠に何もできない場所と言うのは絶望しかない。すべての手段を封じられても人は生きようとするだろう。逆にするべきことが多すぎる時には、選択が多すぎる場合において人は自らの命を絶つことをするのかも知れない。その絶望を受け入れたくはなかった。そして壁の外を一刻も早く見たいと一心に考えた。
ある時、テレビが映像を流し始めた。人々が大勢寄り集まっている映像だった。
「我が国家は自主尊厳の維持と国民の保護を完遂するために、反乱する国民に対して銃を向けることを承認しました。我が国家は、国家の主体に必要な攻撃性を容認いたします。非国民には死を持って償ってもらいます」とマイクを周囲に突きつけられた制服を着た人は、カメラに向かって怒声を浴びるような口調で発言していた。画面が変わり、中年男性のコメンテーターの顔が映り、大変なことになりました、と述べた。女性の方にカメラが移動して、喋ろうとマイクに顔を近づけた途端に驚きの顔をあげて、逃げるようにフレームから消えた。マシンガンを持った黒づくめの男たちが画面のなかに躍り出て、このテレビ局は我らが占拠した。我らの自由と開放同盟が占拠した。これから我らの政権放送を行う。と続けたが、映像が切れた。
断片だけが流されるテレビはAを苛立たせ、慣れることはなかった。窓から外界の音が聞こえてこないか耳を澄まもしたが、何もなかった。変わらず数日毎に食事は差し入れられていた。再びテレビが付いたのはどれだけの時間が経過したのだろう。それ以降長い間、なにも映像を流してはくれなかった。Aはいよいよもって孤独な作業に従事した。
ある時、テレビは我が国家は自主独立を達成した。この国がこの国であるべき姿に回復するには時間がかかるだろう、だからこそ一刻も早く我らの国家を我ら自身が承認しなければならないのだ、と告げた。黒づくめの男はテレビの中で不敵に笑い、この世界を認知すると叫んだ。コマーシャルが挿入されて、牧歌的な田園風景の中で、農民が牛を追っている姿を映しだした。酪農で生まれた新鮮牛乳です。おいしい牛乳です。これを飲んで元気な国民に育ちましょう、と続けた。コマーシャルが終わるとワイドショーになり、誘拐された子供が実は親によって殺されたのだという情報を流していた。一見、隣の家と見分けがつかない郊外の住宅地の中で、その家の周りにだけ人々が集まっていた。警察だろうか。制服を着た人々に捕まれて、やつれた様子の夫婦が玄関に姿を現して、人々が怒声を浴びせかける様子が写しだされた。レポーターがカメラに向かって、粛清です粛清ですと連呼した。両親がブロック塀に並ばされて、周囲からのヤジが飛ぶ中で制服姿の男が夫婦に向かって銃を構えたとき、テレビは消えた。
人の自主独立を規定する行動は、排除から成り立っているのだろうか。Aは考える。外界を拒否していたということは即ち自主的に選択した結果、過去のAはそうしたのだろう。ならばMに取り込まれているこの状態は自主独立であるのかないのか。独立とは食事を与えられ排泄器官としてMという部屋の中で生きながらえることを意味するのだろうか。Mとは謎を含ませて初めて存在することができる器官であり、その内側にAを内包させて初めて成り立つ密室なのではないかと考え、何故、誰、どうして、という問いというのは、AもしくはMの要請によって形成される、クエッションなのであり、それはAの目に見える世界の認識への問いなのではないか。いや、違う。
AはMを規定する条件の一つであるに過ぎない。人は不確定の事象に溢れた外界を認識するために、とりあえずの入れ物としてMという器官を置き、その器官に適合させるための必要条件としてAという存在を提示するのかも知れない。分かりやすい回答と分かりやすい原則がこの世界の秩序を作っているのだ。それは自主独立のためと望むテレビに映し出される人々と同じように、AはこのクエッションQに対して臨んでいるのかも知れない。Aはテレビが再び映像を流し始めるのを待った。だが、いつまで待っても映像は流れてくれず、永遠に取り残された部屋の中で、Aは再び壁に向かう。
与えられる情報に意味は存在するのだろうか。それは恣意的に選択されて、もしかするとビデオ映像や高度な技術による合成された映画のような演劇ではないのか。情報の発信源、つまりテレビに映されている出来事は事実ではないのかも知れない。それを信じるということは情報の発信源の所在を肯定することに過ぎない。だが、事象はAの中で自然に発酵し、勝手に自由気ままに行動し、膨れ上がってAの思考に住み着いてしまう。本来はそうした情報を問いかけてはならないとも感じる。Mはその機能から、問いかけを拒否しているもので、Aに対して情報を与えるがA自身の問題ではなく、M自身の問題であるのだ。
そうか。MはAに見せるための幻影なのだ。と思った瞬間、壁の一部が崩れた。
中からは黒い芯の鉄骨が縦横に走っているのがあらわれた。
鉄骨はAの握り拳ぐらいの間隔で格子状になっており、もし、その格子を人が通れる程の大きさに拡張するのであれば、かなりの大きさの壁を解体せねばならないのだった。Aは絶句し、これまでの苦労が全くの無駄に終わったのだと感じた。あまりの途方もなさにその場に崩れ落ちた。
ベッドに潜り込んだ。テレビは相変わらず砂嵐のままだった。天井際の小さな窓の外には雨が降っていて、力強くガラスに水滴がぶつかるのが見えた。Aは突然呼吸困難になった。咳をするとそのまま酸素が欠乏してゆくのを感じた。シーツを握りしめて息を深く吸おうと努力した。胸が痛くなった。Aは即座にそれが精神的なものからくるものだと直感して、なるべくゆっくりと呼吸をするようにして、長い間苦しみながら、落ち着けたが、冷や汗は止まらなかった。暴れてベッドを蹴ると、板の一部が簡単に剥がれた。Aは生命をとりとめたことを喜んだ。ベッドは解体できるのだ。
組み合わせた板を一つずつ剥がしてゆくのが今度は日課になった。陶器の欠片を板の隙間に差し込んで、少しずつ削ってゆく。壁に比べれば、その作業は容易かった。容易すぎて、その日課が終わり、再び何もできない何もすることがない日々がやってくるのではないかと考えると、薄ら寒かった。