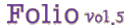数日後にはベッドは見事解体した。Aは歓喜に震えた。小さな引き上げ式の扉がその下からあらわれたのだ。Aは無論
引き開ける。と、その下には同じような部屋があって、ベッドがあって、テレビの代わりに小さなラジオが砂嵐を流していた。
「うわぁ!」
ベッドに寝ころんで天井を見上げていた男がいた。突然真っ白な天井が開いて人の顔が見えたので驚いていた。
「だ、だれだ」
Aは、その男に自分はAだと答えると、男は、じゃあ自分はBだと返事をした。二人はまず状況の打ち合わせをした。部屋MとM’はまるで同じ構造であり、互いに記憶を失い、この部屋で目覚めたという情報は合致した。テレビとラジオから流れた情報は互いに違っていて、Aはこの部屋の外は戦争が起こっているのだと主張すると、Bは、いや、楽園のようだと答えた。
どちらかが間違っているか、どちらも正しいのか、はたまたどちらも間違っているのか、それぞれの断片的な情報では分からなかった。人に会った興奮はやがて失われ、どうしようもない状況に陥ったのだと互いが感じた後に、Bは、「俺もベッドを壊してみる」というと、ベッドを解体したが、そこには下へ通じる扉はなかった。天井と床の間はかなりの距離があったので、Aは下に降りて共に暮らしてゆこうという気にはなれなかった。シーツを垂らしても高さは届かず、途中から飛び降りればどうなるかは知れたものではなかった。
「なあ、どうしたらこの部屋から逃れることができるだろう」とBが呟く。
「ないね。壁を掘ってみたら鉄骨が縦横に走ってて、それ以上は進まない」
「Mとは何だ」
「Mは自己を規定する必要条件だと思う」
「何故、そう思うのか」BはAを問う。
「この部屋は我らを取り囲むことで成り立っているのだ」
「取り囲むことで成り立つのか。なんだか違う気がする」
「なぜ」
「部屋が先なのか我らが先なのかが曖昧だ」とB。
「我らが先であって何がおかしい」
「そもそも人類における住居は固定され、定位置に存在するのが基本ではないか」
「哲学的考えることを知らないヤツめ」
「ならば、こうしてみよう。目を閉じて、この部屋が存在していないと念じ、それを信じ切ってみれば分かることだ」
「我思う故に部屋ありか」
「分からないヤツだな。いまここに存在しているものを、もしそれが仮想的なもので、全く存在してもいないと信じてみることができるか。できたところで、部屋は存在するだろう。それはお前が言う哲学の限界ではないか」
「信じることに成功した者だけが、それが間違いか正しいか判断できるし、信じた者は部屋から脱出できたかも知れない」
「やってみるがいい。俺は寝るよ」とB。
「わかった」とA。
Aは扉を閉じてマットだけになってしまったベッドに潜り込んで、何日も過ごし、それが空想のものだと信じようとした。
数日経っても白い部屋は消えてくれることはなかった。そのうちに食事が出てきて空想が途切れてしまった。一度決定されてしまった嗅覚には勝てないものだ。食事は豚カツだった。
「豚カツ」
「エビフライ」
それからAとBはメニューについて検討した。毎度毎度の食事を付き合わせたが、合致することはなかった。
「この建物は二階建てか、それとももっと高い建物だろうか」
「分からない」
Aは素直に答えた。ここに居るのは二人だけではないという予測も成り立つ。もしかすると別の壁を掘ると隣に部屋が存在するのかも知れないと考えたのだが、もしまた鉄骨があらわれないとも限らない。どこまでが徒労であり、どこからが成果なのかも不明だ。もし隣に部屋があり、人がいる可能性と、外部へ通じる通路が存在する可能性と、鉄骨でがんじがらめにされているという可能性のうち、どれが最も確率は高いだろうか。
Bの部屋のラジオが何か情報を流し始めた。人々の間に「幸福ジュース」が配布されて、その飲み方をラジオは宣伝していたようだ。数日後にAの部屋のテレビが近隣の国家から認証が得られないので、近隣との戦闘が始まった、という。軍備を増強しミサイルを撃ち合っているようだった。AはBに隣の部屋を探すように促した。だが、Bはその誘いに乗らなかった。「やったところで何がある。どうせそっちのように鉄骨を掘り出すのが関の山だろう」という見解だった。Mとは何だという問いを再考することはなかった。
「なあ、A、俺は怖いんだ」
「なんだい?」
「この前から、気になっていたんだけど、壁がだんだん狭まってきてないか」
「壁?」
「そうだ。壁が迫ってきてるような気がする。気のせいか」
「気のせいだろう」
「いいや、きっとこの壁は徐々に俺たちを左右から挟んで潰してしまおうとしている」
「まさか」
「そう。まさかと思うところが奴らの狙い通りなんだ。じっと見てみろよ。だんだん壁が迫ってくるのがわかるはずだ」
「まさか、な」
Aが答えた途端に、Bは突如大声を上げて、いやだ、いっそのこと殺してくれ。生き地獄はイヤだ。殺してくれ。と暴れた。AはBが暴れるに任せた。彼は彼なりにMと戦っているのではないかと思われたからだ。だが、自殺だけは思い留まらさねばならないと思った。自殺されたとしたら淋しくなるなと思い、自分の中に生まれた、その「淋しい」という感情に驚いた。孤独と淋しさは別個のものだ。人は必ず孤独に生まれ付くが必ずしも淋しき生物として生まれる訳ではない。
「淋しい」とはそれまで存在したものが、もしくは存在してしかるべきと認知された事物が主体の側に存在しないことをいうと仮定する。ならばMから我々が脱出してしまったなら、Mは「淋しさ」で自殺でもしかねない。いや、それはストックホルムシ症候群だ。誘拐犯に連れられた被害者が、誘拐犯に同調してしまうあれだ。MがAに与えたクエッションは、Aの存在はMに規定されているのではないか。もしくは規定されながらAはAであり続けることができるのだろうかという問いでもあり、Aを入れる入れ物の存在とは、A’でありつつMではないかという、例の循環する疑問構造に迷い込んでしまった。
そもそも自己とは何か。その答えは永遠の問いとして問われたのではなかったか。答えは問いの中にあるだろう。
Mが半密室で完全な密室ではないことは、Aが暮らす部屋とBが暮らす部屋が連結されているという事実が証明しているが、AはBを朋友とも同居人とも感じてはいない。もしかすると同じ部屋で寝起きをすればそう感じることは可能かも知れないが、共同生活をする程でもなかった。厄介事をこれ以上増やしたくないという思いもあり、恐怖もあった。この白い部屋はそれぞれの聖域なのではないかとも思え、AがBとは別物の存在であるのと同じく、Mに人が規定されているとするならば、それぞれのMも別物ではなかろうかとも思えたのだ。
同じものを見ているようで同じものを見ることはできない。それは人の視野がそれぞれ別物であるからだ。そうするとBの部屋は実はBの言うとおりに幅が狭くなり、徐々にBを押しつぶそうとして迫っているのかも知れない。Aは再び過呼吸の症状が露われるのを感じた。いっそこのまま死んでしまいたいと思った。