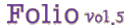久しぶりにテレビが点灯した。
音声がある探検隊がジャングルの奥に眠るソロモン王の秘宝を探していると伝えた。それはドキュメンタリーなのか創作物なのかは判断が付かなかったが、彼らはそれを探していたか探している振りをしていた。要するに謎さえあれば番組は成立するのであって、その謎が切実なものであるかそうでないかなど疑問を呈する必要などない。宝の価値さえもそれほど重要ではない。探検をするという行動その一点において彼らは成立し、行動それ自体が目的であるのだ。Aは冷たい汗が背中を流れるのに気が付いた。
このMという問いはAにとって回答が得られた時に必要のない問題なのだ。すなわちAは回答が得られた際に、Mと共に消滅してしまう恐れするらありえるのだった。それまでずっと一縷の望みを託していた「脱出」という言葉は安易に用いるべきではないものだと気がついた。死にたくないと考えつつ、自死への道を進んでいるのかも知れないのだった。もし仮に脱出し、生き延びられたとする。その場合においてもMとAの関係はもうAの脳裏から拭うことはできなさそうだった。
「もしここから逃れることが、我々の死だとすると我々はどうすればいいのだ」
概要を説明してMとの関係に無頓着なBに思考を促した。だがBはあっけらかんとした表情で「死はいずこでも何者でも逃れられな」と答え、「何故、おまえはMに拘るのだ」とききかえした。
「問い・思考する行為はおまえに何を与えた。時間潰しか、それとも心潰しか?おまえが捕らわれているのはおまえ自身、Aという身体ではないか」
「その身体はMに関わりがあるから問うというのは間違いだというのか」
「ちがう。おまえは問い、おれは受容することの違いだ。おまえとおれの関係で、おまえは圧倒的に有利な位置にいるだろう。おまえのいる部屋とこの部屋を繋ぐのはおまえの部屋にある扉しかないのだ。それを恣意的に開けるのはおまえ。自分だけの世界に閉じこもっているのはおまえ。おれはただ扉が開くのを待っているだけだ」
「非難か?やっかみか?」
「ちがうよ。所詮おまえとおれとは双児型だよ。同じ穴の狢に過ぎない」
「同じではない」
「同じさ。死から逃れられないのと同じくMからも逃れられない。生きると言うこと自体がMでありQであるのだ」
「ならば死ねと?」
「死なずともMとうまくやることはできる。気にしなければいいのさ」
「このまえとは全く逆だな。俺が目を閉じて実験しようとしたのを嘲笑した癖に」
「そうさ。メタ的に考えて見ろ。おまえの外にMがあって、その外にQがあって、いや、QはMの中かも知れないが、その外に?セカイ?が存在して、その?セカイ?を認識しているのはおまえではないか。そしておまえはMの中にいる。この永遠なる循環がMの正体のすべてだ」
「論理が矛盾してはいないか」
「矛盾?それがおれにとっての真実だよ」
「安易に真実などと語るのは子供じみている」
「嘲笑するか?」
「ああ、してやるさ。hahahaha....」
Bが死んでいるのを発見したのはそれから数日経過した後だった。床の蓋を開けた途端、Bの死体を発見して、Aは扉を閉ざした。Bは数十センチあれば自殺できるのだということを実践したようだ。何でもないように見せかけていたが、彼にとって死は遠いものではなかったらしい。Aは孤独を感じた。そして強烈な淋しさを味わった。そして自らも死にたくなった。ベッドの端にくくりつければ可能だろうと考えた。だが、ベッドは解体されてしまっていた。
テレビが点灯した時、「ということが今回の事件の顛末であります」と男の陰が人々に向かって喋っていた。人々が訊く。
「いつ、このトリックに気がつかれましたか」
男はにやりと笑い続ける。
「初めからさ。そう、初めからさ」
Aはテレビを消した。電源を抜いた。そして中断した壁の脱出口を見た。ベッドから起きあがり、以前のように穴に向かった。
一体どれだけの時間が経過したことだろう。Bが死んでから日付を記録してゆくのをやめた。Aはひたすらに黙然として壁に向かったのだった。
壁がかなりの大きさに崩されていた。鉄骨をじわりじわりと曲げてゆくのは至難の業だった。握ったままでミイラと化すかも知れないとも感じた。だが、念願の壁の向こう際につながるひび割れを発見した時に、Aは歓喜してその罅を崩す作業にこれまで以上に没頭した。穴が空き、新鮮な空気が差し込んできた。
穴から覗ける青い空を見つめ、間断なく入り込んでくる風に心を躍らせた。
まだ穴の外を覗き見ることはできなかった。その穴を拡大することに集中した。一部が崩れると後の作業は容易だった。穴の周囲の罅を拡大し、その罅を割ってゆくだけだった。Aは心浮き立てたまま作業をし開放される予感でに感動した。
最後の一部が緩くなったのでAは蹴りつけた。
穴は陥没するように空いた。ガラガラと崩れて向こう側に消えた。ついに空いたのだ!Aは高笑した。
そして、首を突きだして外を覗き込んだ途端に再び絶望した。
Aがいるのは高い塔の上だった。強風がしたたかAの顔を目掛けて吹き上げ、目を開け続けることは難しそうだった。相当に高い石造りの塔の上だった。上を見ると雲に届く程の高さに塔はのびていた。
見下ろすと遙か彼方の地上には住宅と人々が生活する地面が存在していた。豆粒のような車が右往左往していた。家々はマッチ箱で、ビルたちはモザイク画のようだった。たとえシーツをどこかに結びつけても降りることは到底無理だった。Bの部屋であっても無理だったように、それは馬鹿げた振る舞いだった。今までの苦労はまるで無駄だった。このMという密室からは逃れられない。もう駄目だとAは考えた。テレビのコードで首を吊ろう。
だが、その場所で死体となり、腐敗してもきっと食事は差し入れ続けられるに違いないと考えると、何かも無駄のような気分になった。その状況を見るのが怖くてAはBの部屋への扉を閉ざしたままだった。他の壁にもうひとつ穴を開ける程の余力はもうないし、余力があったとしても、それほどの長期の時間を、もう一度自分の身体が持ちこたえられる訳はなかった。
やがて、Aの脳裏にひとつの考えが思い浮かんだ。Aは穴に戻った。そして掘り続けた。大きく開けることができると、まずテレビをその穴から落とした。Aは穴から飛び降りた。これでやっとMを出し抜けるのだ。一方的に与えられる情報を排除し、回答である我が身を混沌の地上に回帰させるのだ。我がセカイは自らの身体と合一するのだ。Mの永遠なるくびきから逃れることができるのだ。Aは落下しながら泣いた。ようやくAの視界に地上が判別できるようになった。