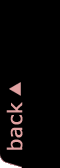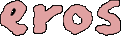と、彼女は言って、手付かずのトリッパの皿を友人の方に押しやった。友人は彼女の反応を楽しむようににやにやしながら、グラスの中のワインを飲み干す。
「でもちょっと分かるでしょ?」
「全然分からないわ」
「そう、それは残念」
彼女は、フォークで突き刺しながらおいしそうに牛の胃を口に運んだ。店員がゆっくりと近寄ってきて彼女のグラスにワインを注ぐと、テーブルの上の空いた皿を下げて去っていった。
「あとはね、ギブスをはめている人とか眼帯をしてる人とか、松葉杖をついている人とかにもエロスを感じるわ」
「あなた、ナース辞めたら?」
「どうして? 天職だと思うけれど」
彼女の友人はそう言って、二人分平らげたトリッパのお皿を押しやり、再び煙草を咥えて火をつけた。煙草を咥えた彼女の友人は黙ってしまった。何か考えているのか、煙草の味を堪能しているのか。彼女はこの隙に店員を呼んで水を頼んだ。もうフルボトルの中身が半分になろうとしている。アルコールに強くない彼女は、友人につきあっていると、限界を超えてしまいそうだと思ったからだ。
「で、エロスとリンゴについての関係だったわね」
彼女の友人は煙草の煙を吐き出すと、その煙を見送るように天井を見つめる。彼女も一緒になってその煙を見つめる。煙は細く、白い筋となってゆっくりと円を描くと天井のライトに溶けて行った。
「私はキリスト教徒じゃないから不謹慎ついでに好きなこと言っちゃうけど、アダムとイブが食べたリンゴはエロスそのものだったんだと思うわ。エロスっていうのは、つまりね。うーん、」
友人の華奢な右手の指に挟まれた煙草の先からは白い煙が立ち昇りつづけ、じわじわと赤い炎が紙を侵食し、筒型の灰が生成されていく。今にも灰皿の上に落ちそうになりながら少しずつ成長して行くその灰色の筒を彼女は見つめている。友人の指が動いた。灰がゆっくりと落下した。落下した灰がほろほろと崩れ粉になった。少し、粉が舞う。
「エロスってのは禁断の中に存在するの。決して食べてはいけない果実を、どうしても食べたいと欲すること、それがエロスよ。ええ、そう、そうね。解剖室の例は極端な例だけれど、それだって当てはまるわ。たとえ私が解剖される遺体となって解剖する学生たちに欲望を感じても、学生たちは決して私に欲望を感じない。感じてはいけない。
逆に手に入ってしまったもの、当然のようにそこにあるもの、いつでも触れられるもの、そんなものにはエロスはないの。セックスしたいって思ったら、どろんと裸の異性が現れたら、誰がそこにエロスを感じることができるっていうの? んー、男はそれでも感じるかもしれないけれど。ね、女は違うわ。
アダムとイブが禁忌を破ってその果実を食べた時、エロスはエロスではなくなって、その果実はただの何でもない果実となった。この世にエロスがなくなったことを嘆いた彼らは、仕方なく自らの体を隠しあって新たな禁忌を作ることで、再びこの世にエロスを生んだわけ」
「はあ、」
と、彼女は友人の考えに圧倒されて間の抜けた相槌を打った。友人は短くなった煙草を灰皿に押しつけてもみ消すと、声をたてて笑った。
「どう? リンゴとエロスの関係が証明できたでしょう?」
「何だか、あなたのこと見直したわ」
と、彼女は友人に言った。
「ええ、任せて。エロスについてはちょっとした専門家なのよ」
と、彼女の友人は赤い唇で笑って、グラスに残っていたワインをつるつると飲み干した。
上へ参ります下へ参りますと言いながら、エレベーターガールの彼女は、リンゴとエロスの関係について再び考えていた。またしても彼女がこの議題について考えているからといって、彼女がリンゴとエロスの関係に特に執心しているという証明にはならない。なにせ彼女は暇なのだ。仕事は自動運転でこなしているのだから、考える時間は山ほどあった。他に考えることがあれば喜んでその議題に移ったことだろうが、今のところ他に考えるべきことはなかったのでリンゴとエロスの関係について考察しているのだった。彼女は二人の有識者からエロスの考察を得ることが出来たが、彼女自身がぴんと来る答えは未だ見つかっていないのだった。
彼女は9階で受験生風の男子学生を降ろし、上の階で呼ばれていることを確認して、「上へ参りますので少々お待ち下さい」と、今にも乗りこもうとしていた中年女性をやんわりと断った。
「急いでるんだけど、先に下に行ってくれない?」
と、中年女性は声を荒げた。
「申し訳ございません。すぐに参りますので少々お待ちください」
と、彼女は申し訳なさそうに頭を下げ、素早く罪のない笑みを浮かべた。これも自動運転の一部だ。女性が納得した様子を見せたので彼女は、ドアを閉めるとエレベーターと一緒に上昇して行く。彼女のエレベーターを呼んでいるのは屋上だった。彼女は腕にはめた時計をちらりと見る。屋上には子供用のミニ遊園地と、ちょっとしたペット売り場があるだけだ。夕方を過ぎているので遊園地はもう閉まっている。こんな時間には屋上から呼ばれることは少ないのに。
エレベーターが止まった。扉が開く。彼女は扉が閉まらないよう手で押さえながら一歩外に出ると、最上級の笑顔で微笑みながら「下へ参ります」と言った。エレベーターのドアの前には若い男が一人壁にもたれて立っていた。男は彼女を上から下まで眺めたが、壁から動く気配を見せない。彼女は辺りを見回したが、男以外に客はいないようだった。
「下へ参ります、」
と、彼女はもう一度男に向かって微笑んだ。男は人懐っこい笑顔で彼女に微笑み返すと、「あとでいいよ」と言った。エレベーターのボタンを押した人間は既に他の場所に行ってしまったのか、男がボタンを押したのに急な用事、たとえば恋人がトイレに行ってしまったとか、のために今は降りる必要がなくなったのか。どちらにせよ、デパートではよくあることだった。彼女は男に笑顔で会釈すると、エレベーターの扉を閉める。男はだんだん細くなる扉の隙間ごしに彼女を眺めている。まとわりつくような濃い視線だ。彼女も男から目が離せなかった。扉が完全に閉まり、一人残された密室の箱の中で彼女は軽く目を閉じ、息を吐いた。エレベーターの扉はすっかり閉まったというのに、男の視線がこの密室に残ってあたしをじろじろと眺め回しているようだ、と彼女は思った。
3 / 4