第一夜
こんな夢を見た。
蝋燭によって淡く照らされた空間を前に胡座をかいていると、対峙している女が、「もう死にます」と言う。
女は能面のような顔をキッとこちらに向け、まだ整っていない黒髪が肩にかかっている。血の気が通っていないような頬は痙攣しているように、ツッツッと時折上下する。
死にますか、と尋ねると、はい死にます、とはっきり言う。そこまで断言されると自分も、あぁ死んでしまうのだ、と無色透明な感想を抱くのだ。手を休め、女の顔をしっかりと覗き、聞いてみた。
「斬りますか?」
「斬るでしょう」
「死にますか?」
「死ぬでしょう」
眼には潤いがあり、その深い黒は自分の姿をしっかりと写していた。
かつーんかつーん……かつーんかつーん……
斬り続け、死に続けるでしょう、女は繰り返しそう言う。しきりと、「斬る」と口にする女を自分は黙殺した。
「私が死んだら、朝日の見える丘に置いてください。あそこから見えるあの丘です」
膝頭の前に存在するその女は徐々に表情を作っていった。
「昨日は雨でした。明日も雨でしょう。明後日も、そのまた次の日もずっと雨でしょう。あなたは耐えられますか? 耐え抜くことが出来ますか?」
自分は僅かに首を引くだけに留めた。
女はそれを確認すると、満足したかのように目を閉じた。瞼、頬、唇、顔から血の気が徐々に通っていく。自分は慌てる様子でもなく、「あぁ、これが死んでいくということなのだな」と、思うだけだった。
空が白み始め、障子は段々と明るさを持ってきた。女が斬るとしきりに言っていた作業もそれに合わせて完了しつつあった。
女が口を開くことはなかった。
障子を開けると、丘に朝日の赤みが当たっている。
女はあの丘に思い入れでもあったのだろうか? 朝独特の澄んだ空気が顔、身体、内臓までも包み込むように当たる。
女は死んだのだろう。自分が殺したのだろう。「斬り」続けたからだろう。
哀しいかい? 寂しいかい?
自分が、そのどちらでもない安堵感を胸に作り始めたことに気づくのは、これからずっと先のことだろう。
丘にある一体の木像は朝日を何度見るのだろう。
第二夜
こんな夢を見た。
夢であるはずなのに痛みがある。
おかしいなと思ったのも無理はない。ここは夢の世界で現実ではない。夢の中では痛みは感じないというのが巷の評判ではないか。
しかし、痛みがある。
右腕を見てみると、青黒く痣が出来ている。打ち身らしい。
舌打ちをしようと思ったら、口の中で血の味がする。どうやら切れているらしい。
周りを見渡すと、野次馬らしき人だかりが自分を取り囲んでいる。次に自分を見回せば、どうやら武士らしいことに気づいた。腰に大小を携え、右手にその一振りが握られている。自分の足下にこれまた武士らしき一人、二人が倒れていた。
自分が斬ったらしいが、身に覚えはない。ざわめき始めた野次馬を掻き分けるようにして、その場から立ち去った。
暫くして振り返ってみたが、相変わらず人垣が出来ていた。自分はそこで、はたと止まり一体どういう顛末なのかを考えなければならなかった。しかし一向に埒があかないのは必然だった。
「おじさん、さっきの教えて」
と、自分の腰ほどの背丈の子供が言ってきた。所々に継ぎ接ぎのある服を着た子供をまじまじと見れば、女だということがわかった。
「娘子が剣術なんぞ覚えてどうする」
「仇をうつのよ」
素直な感想をその娘に伝え、諦めさせようとしたのだが、娘は一向に引かない。自分でさえ何があったのか覚えていないものを他人に教えられるはずもない。
「ならば明日、家に行こう。そこで教えるというのでどうだ」
娘は渋々そこまで譲歩し、自分は解放された。明日までに思い出さなくてはならない。
人垣に戻り、野次馬の一人にあらましを聞く。
飯屋にて揉めた後、逃げ出すように場を後にした自分を二人は追ってきた。そこを振り向きざまに斬ったらしい。「見事なものでしたよ」と、野次馬は嬉々として言った。そこまで聞いてもやはり思い出せやしない。近くにあった宿の一室で何度も繰り返す。
蝋燭の明かりと月明かりで、刀はよく光った。精神を集中させ幾たびも、シュッシュッシュッ……シュッシュッシュッ……と音をさせる。
繰り返される音。次第に疲労が出てくる右腕。
何度繰り返そうが素振りの音は悲哀のままだった。
人を斬ったのだろうか。じっと手を見る。肉を斬った感覚もなければ、当然骨を砕いた感触もない。しかし鞘から刀を抜き出し見れば、うっすらと油が浮かんでいる。斬ったようだ。
額にじわっと浮かんだ汗を懐の手拭いで拭う。
一度寝て起きれば、この夢は覚めるだろうか。覚めないのだろうか。打ち身が再び疼き出す。
今宵の月は赤味を増していた。所々擦りきれた畳の上で大の字となった。娘の敵討ちは自分が行こう。されば結果の如何にかかわらずにあの子も満足するのではないか。明日、自分は死ぬかもしれない…………………‥‥…‥‥‥‥…‥‥・・・・・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
――まだ、一人で尻拭いもできんのかね
はっと気がつき小刀を抜いたのは、陽も南中の頃であった。
第三夜
こんな夢を見た。
目の前に、和服を着た一人の女性が佇んでいる。黒髪はボサボサで着物も黒ずんでおり、全体的にどこか見窄らしい感じを受けた。女性は礼儀正しく背筋を伸ばして立っていた。
「遅かったわね」
と、口にするとくるりと背を向け夜道を歩き出した。
自分はその背を一点に見つめながら追いかけた。
遠い空に虫の鳴き声が木霊する。舗装されていない道で、時折風で砂埃が舞い上がる。女性は一定の速さで歩き続けた。自分も二、三歩遅れて続いた。
付き合いのあった女性だろうか。恨みを買ったのだろうか。そういうことを考えていると、「元気そうね」と女が言った。どこか棘のある口調だった。自分は、「あぁ」とか、「うん」とか曖昧な返事をするだけで、女も返答に興味があるようではなかった。
その顔をどこかで見た記憶はあった。それがいつのことだかは思い出せない。
「あの木、憶えてる?」
立ち止まった女の前方に大きな木が一本植えられていた。
女は再び歩み始めた。自分もそれに続き、幹に近づいてみると、名前が彫ってあった。彫った痕は長い年月によってわかりにくくなっていたが、その名前は自分のだった。自分の名前に手を重ねた。
思い出せそうだが、どこかでそれを止めようとしている自分がいた。必死に足掻くその姿をもう一人の自分が哀れみを顔に浮かべながら見ている。「あぁ、あれは小さな自分です……」「とても小さな自分なのです……」どこかで、自分が呟いていた。
「あの木はとても思い出深いわ。ほら、触ってみて」
女は幹に置かれていた手を取ると、胸にあてた。恐ろしいほど冷たい皮膚は硬かった。
掌は凹みを感じ取っていた。拳ほどの大きさの凹み。ひびも入っているようだ。
「一体……」
次の言葉を言う前に、はっと自分は思い出した。
この凹みは自分が作ったことを。自分の拳が原因だということを。
「今日は何日だい?」
「三月十日よ」
あぁ、やはりそうだ。今が何年であるかわからないが、この日は忘れられない日のはずだった。
妹が気に入っていた人形を埋めた日だ。
向けられなくなった母親の愛情を一身に受けていた妹へのささやかな復讐。根本に埋めたのだった。
謝罪すべきだろうか、幼い日の過ちを。顔を上げ女の顔を見た。その表情は最早原型を留めていなかった。
「あんたに埋められた日ね」
第四夜
小学校の前に露店がある。
その噂を聞いたのは、昼食も終わる頃だった。
どうやらここ一週間ほど店を構えているらしい。
その話を聞いて、自分が子供の頃に実験キットなどを売っていた人がいたのを思い出した。時代は変わっても人は変わらないということだろうか。
授業が終わると、子供たちを送り出す名目でその校門に足を向けた。
確かに露店はあった。学校に面した通りの反対側にある公園から子供たちの歓声が聞こえる。自分もサンダルをペタペタやりながら、その輪へ加わった。
売っている物もあの当時と大差なかった。カラーひよこすら健在だった。
売り子は自分の存在に気づいたようで、少々気まずそうだった。が、自分は注意することを忘れ、折りたたみの机に載せられている品物に心を奪われていた。
机の端に白い箱が置かれているのが目にとまる。立方体のその箱は、大きさは縦横高さともにフロッピーディスクと同じくらいだろうか。それほど大きくない。
「それは?」
と、指を指し尋ねた。
売り子の男は何も答えずにただ黙っているだけだった。聞こえなかったのかと思い、もう一度尋ねたかったが、何故か出来なかった。恥……ではないだろう。男には質問をそれ以上させない何らかの力があったのだ。
子供たちは時間が経つにつれ徐々に数を減らしていき、子供たちの挨拶が頭の中を通り過ぎていく。とうとう最後には、自分と売り子の二人だけとなった。その間も売り子は決して物を勧めたりはしなかったし、自分も最初の質問以外、男に話しかけなかった。
箱がガタガタと揺れだしたのは、公園に設置された大時計が午後五時過ぎを指した頃だった。
その頃になれば、売り子の顔には影が出来、白い箱の影も長く伸びていた。
揺らめく影、伸びゆく影……。
はっと思い、売り子の方を見ると先ほどまで座っていたはずの売り子はもういなくなっていた。慌てて周囲を見回したが、どこにも見当たらない。
もしかすれば、箱から売り子がいた場所へと視線を動かしたその一瞬のうちにこの箱の中に隠れたのかもしれない。
起こりえるはずのない空想が頭の中で過ぎる。傾向としては良くない部類に分けられるだろう。しかし、その箱がガタガタと動くことが無くなったのも事実だ。蓋を開けなくてはならない。開けて事実を、現実を、正解を直視しなければならなかった。蓋を開けた箱の中身がどうなっていようと、何が飛び出ようが、開けなければ先に進めそうになかった。
案外、箱を開いたパンドラも同じような気持ちだったのかもしれない。
周囲には誰もいない。止める者は誰もいない。パンドラが開けた箱からは厄災が飛び出したが、この白い箱からは何が飛び出していくのだろうか。もしかすれば何も飛び出さないかもしれない。自分の悩みはただの徒労に終わる可能性だってある。
「開けなさい。早く開けなさい」
「欲望を表に出しなさい。隠さず出しなさい」
カラスは売り子の顔をして言う。あの売り子はもしかしたら女だったのかもしれない。そしてあの売り子こそ、パンドラだったのかもしれないな、と自分は思う。思って笑う。馬鹿らしい。
数分間蓋に置かれていた掌にはうっすらと汗が出ていた。
影はもう消えていた。揺れてなんていなかった。
第五夜
こんな夢を見た。
どうやら、誇りと自負心のある時代らしい。男たちは自信に溢れ、女たちも生き生きとしているそんな時代らしかった。
往来は雪化粧であった。遠方からは雪を踏む音が響く、まだ夜明け前だった。
ぎゅっぎゅっ、と音の鳴った後には無数の足跡が残った。
音の主たちは、頭から爪先まで黒ずくめで各々様々に物騒な獲物を持っていた。自分にはその一行の目的地など窺い知れない。ただ跫音だけが時に不気味に、時に陽気に響くのだった。
反響する音たちの中で、自分は一人取り残されているような気分になった。大勢に取り残されるのはいつでも不安だ。寡黙について行くしかない。
真っ直ぐな道の両隣には高層建物がひしめいていた。雪明かりや月明かりに反射する建物群は道標のように一本の道を浮き上がらせていた。それを綺麗な景色とは感じなかった。どことなく、他人行儀な感じさえ受けた。
気づくと自分は一人だった。
あれだけ大勢がいたはずなのに一人になっていた。立ち止まり振り返ると、道標も何処かへ消えていた。一体……どこへ?
「申し、申し」
声をかけられた方を見ると、男が一人深々と頭を下げていた。その男は自分の父親に似ていた。母親を追いつめた父は他人面であった。自分はというと、怒りに拳を震わせていた。ただ単に、父親がそこにいたからではない。父親が黒ずくめの男によって捕まっているからだ。父親は息子に命乞いを迫ってきたのだ。嘗て、捨てた子に助けを求め、その顔は必死且つ惨めなものだった。
「生かすか、殺すか」
父親の後ろにいる黒ずくめの男の一人が言う。黒ずくめの男は既に哀れなその男が、自分の父親であることを――少なくとも身内だということを――知っているようだった。頭巾から僅かに見える眼は、落ち着いていた。事務処理をするような目つきであった。
――生かす
と答えれば、自分は誇りなき男となり、
――殺す
と言えば、自分は不忠者となる。
黒ずくめは、自分が答えに窮するというのを予見していたらしい。
「自分の一存では決められない。母親に相談したい。一日の猶予をくれ」
との申し入れに特に反対しなかったのも、予想していたからこそだろう。ただ、自分は母親がどこにいるかなど到底知るはずもなかった。父親の顔を見たが、相も変わらず俯いていた。
誇りの無くなった父親は捕縛されて当然なのだろう。そういう時代なのだ。自分は実の父を捕まえるために、この雪道をひた走ってきたことを悟った。誰に言われることもなく、悟った。
自分を取り囲む黒ずくめたちは静かだった。その静けさが不気味でもあった。何かの物音を欲していたが、叶わぬことだと諦めた。
この時、母は高層建物の一部屋で硝子窓から月を眺めていた。胸騒ぎがしたのだろう。出かける準備をし、モニターから車を呼び出した。車は間もなく到着した。この時間の空中道路を走る車などないらしい。
目的地を告げなくとも車は勝手に走り出した。意思など備えていないはずだったが、運命に身を任せたかのように、母はそれに任せた。空中に浮かび上がるレールのような光に沿って車は音もなく走った。走っていく中、何やら物体があるのが目に見えた。車の照明に反射したその影はまぎれもなく、人の形をしていた。それにも構わずに車は進んだ。母は必死に止めようとしていたが、操作は出来なくなっていた。
黒ずくめの男だった。
すると、急にブレーキが効き、車は急停車を開始した。「あっ」と言った時にはもうそこに母親はいなかった。断末魔さえなく、粉々になる音だけが響いた。
自分にもその音は聞こえた。月明かりに視界は遮られたが、何が起こったのかわかった気がした。
父親は依然として、俯いたままだった。
何時からか、握りしめた手からは鮮血が滴り落ちていた。
その染みが消えることはあるのだろうか。![[fin]](img/main_lm.png)
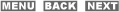
 |
 朝倉海人 朝倉海人- シュールレアリズムの断片を探す旅に来ております。
長編小説を現在書いてます。
- URL:漸
|
|