|
おかしいなと薄々感じ始めたのは四十を過ぎた頃だった。
世間でよく言われる、「四十の声」を聞き、体力的思考力的な衰えを覚悟していた。しかしその衰えは一向に見える気配がないのだ。日頃から特別に身体を動かしたりしているわけでもない。周囲の友人たちが口にする健康に関する事柄も私には全く当てはまらなかった。友人たちは一様に羨ましがっていた。
その時は目に見えないところで衰えていっているのだろうと、あまり深く考えないことにした。
「健康診断のお知らせ」という封書が届いたのは、それから一年ほど経過した頃のことだった。白い封筒の表には、私の名前と住所が宛名シールで貼られており、その下に印刷された青の字で、「大日本健康管理センター事務局」と書かれていた。
私はその聞き覚えのない送り主の名前を自分の記憶と何度も照合したが、やはり思い出せなかった。
書斎に戻った私は椅子に座ると、開封した。中には紙が二枚と診察証のような緑のカードが入っていた。
拝啓 鯨中様 K-10222993332
季節の変わり目、いかがお過ごしでしょうか。
今回は鯨中様の定期健康診断の時期がまいりましたので、お手紙を差し上げました。我々、大日本健康管理センターは国民の福祉向上と健康管理等を目的に内閣府に設立された機関です。
聞き覚えのない名称でしょうが、我々は国民の健康統計を目的に毎年、二十歳以上の成人の男女五千人を対象に無償健康診断を行っております。
本年度におきましては、鯨中様にご協力をお願いすることになりましたので、何卒よろしくお願い致します。
敬具
大日本健康管理センター事務局
内容はそのような感じであった。二枚目には健康診断を行う場所と日時が記載されていた。「ご不明の点があれば、下記にご連絡ください」と添えて電話番号と住所が記載されていた。
私はその手紙について懐疑的であった。第一に、「大日本健康管理センター」などという機関――しかもそれは内閣府直轄というではないか――を聞いたことがない。第二に、その団体が作ったとされる統計を見たことがない。厚生労働省の白書であれば見たことがあるが。以上の点から私はその内容を盲目的に信じることはせず、友人に確認をとってみることにした。
すると案の定、私の友人は誰一人「大日本健康管理センター」という機関を知らなかったのだ。私はほくそ笑んだ。私をはめようとする何者かの鼻をあかした気がしたからだ。そして念のために、電話で確認したところやはり、「そのような機関はない」という答えが返ってきた。
私はその答えに満足し、一人書斎で送られてきた手紙を眺めていた。
大日本健康管理センターとは何とも仰々しい名前を騙ったものだ。このまま無視をするのもいいだろうが、私はそこでひとつこいつらを逆にはめてやろうと思い至った。――正義感などというものではなく、騙そうとしている奴を逆にはめてやるのは、気分が良い。特にこうして善良な市民を騙そうとしている輩に、善良な市民の悪意を見せつける必要がある。
私は自分のその思いつきに満足し、一人静かに笑った。
そうとなれば、それなりの準備をしてそこに向かわなければならない。翌日の仕事帰りに私は駅前にある大型電器店に足を運び、レコーダーを吟味し、気に入ったものを購入していた。一部始終を録音してやろうということだ。
健康診断を行うとされた前日の夜は、まるで遠足に行く前の晩のように興奮し、なかなか眠りにつけなかった。私の他にも誰か来るのだろうか? 書面には五千人と書いてあったが、恐らくそれは嘘であろう。数の多さで一人を納得させようとするは昔からの常套手段だ。私は自分に言い聞かせ――もしかしたら、多少恐怖感のようなものがそこにはあったのかもしれない――まだ見ぬ相手に対し、対決姿勢を強めていった。もし私の他にも騙され足を運んだ人がいれば、そちらの方が好都合のようにも感じた。何しろ複数の証言があった方が警察なども動きやすいだろう。
「ふふ」
私は布団の中で笑っていた。
気がつくと、カーテンの隙間から光が射し込んでいた。時計を見ると、八時少し前を針が指していた。伸びをひとつして、布団から抜け出た。朝食を取り支度をし、ちょうど良い頃合いになると出かけた。
休日の電車はそれなりに混んでいた。この中にもしかしたら私同様、大日本健康管理センターに向かう人がいるかもしれないと思うと人間観察をせずにはいられなかったが、健康診断に向かう人間を見分けるのは無理だった。
目的の駅には電車をひとつ乗り換えて、一時間ほどで着いた。駅から地図を見ながら歩くと、十分ほどでその建物は見つかった。予想していたよりも立派な建物だった。どこか雑居ビルの一室を思い描いていた私は目の前の「山邑会館」という近代的なビル――実際、二年前に建築されたものらしかった――に戸惑いを隠せなかった。
いや、相手は見かけで私を騙そうとしているのだ、と私はその驚きを極力小さなものにしようとした。心の中で死滅しようとしていた「もしかしたら本当に公的機関なのかもしれない」という思いが頭を持ち上げていたが、もし本物だとしても私にとって不都合なことはないのだと思い直した。そう、本物であればただ健康診断をするだけでなのだ。
入り口を抜けると私は再び狼狽した。
そこには受付があり、「健康診断用受付」と書かれた案内板の隣には女性が二人いたからだ。私はここでいよいよ、「これは本物ではないか」という前日までには予定していなかった結論に急遽変更せざるを得なくなりつつあった。
「こんにちは」
「こんにちは、健康診断に来られた方ですか?」
女性二人の問いかけは私の狼狽を見透かしたかのように、考えさせる余地を与えなかった。私は言葉なくただ頷き、「それでしたらこちらにご記入お願いします」という言葉にただ従うだけだった。
所定の用紙に氏名を書き終えると、それで受付は終了したようで、二階のホールに行くよう言われた。私の頭の中はこの時、混乱の絶頂にあった。この戸惑いが他の人にわかるだろうか。既に相手を逆にはめてやろうという私の前日までの考えは、あれほど面白いものに感じたはずなのに、最早どこにもそこに面白さを感じることはできなかった。
足取りも重く、二階へ向かう階段を一歩一歩登っていく。胸ポケットにしまい込んであった録音レコーダーも今では間抜けに思えた。この階段がいつまでも終わることなければいい……と思ったが、そんなわけもなく私は二階に辿り着いた。
階段を登って左手に会場となっているらしいホールがあり、「健康診断会場」と印刷された紙が入り口に貼られていた。中には私の他にも人がいるようだ。
その小学校の体育館ほどの広さのホールは、いくつものブースで仕切られており、薬品の匂いが鼻についた。私は持参した封筒の書面を係らしき人に見せた。
「Kの方はあの二十五番ブースになりますね」
とだけその係の男は言うと足早に私の目の前から立ち去っていった。
二十五番ブースは入り口から一番左手奥にあった。
衝立で仕切られたその空間には医者と思われる男と看護師らしき女性が一人いるだけで、他には折りたたみの椅子が一脚、診察用用具を置く折りたたみの長机があるだけだった。
看護師に進められるまま私はその椅子に腰を下ろした。あの緑のカードを看護師に見せると、看護師は私の名前を医者に伝え、医師はカルテを探り始めた。
その作業が終わると、医者は咳をひとつ、「ゴホン」とし私に上着をめくるように指示した。無論、私は素直にそれに応じた。
診察はそのような感じで何事もなく終わった。診察が終わると、医者は奇妙なことを言い始めた。
「……どこも変わりないようですね。非常に良い状態です。保証期間は残り七十八年ですが、この分だとメンテナンスは特に必要ないでしょう。ただ、保証期間の百年過ぎますと、無償交換などはできませんから気をつけてください」
保証期間? メンテナンス? 無償交換? なんのことだろうか、私は全く理解できなかった。
「え?」
と、私がそれしか言えなかったのもわかるだろう。すると今度は医者が驚いた顔を見せ、看護師と顔を見合わせていた。さも私が奇人かのようなその仕草に腹を立てた。
「いや、何を仰ってるのか私には理解できませんが……」
私のその言葉に医者は再び驚いたようだった。慌ててカルテを見直し始めた。
「なんだ。保護者同意か。困るんですよねぇ、ちゃんと説明しない人が多くて」
医者は心底面倒そうに話した。
「あなたは十九歳の時……ですから今から二十二年前ですか。その時にですね、人工体移植手術を受けていらっしゃるのですよ」
「人工体……?」
私にその単語の馴染みはなかった。
人工体……。私は何度も呟いてみたが、思い起こされるのは二十年以上前に目にした、「人工体技術確立へ」という記事の見出しだった。確かそう、人工体というのはクローン技術によって、内臓や皮膚などの生成のために動物――確かあの頃は豚を使っていたはずだ――を使うことは非人道的であるという風潮が高まった結果、それならばと完全に人工的な内臓、骨、血管などを作ろうとしたのが成功したという記事だった。
それはわかる。いや憶えている。
だが、それが私に使われているなど。こいつらは私の心を掻き乱し、法外な治療代をふっかける気なのではないか。再び私は気を引き締めた。
「鯨中さん。あなたは十九歳の時に交通事故に遭ったのを憶えていますかね。ここにその時の記録もあるんですが。あなたは家の近くの十字路で右手から来た大型トラックによってはねられ、意識不明の重体になった。
その時にですね、あなたのご両親はこう仰った。『どんな方法でもいいから、あの子を助けてください』と。しかし、あなたは残念なことに最早助かる見込みはなかった。そこで、人工体を使う手術を当時の主治医が提案した。ほら、ここにあなたの父親のサインがある。手術承諾書です。あなたは未成年でしたからね。未成年後見人のサインでいいのです。当時、この技術は実験段階から実際に医療現場で使用する段階に移っていました。
が、あなたのように全身――脳以外全てですが――を人工体に変えるというのは初の試みでした。あなたの頭蓋骨はセラミック系の素材……水酸化アパタイト……骨はカーボン……全置換用人工心臓が体内に血液を送り続けている……。それが今のあなたの身体なのです。本当は成人するとともに伝えなくてはならないんですがね」
私はその医者の言葉を極力聞かないように上の空を決め込んだのだが、否応にも聞こえてくる。私の身体はもう「私」のものではないのだというその突然の告白は私に非常なダメージを与えた。
私はそのままその会館をあとにした。呆然とただ呆然と歩いていた。
医者が言うには、特に切り傷に注意することを言われた。自然治癒によって傷口がふさがれることはないとのことだったが、今の私にはどうでも良かった。
そういえばこの時以降、母親が私に何度も注意を促していたのを思い出した。それはつまりそういうことだったというわけだ。
その後、私は立ち直るまで相当の時間を要した。めっきり外に出かけることも少なくなり、会社も辞めた。それでも生活できたのは、親の口座に毎月入ってきていた国からの補助金が使われずに貯められていたからだろう。私はそのことすら知らなかったのだ。
私は外界との接触を断ち切った。それは行動だけでなく、精神的なことも含めてだ。私の身体はもはや「私」ではない。私は一体誰なのか。私にはわからない……。
あれから七十二年経った。私の肉体はそれでも衰えなかった。いやもしかしたら金属劣化のように劣化しているのかもしれない。兆候は見えずとも、ある日突然機能停止をする可能性はあった。僅かな亀裂が何かのきっかけで崩壊するのは建築物によく見られる現象ではないか。私は恐怖した。死刑囚にも近い精神状態を余儀なくされたのだ。
ある日、私はテーブルの角に足の小指をぶつけた。そういうことはそれまでも何度かあった。私はその度に恐る恐る小指を見るのだが、幸い指は何の変化もなかった。
その日もあまりの痛さに声を失い、小指に私は目を向けた。そこには見慣れぬ人工骨が剥き出しとなり顔を覗かせていた。まるで自分の存在を忘れさせないように……。その時の私の狼狽ぶりといったら、それはなかった。大慌てで電話をかけた。無論、「大日本健康管理センター」にだ。
電話口に出た担当者の声はどこか冷たかった。
「あぁ、もう保証期間が過ぎてますねぇ。残念ですが、無償では交換できませんよ。それでもよろしければ、皮膚を交換しますが……あぁ、このタイプですか。これはもう旧タイプなので換えの在庫がないですねぇ」
という男の対応に私が声を荒げたのは言うまでもあるまい。
「ふざけるな! 私は人間だ。そこいらの機械とは違うんだ!」
「ですが、部品保管期間というのが決められていましてね。もちろん法律によってですよ。そのタイプを制作してから百年なんですよ。それ以上経過した場合は、在庫の保有は任意でしてね。申し訳ないですね」
私は力任せに受話器を叩きつけた。その反動か、右肩の関節が外れたようだった。
人工体は劣化しないのではない。劣化スピードが人間の肉体よりも遅いと言うだけなのだ。金属劣化のように私のあらゆる器官は壊れていっているということだ。今、この左手で目をこすれば、目玉が取れるのかもしれない。いや、左手甲の皮膚がべっとりと取れるかもしれない。
私は恐怖に襲われて、布団に潜り込んだ。崩れゆくかもしれない自分の肢体を視界から隠し去りたかったということもあった。私は頭の中に浮かんでくる自分の顕わになった人工骨の映像を幾度も必死に忘れようと努めた。あの不気味な骨の色が私の全身にあるかと思うと自分のアイデンティティを崩壊させられた気分だった。
私の脳は騙されているのすら気づいていないようだ。確かに脳は私のものだったが、果たして心は私のものなのだろうか……。心は肉体に宿るのか、脳に宿るのか……。肉体に宿るとすれば、もう心すら私のものではない。
睡魔に襲われた私が気がついたのは、異様な熱さを感じたからだ。目を覚まし、周囲を見ると火が燃えさかっていた。煙草の火が何かにうつったらしかった。私は大急ぎで寝床から出て、消化器で火を消し止めようとした。それも虚しい努力なことにすぐに気づき、家の外に避難した。家の周りには人垣ができていた。遠くからサイレンが聞こえてくる。どうやら誰かが通報してくれたようだ。
私は一安心し、その場に尻餅をついた。しばらく経つと、私の周りから徐々に人が離れていくのを感じた。私は不審に思い、振り返ると、辺りから悲鳴が起こった。
そう、私の皮膚は熱によって溶けていたのだ。顔、腕、足、背中、腹……所々でもう皮膚は原形を保っていなかった。火に照らされる爛れた顔の私はそれはもう人間ではないと思われてしかたない姿だったようだ。
私はそこで一人大声で笑った。これを笑わずにどうしろと言うのだ。![[fin]](img/main_lm.png)
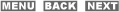
 |
 朝倉海人 朝倉海人- シュールレアリズムの断片を探す旅に来ております。長編小説を現在書いてます。
- URL:漸
|
|

