 昨日からマサトは自室に籠もりっきりだ。昼夜を問わずカーテンを閉め切った真っ暗な部屋で、二十四時間つけっぱなしのテレビと、パソコンの液晶モニターが水槽の奥のような光を放っている。
普段ならろくに見もしないテレビニュースだが、今日ばかりは気が気ではない。インターネットにつないでもオンラインゲームやアダルトサイトに寄り道せず、新聞社のホームページや掲示板のニューストピックスを虱潰しに当たっている。
どこの報道を見ても扱いはきわめて素っ気ないものだった。よくある話、軽微な犯罪ということらしい。だが彼にとっては深刻だ。「伯爵」が逮捕されたのだ。
杉並区在住、無職、黒木紳一容疑者、三十歳。無限連鎖講防止法違反の容疑で逮捕――。
それがあの「伯爵」だと気付いたのは昨日、何の気なしに目にしたニュース番組に映し出されたメールの文面に見覚えがあったからだ。
ちょっとしたマネーゲーム。入会金はわずか五千円。誰も損しないし、誰も傷つけない。それでいてみんな小遣いが稼げてハッピーになる。仲間を増やせば増やすだけ実入りも増える。参加するなら早いほうがお得――。
それがいわゆるネズミ講と呼ばれるものだとは知らなかったし、そもそもネズミ講というものが違法だということも知らなかった。オンラインゲームで知り合った「伯爵」に話を持ちかけられたときも、それが犯罪だとは思いも寄らなかったし、いまもって、なぜそれが罪に問われるのか理解できない。参加者みんなが納得しているというのに、いったい誰が害を被ったというのだろう?
試しにネットでネズミ講について調べてみるが、法律用語や数式などが引用されていて彼にはさっぱり解らない。ただひとつ理解できたことといえば、騙す意識がなかったとしても、他人を勧誘しただけで罪に問われ、刑に服す羽目に陥るということだ。
(まずいよ)
彼も「伯爵」の誘いに乗って、マネーゲームに参加した一人だった。お年玉の残りで入会金を払い、それを取り返すためにいろんなところで話を持ちかけたのだ。たいていは相手にされなかったが、それでも何人かは興味を示し、勧誘に成功した。参加者を集めるたびに、取り決めどおりの報酬が振り込まれ、それに気を良くして彼は精力的に参加者を募ったものだ。
つまり彼もまた知らぬ間に「あちら側」に回っていたのである。
(やばいよ)
こんなとき、相談できる相手が彼にはいなかった。両親に話せば一悶着起きるし、こっそり法律相談事務所に行くには金もなければ度胸もない。
物知りで、世慣れていて、経験豊かな相談相手。そんな便利な人間が――。
――いた。
思い至り、慌ててオンラインゲームに接続する。ログインすると何はともあれ冒険者の集う酒場に向かい、目当ての人物を捜し回る。
魔術師ヴァン、通称「教授」。今まで何度かパーティを組んで冒険した仲だ。なぜそんなあだ名を付けられているかというと、魔術師ヴァンを操作している人物は、とある法学部の教授だか助教授だという噂があるからだ。法学部の教授なら法律にも詳しいはずだし、彼になにがしかのアドバイスを与えてくれるかもしれない。
それを期待して、彼は冒険者の集う酒場「黒牛亭」をノックする。
「おつかれーっす」
常連客の気安さでマサトは声を掛ける。何しろ暇は腐るほどある。他の連中が仕事や学校に行っている間も冒険と戦闘を繰り返しているのだ。当然、彼のキャラクター、戦士のマーカスはかなり高いレベルまで成長しており、冒険者たちからも一目置かれている。
パーティに高いレベルの仲間がいるだけで、戦闘はぐっと楽になる。そんなわけでいつもなら、戦士のマーカスは引っ張りだこ。酒場に足を踏み入れただけで、助太刀を乞う冒険者から声を掛けられる。
だが今日はちょっと様子が違う。
マーカスが話しかけても、冒険者たちはなぜかよそよそしい。昵懇の仲である狩人のレヴなどは、
「無事だったんですか、マーカスさん?」
「無事って何が?」
「聞いてないんですか? 伯爵、逮捕されたらしいですよ」
内心血の気の引く思いだが、マサトは素知らぬ振りでキーを打つ。
「逮捕って何やったの、あの人?」
「ネズミ講ですよ」
ああ、そうなのだ。伯爵はこちらの世界でも、ずいぶん手広く勧誘していたのである。だからマサトが気付いたように他の冒険者も、あの逮捕された男が「伯爵」だと察したのはおかしなことじゃない。
「――で、ほら。マーカスさんもひとくち噛んでたじゃないですか。だから心配してたんですよ、俺たち」
ああ、そうだった。マサトもまた、こちらの世界でいろいろと話を持ちかけていたのだった。ときには助太刀してやる代わりにどうだと誘ったり、レベルの低い冒険者には入手困難なアイテムを取ってくる代償としてマネーゲームに誘ったりしたこともある。
「俺は関係ないよ。伯爵に騙されたんだ、俺も」
我ながら苦しい言い訳だ。確かに伯爵は利己的な意図で彼をネズミ講に誘った。その時点では彼も被害者であるといえるかもしれない。しかしネズミ講に参加したあとの彼は、やはり利己的な意図で他の人間に声を掛けてきたのだ。初めは元手を回収するために。そのあとはちょっと小遣いを稼ぐために――。
「ところでさ」
震える指でキーを叩く。
「教授、今日見てない?」
「教授ですか? さあ、俺は会ってないですね。元々あの人、あんまり顔見せないし」
教授こと魔術師のヴァンは、このオンラインゲーム発足当時からいる最古参の冒険者だ。しかし多忙なのかそれほど冒険に来ない。
「教授に何か用ですか?」
「いや、用ってほどじゃないけど。何やってるのかなと思って」
焦りと失望がマサトを苛立たせる。教授がいないのならここにいても仕方がない。
と、そのとき、新たな冒険者が酒場の扉を押し開ける。
「――ご無沙汰」
教授だ。
マサトは胸中、快哉を挙げた。慌てて駆け寄り話しかける。
「お久し振り、教授。何やってたの?」
教授はやめてくださいよ、と魔術師ヴァン。「教授」はあくまでもあだ名である。何となくそれが通り名になっているが、別段この世界で教授と名乗っているわけではない。
「これから何か予定ある?」
「いや、ぶらっと顔出しただけですけど。どうしたんですかマーカスさん?」
「じゃあさ、ちょっとそこらまで出掛けてみない?」
ずいぶん強引なお誘いですね、と教授。
「まるで中学生のデートみたいですよ(笑)」
だがこっちとしてはそんな軽口に付き合っていられる心境ではない。果たして自分も法的責任が問われるのか。問われた場合、どれほどの罰則が課せられるのか。それを免れる可能性はどれほどか。訊きたいことは山ほどあった。
できれば二人だけで、とマーカスが言うと魔術師ヴァンは、
「じゃあヴァンパイアの洞窟なんてどうですか?」
確かにヴァンパイアの洞窟は手頃なスポットだ。出現する化け物の大半はコウモリばかりで、マーカスほどレベルの上がった冒険者なら恐れるに足らない雑魚ばかり。
唯一、警戒すべきは最深部に巣くうヴァンパイア・ロード。特にその吸血攻撃はたちが悪い。衰弱した冒険者が吸血攻撃を受けると、死んでしまうどころか、今度は操作不能の吸血鬼となって仲間を襲うようになるのである。つまり先ほどまでの仲間が、突然モンスターの側に回って襲いかかるのだ。かつて低レベルの冒険者たちが二十人という大パーティで踏破を試み、お互いに血を吸い合って全滅したこともあった。
要するに、ヴァンパイアの洞窟を攻略する最も無難なやり方は少数精鋭、それに尽きる。頼りない仲間とつるめばそれだけ危険も増えるのだ。
その点、教授こと魔術師ヴァンはキャリアを積んだ冒険者だ。コウモリなどは火炎魔法で一掃していく。ちょっと手強い人狼や食屍鬼も、歴戦の猛者マーカスが振るう大剣にかかればひと薙ぎだ。
マーカスとヴァン。たった二人の冒険者の通った後は死屍累々の惨状だ。ほとんど傷を負うこともなく、ベテラン冒険者たちは最深部に歩みを進める。
「――教授。伯爵が逮捕されたっていう話、聞きましたか?」
「ええ」
魔術師ヴァンは指を一振り。毒霧にまかれたコウモリが地に落ちる。
「俺も、ちょっとだけ仲間になってたんです」
「らしいですね」
物陰から飛び出してきた黒犬。マーカスの一撃で弾け飛ぶ。
「俺もやばいですかね」
どうでしょうかね、と教授。
「ああいうのは被害者と加害者の区別が難しいですからね。たいてい捕まるのは首謀者とその周辺だけですよ」
それを聞いてほっとした。少なくともマサトは首謀者ではない。あくまでも彼は伯爵の「子」である。素知らぬ顔をして被害者面していれば乗り切れるのではないかという気もしてきた。
と、BGMが変化する。強敵の予感にマサトは気を引き締める。
岩盤むき出しの背景にそぐわぬ夜会服。漆黒の髪をオールバックになでつけた伊達男。紅く小暗く輝く瞳。やけに艶めかしい薄い唇を開けば、顎の左右にナイフのような犬歯。
洞窟の主、ヴァンパイア・ロードのお出ましだ。
何の申し合わせもないというのに、いきなり教授は二人に対魔法効果のバリアを張る。ヴァンパイアの怖さは単なる攻撃力、回復力にあるのではない。奴らは人の心を盗む。魔力を帯びた視線で誘惑し、混乱させ、霧をかけ、同士討ちを誘う。そして取り乱した冒険者を毒牙にかけ、次々と闇の眷属に引き込んでいく。
しかし教授の張ったバリアのおかげでヴァンパイア・ロードの魔力は激減した。少なくとも瞳に魅入られて幻に囚われる危険はなくなった。
手慣れているな、とマサトは感心する。対魔法バリアは諸刃の剣だ。敵の魔法攻撃を跳ね返すが、しかし反面、味方の回復魔法の効果をも削減してしまうのだ。
だがマーカスは戦士、魔法を使えない。一方の教授は回復魔法を使う僧侶ではなく、攻撃魔法専門の魔術師だ。戦士と魔術師の二人連れとなれば怪我の治療は魔法でなく、大量に持参した薬草に頼ることになる。
つまり、自身に対魔法バリアを張ったところでデメリットは何もないというわけだ。
「こいつと戦うのは何度目ですか?」
二十二回、と教授。
なるほど、吸血鬼狩りはお手の物というわけだ。しかしそれはそれで腑に落ちない。確かにヴァンパイア・ロードは難敵で、倒せばそれなりの経験値が手に入る。しかし同程度の経験値を手に入れるなら、他にもめぼしいモンスターはたくさんいる。なぜそこまで吸血鬼狩りに血道を上げるのだろうか。
来ますよ、と教授が警告する。
「よろしく頼みます、マーカスさん」
幻術が通じないと見るや、ヴァンパイア・ロードは猪突猛進、腕力にものをいわせてきた。侵入者に躍りかかり、爪で、牙で攻撃を仕掛けてくる。それらを引き受けるのは分厚い鎧を身にまとい、強靱な体力を誇る戦士マーカスの役割だ。
頑丈な盾で攻撃を遮りつつ、マーカスは教授をうしろに避難させる。目的は呪文を唱える時間稼ぎだ。ヴァンパイアのように自動回復するモンスターを相手にしては、剣でちまちま削ってもきりがない。ここは魔法で一気に大ダメージを与え、そのままの勢いで押し切るのが得策だろう。
しかし百戦錬磨の強者とはいえ、一対一でヴァンパイア・ロードとやり合うのは分が悪い。重装備のおかげで致命的なダメージは負っていないが、徐々に体力を奪われていく。一方こちらも反撃するものの、ダメージを食らうそばから回復していくヴァンパイア。
――まだか。
隙を見て薬草で体力を回復するが、しかし次の攻撃でさらなるダメージを受ける。いつしか体力は半減し、じりじりと後退するマーカス。ずいぶんと手間取っているじゃないか、教授?
――まだか?
やばい。このままだと吸血攻撃の餌食になる。体力が五分の一を切ったあとで吸血攻撃を食らうと、彼もまた吸血鬼になってしまうのだ。
――まだかっ!
とうとう体力が五分の一まで減少した。一年以上、毎日のように冒険し、ここまで鍛え上げた戦士マーカスが制御不能の吸血鬼となり、彼の手から離れてしまうのか。
――嘘だろ? イヤだ。冗談じゃないぞ!
「教授っ!」
モニターの前でマサトは絶叫していた。タイピングする余裕などない。
「――お待たせ」
教授だ。呪文を唱える準備が完了したのだ。
慌ててマーカスは脇に飛びすさる。
がら空きになった。遮るものは何もない。
向かい合う、返り血を浴びたヴァンパイアと、枯れ木のような老魔術師。
目の前に立つ新たな獲物めがけ、ヴァンパイア・ロードは豹のように身体をたわめると、驚異的な跳躍力で間合いを詰めた。
瞬間、洞窟を目も眩むような光が包む。何十個もの火の玉が乱れ飛び、黒い影を四方八方から焼き焦がす。
何も見えない。何も聞こえない。ただ炎と爆音のみが洞窟内部を塗りつぶす。
モニターの前で呆然とするマサト。なるほど手間取るわけだ。Fire ball×48。狂気に満ちた集中砲火。これならさしものヴァンパイア・ロードといえども、三回殺してお釣りがくる。
もはや地面には消し炭がひとつ横たわっているのみだ。回復能力などでは到底追いつけない猛爆撃を受けて、夜の紳士はぴくりとも動かない。
「ヴァンパイアと戦う際はね、一撃必殺が鉄則ですよ。自動回復、吸血攻撃。長引けばそれだけ不利になる」
事も無げに教授は言った。
戦闘参加者はたったの二人。それ故に経験値の分け前も存外大きいものとなった。だがやはり納得がいかない。あれほどの魔法が使えるのなら、ヴァンパイアなど相手にせず、ドラゴンや巨人といった大物を狙えばよさそうなものだ。
「ヴァンパイアを狩る理由ですか? まあそれなりに目当てがありましてね」
経験値に続き、戦利品がカウントされる。金貨486枚、そして――。
“不死者の指輪”×1
ヴァンパイア・ロードのレアアイテムだ。滅多にお目にかかれない代物で、道具屋に売れば高い値が付く逸品である。特筆すべきはその効能。この指輪を装着していれば、戦闘で死亡しても生き返ることができる。死亡、即、キャラクターの消滅というシビアなシステムを採用しているこの世界で、蘇生効果は垂涎の的だ。
だがこれを装着する者はいない。仮にこれで生き返った者はヴァンパイアとなってしまうからである。操作不能になり、回復魔法も効かず、太陽の出ている場所では活動不能となる。
これほどのペナルティがあるために大方の冒険者はさっさと売り払って、その金で武器や道具を揃えるのが常だった。
しかし教授は、
「――この指輪、私に譲ってくださいませんか?」
冗談じゃない。売れば金貨2000枚にはなるお宝だ。そう易々とくれてやるわけがない。だいたい収穫は均等割りするのが原則だ。割れない物は換金して折半するのがルールである。
だが教授はしつこく食い下がる。
「これが狩りの目的だったのです」
魔術師ヴァンは最古参の冒険者。ゲーム内年齢はすでに七十歳を超えている。どれほど鍛え上げた冒険者も年齢には勝てない。いずれ老衰し、死亡し、消滅してしまう。
「ですがヴァンパイアになればそこで老化はストップします。もはや私の手を離れてしまいますが、しかし魔術師ヴァンは永遠の命を手に入れ、この世界に留まることができるのです。あなたもプレイヤーなら解るでしょう。手塩にかけて育ててきたキャラクターが消滅してしまう悲しさを」
「何と言われても駄目ですよ。第一、割り勘がルールじゃないですか。そんなことくらい教授だって知ってるでしょ?」
「そこを何とかお願いします」
「駄目なものは駄目です。指輪は売ります、それがルールです」
どうあっても説得に応じようとしないマサトの態度に、さすがに教授は諦めた様子で、押し問答を切り上げる。
「仕方ない。帰りましょう」
無言のまま、洞窟を逆戻りする冒険者たち。何だかしらけてしまった。
途中出てくるモンスターは小物ばかり、何の張り合いもない道程だ。コウモリ、山犬、毒蛇。
またしても岩陰からコウモリの群。鬱陶しいだけの雑魚である。
つい、と教授が前に出る。この程度の奴らなら毒霧で殲滅できるはずだ。
――が。
教授の唱えた呪文は相手を眠らせる魔法だった。しかもその指先はマーカスに向いている。呪文そのものは初歩的なものだが術者のレベルが問題だ。さすがのマーカスもあっさり眠りに落ちる。
「どういうつもりですか?」
身動きできないマーカスだが、マサトがキーを打てば画面にメッセージが表示される。
「早く起こしてくださいよ」
返事はない。
一瞬、不吉な想像が脳裏をよぎる。指輪欲しさに教授は俺を殺すつもりだろうか?
だがすぐにあり得ないことだと気がつく。プレイヤー同士の殺し合いは御法度。やろうと思ってもできないシステムになっているのだ。しかしいくつかの魔法は例外的に効果がある。催眠魔法もそのひとつだ。戦闘中混乱した仲間をおとなしくさせるために、故意に眠らせるという利用法があるからだ。
教授は襲いかかるコウモリに一切反撃せず、ある程度負傷したら薬草を使い、自分の体力を回復している。そしてしおを見てはまたマーカスに催眠魔法をかける。この繰り返し――。
“マーカスは眠っている”
“吸血コウモリDの攻撃。マーカスに2ポイントのダメージ”
“ヴァンは薬草を使った。ヴァンの体力が30ポイント回復した”
ようやく教授の意図に気付き蒼褪める。
確かにプレイヤー同士は殺し合いができない。だがモンスターに殺させることはできるのだ。
「きたねーぞ教授!」
無視。
“吸血コウモリCの攻撃、マーカスに3ポイントのダメージ”
“マーカスは眠っている”
“吸血コウモリFの――”
都合187回にわたる吸血コウモリの攻撃を受けて、歴戦の猛者マーカスはこまぎれの肉片になった。
“マーカスは死んでしまった”
そのメッセージが表示されるや否や、魔術師ヴァンは呪文を唱える。洞窟に紫の霧が立ちこめ、取るに足らない哀れなコウモリは瞬く間に全滅した。
マサトは茫然自失のていである。信じられなかった。こんなにあっさりと、しかもこんな形であのマーカスが死んでしまうとは。
「マーカスさん。まだ見ていますか?」
鼻くそ程度の経験値がカウントされる。戦利品は銅貨16枚と、戦士マーカスの遺品。
「――ルール違反はお互い様。棲み分けできない馬鹿は死ね」
それを最期に画面が暗転した。
マーカスの魂は天上へ送られたのである。
一週間ばかりは腹が煮えて仕方なかったものの、しかし性懲りもなくマサトはまた戻ってきた。レベル1の魔女メイアの名を借りて。
よくよくのゲーム中毒なのだ。
かつてはマーカスのご機嫌を取っていた冒険者も、駆け出し冒険者のメイアには冷淡だった。先輩面してアドバイスをくれる者もいるが、そんなことはマサトにしてみれば熟知の事柄、余程「俺はマーカスだ」と言ってやりたかった。
だがあくまでも素知らぬ顔で初心者を装っていた。かつては仲間だったはずの連中が、内心、彼を憎々しく思っていたことを知ったからだ。
「馬鹿だよ、マーカスは。こんなところで小銭稼ぎしやがって」
狩人のレブは嘲笑う。
「だいたいな、ネズミ講なんてのはいつか破綻するもんなんだって。あんなのに引っかかる奴はよほど頭が悪いか世間知らずのガキか、何にしたって馬鹿なことに間違いないよ」
あのネズミ講に参加した連中は軒並み村八分にされ、今はほとんど残っていない。外の世界を持ち込む者は冒険世界の住人を興ざめさせる。それが意地汚い欲得ずくの話ならなおさらだ。
だからメイアは沈黙を守り、先輩たちのあとに従って冒険に参加させてもらっている。一から始める煩わしさ。メイアの放つ電撃はマーカスの一撃に遠く及ばない。だが嘆いても仕方ない。マーカスは死んで、データは消滅したのだ。
この屈辱的な再出発にマサトは黙々と耐え、以前にもまして冒険し、メイアを一人前に育て上げることに心血を注いでいる。なぜなら、もはやこれは気軽なゲームではない。世界を救う旅なのだ。その使命感が彼を力づける。
不死者の指輪を装着した魔術師ヴァンは、隣の大陸へ繋がる海底トンネルを死に場所と定めた。そこであえてモンスターの手にかかり落命すると、目論見どおり指輪の魔力で蘇り、魔術師はヴァンパイアとなった。
「教授」の支配を逃れた不老不死の魔術師ヴァンは、現在、陽の差さぬ海底トンネルに巣くい、新天地を求める冒険者たちを圧倒的な強さで跳ね返し続けている。挑む者は殺されるか、さもなくば血を吸われて、下僕の吸血鬼となりトンネル内を徘徊するようになる。
海底トンネルで絶大な存在感を示す魔術師。奴を除かぬことには新たな冒険の場を求めることができない。それは衆目の一致するところだが、幻術、吸血、自動回復、それに加えて高レベルの魔法攻撃。誰もがこの怪物相手に勝ち目はないと諦める。
だがマサトは諦めない。復讐などという個人的な感情ではない。
この世界は死に瀕しているのだ。
吸血鬼に襲われた者は自ら吸血鬼となり、新たな獲物を探し求める。それが繰り返されれば、いずれ世界は吸血鬼だらけになってしまう。そうなってしまえばもうおしまいだ。悪夢のような食物連鎖、滅亡へ繋がる逆ピラミッド。人間は食い尽くされ、やがて吸血鬼も飢え死にする。つまり行き止まりだ――。
余暇時間を利用してゲーム世界を訪れるプレイヤーたち。彼らは仲間を募ってパーティを組み、モンスター狩りを楽しんだり、珍しいアイテムを収集しては悦に入っている。つまりは遊びだ。息抜きだ。
しかしマサトは違う。彼だけは心底世界を憂い、破滅の瀬戸際に立つ世界を救おうと奔走しているのだ。
膨張し続ける吸血鬼の群。いずれ破綻する世界。それを阻止するには教授の亡霊を仕留める以外ない――。
この世界に遣わされた、たった一人の救世主。
その重責を果たすべく、毎日毎夜ヴァンパイアの影を追うマサト。
当然ながら、学校に行く暇などない。![[fin]](img/main_lm.png)
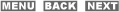
 |
 オカヤマ オカヤマ- オンラインゲームはやったことないです。ゲームの描写は超テキトーです。
- URL:20%off
|
|