上
もうたくさんだと阿美は叫んで家を出た。町を駆けて大通りに出るとはしとタクシーを止め、ふんぞり返って乗り込んだは良いものの、徐々に心苦しくなり胸のうちで感情がちゃんぽんにかき混ぜられ、やがてそれは悲しみの滂沱となって溢れた。荷物を詰め込んだプラダのバックを抱えながら黒光りしたシートに身を任せているうちに涙が溢れてきた。夕闇がとうに落ちた頃、懐かしい家の前で車から降りると、家(うち)では父親が相変わらずの様子で機嫌よく晩酌をして母親を呼んでいる声がする。阿美はもう引き返すことはできないのだと胸中で繰り返してはみるものの、それが逆に哀れにも家を飛び出してきてしまった事実にやや後悔を覚えた。
玉の輿ではなかったのかと繰り返して我が身を思えば思うほど怒りと悲しみに包まれ、なんのために自分はみなに喜ばれながら結婚をしたのだろう、どの面下げて家族に会うことができよう。前々から用意していた離婚状をダイニングのテーブルの上に置いてきてしまった。今更、どうして老い先短い両親を悲しませたものか。叱られるのは必定。息子の太郎がようやく年めいてきているのに、戻れば太郎の母、原田の奥様としてあんじょうにやってゆけるはずなのに、それを水の泡としてしまうのは、本当にもったいないことをしたものだと思った。
一度出てきてしまったものは仕方がない。玄関先でやはり戻ろうか戻ろうかと思案しているうちに、居間の方から父親の声。誰だ? と呼ぶので腹を決め、努めて笑ってガラス戸を開けると、おお、阿美か阿美かとご機嫌な顔が現れた。「どうした突然」
めっきりこの数年、太ってしまった父親の頭には白くなりすぎて、粋を通り越して滑稽にみえる。母の皺は深く深くなりすぎて、既に顔から切り離せない。ほう、阿美だ。阿美だ、やれ入れ入れ、よくこんな遅くにやってきたものだ、どうも不意に帰ってきたと思ったらどうした。我が家が懐かしくなったものかと好々爺が板についた父はほくほくと、母は奥から茶をだしてきてソファーに座らせて曰く、弟はどうしたのと問うた答えが、あれもお前のお陰で課長さんにも可愛がられて昇給も垣間見えているのよと高らかに笑う。原田さんの縁があるのでやはりお前は良いところに嫁いだ。太郎はいずれに居ますか。どうして今夜は一人で参ったのかと問うので、阿美は和やかに濁らして、まあまあたまには母親も休業したいのよとさえ言うがやはり心許なく、連れて来ようとは思ったけど風邪をひきまして、それほど大した風邪ではないのでハウスキーパーのお峰さんに任せて参ったのよと重ねるのだった。本当に悪戯ざかりで、といいつつも父親から煙草を久しぶりに貰ってふかしてみると途端に胸が苦しくなって、噎せ込むと共に涙をこぼした。
(だめだもうダメだと胸の内が騒ぐ)
父母はそれが煙に目を焼いたと思い、まあまあと笑い、奥より「ほら、これ食べなさいよ」と団子を持ってきた。訊いてみると昨日は確かに十五夜で阿美はその日付を忘れていたが、子供の頃にはこの居間で月を見ながら家族団欒として食べた団子と同じ味に餡子と黄粉を取りこぼしながら母親に叱られたっけと阿美は懐かしがり、味覚は記憶に結びついていて、次々に子供の時代を思い出すのだが、もう長い年月が経過してしまったという思いだけがじわりじわりと首を絞めてゆくようだった。
阿美は結婚してこのかた、団欒というものは知らない。
十五夜にお前のことを話ながら食べたものの残り物だけど、今夜来てくれるとは思いも寄らなんだ、ほんに心が届いたのであろう。高給取りの奥様ではなくて今夜は昔の阿美に戻って、甘いものは別腹と言うじゃないか、たんと召し上がれと盛られた皿を出され、どっと胸に詰まった堰が切れて涙が溢れた。不審がる父母の顔に向かい、やはり実家(うち)はいいものだとこぼして、出世は出世に違いなく、原田の妻ということなれば、片意地張ることさえ多かろう。お金持ちの方々に囲まれてさぞや辛かったに違いないと慰めの言葉に、首を振る。里方の家がみすぼらしければみすぼらしいほど、阿美は立派な結婚を続けて行かねばならないのだと思いもしたし、だからこそ七年もの月日を費やして身を粉にしたのだった。
ふと見ると、塗炭の屋根と隣の生け垣の僅かな隙間に丸く輝く十六夜の月が煌々として、隣の庭の木々の下に引っかかるようにしてあった。ごたごたと年月の積み重なった雑多な事物をとりえず脇に退けただけの小さな家の庭先の、鉄できたロッカーが、その脇にも小さな鉢植えや古い缶が錆び付いていた。原田の家の庭やベランダに比べてなんとみすぼらしいことか。だが、みすぼらしさの中に生来の積み重ねと子供の頃から阿美が育った歴史がある。阿美はふらりと僅かばかりの場所に荷物を置いた小さな庭の脇に引き寄せられて天を望んだ。徐々に高く上りつつある輝きは、遠き昔の夜を思い出させるのだった。
阿美は私は親不孝でございます。しばらくここに居させてください、この家が好きですとやがて語りだすが、そんなことは口に出すものじゃないのだと父母に叱られ、家に居るときは斉藤の娘、嫁に行っては原田の妻ではないか、よくよく考えなされ、勇さんの気に入られるようにして、精魂込めて家庭を納めぬ訳にはゆかないのかと懇々と口説きが始まる。阿美は私が悪いのではないのです、あの人が悪いのです。私はと床に崩れ落ちるのをみて、父はただならぬことと思いて、時計を見、もう十時ではないか今夜は阿美は泊まれば良い良いと背中を慰めるも、阿美はお願いがあるのですと、とうとう思いを口にした。
「私はもう帰らないつもりで家を出てきたのです。今日限り原田の家に戻らぬつもりででてきました。風邪なんかじゃありません。太郎を寝かしつけ、心を鬼にしてでてきました」
馬鹿っ。父は阿美の頬を叩いた。
肩を揺さぶり、どうしてそんなことをしたのだと詰め寄る。お父さんお母さん、察してください。私はこの七年間、誰にも夫とのことを話したことはありません。長い時間を考え二年も三年も思案した末の決断なのです。今日という今日は離婚をさせてくださいと、手を突いて謝るのだった。
「原田さんのどこが良くないのか」
そう詰め寄る父の顔をじっと見て、阿美は私の夫婦を半日ほど見ていただければ分かることだ、私たちは既に何もありません。顔を向かい合わせることさえなく、太郎が生まれるまでと、生まれた後ではあの人はまるで違ってしまいになりました。太郎の病気はお前の血だと私を蔑むのです。いいえ決して言葉には出しません。でもあの人の目は言葉より饒舌です。私は何度太郎を連れて死んでしまおうかと思いました。太郎はただ口がきけないだけじゃありませんか。その上私の生まれが貧しいのと、あの人は旧家の華族の出、峰子さんの前でさえも、親戚一同の前でも私の不器用不作法を殊更にたしなめられ、その上、周りの奥様方のように花や着物やピアノなどの趣味もなく、ないならないで習わせてくださってもよろしいのに、決してそのようなことはなされないので、私は実家の悪いのを吹聴されてるようで身も心も怯えてしまいます。だからこそ更にあの人は私を邪険に扱うのです。
(はじめは邪険に扱うことはある種の遊戯だと思っておりました。そうです、そのようなプレイに興じたのが夫との間を近接させましたし、私は奴隷、あの人は王様の立場のそのことを行う場所にて出会ったのでありましたから、初めは単なる放置の遊戯だと思っておりました。そしてその快楽は私を狂わせ、肉欲と情欲に我が身を墜としていったのです。確かに私は夫との行為に初めのうちは没入いたしました。いや、夫も没入していたと思います。だけどだけどだけど、きっと他の女に私と同じことをしているのだと思うと悔しいのです。私よりあの人が他の女の人と高みに昇ってゆくのを考えると、とても正気じゃいられませぬ。嫉妬をおくびにも出さず耐え忍ぶのはもうこれ以上イヤなのです。こんなことはお父さんやお母さんには聞かせられません。この人たちは至極まっとうな世界に生きているのです。どう伝えればいいのでしょう私の感情を)
阿美は指が壊れるほどに固く握りしめた。ですが、私はずっとそれに耐えてここまでやってきたのです。何をいうのと母は阿美を叱る。阿美は泣きながら、それでも私が堪え忍べばよいのでしょうとお考えになってると思います。でも、私はある時、はっきりと分かってしまいました。彼は私を愛してくれていないのだということをです。これ以上愛のない生活には耐えられません。私に飽きてしまったのでしょう。女を買ったり外に女も作っているという噂も聞こえてきます。もちろんあれだけの稼ぎがある人なら、それぐらい当たり前かと思いましてずっと我慢をしてきました。お父さんもお母さんも私の性分を分かってるなら、何も言わないで私を許してください。
見てくださいと阿美が差し出す腕には散々の切り傷の跡。
私は何度このまま死んでしまおうかと思いました。その度にあの人は冷たくなさるばかり。詰まらぬやつ。分からないやつと私を蔑むのです。そのまま死んでしまえばいいのだとさえ申すのです。
(かつてまだ関係が若々しかった頃のこと、あの人は犬の私に首輪をつけて深夜の誰もいない公園を散歩されました。私は全裸で凍えそうだったのですが、あの人はお構いなしに私の背中で煙草の火を消しました。今でも跡は残っております。あの痛さと悲しみと空白になってしまった感情をどう言い表せばいいのでしょうか。あの時、あの場所にいた、わたしたち、たった二人しか感じられないあの感情を、嗚呼、彼は失ってしまった。もっと更に更に高みに昇ろうとして行った結果、彼の冷たさは冷酷さを増し、やがてその場のことだけではなくなったのです。きっとあの人は私を蔑むことに快楽を見出してしまったのです。あの公園で過ごした夜も月がこのように明るかったのを覚えております)
私は勘違いをしておりました。その勘違いを信じて結婚をし、太郎を生んでしまった。嗚呼、残るは太郎のことのみ心残りだ、太郎さえ健やかに育って欲しいと望みながら冷え冷えとした家庭に留まっておりました。
父と母は頭を抱えて、お前がそのような性分だと分かって結婚したのではないのか、だがしかしとしばし考え、太郎はどうする。太郎は片親になってしまうし、それに病もある。「そうなのです。そうなのです」
阿美は涙ながらに訴えた。母も涙を押し殺しながら、初めからおかしいと思ってました。あまりにも良い条件で阿美を娶るということで、あまりにも多くのお金を頂き、丁度暮らしも辛かった時期だったのもあって私たちは阿美を嫁がせてしまった。何もしなくてよい。原田さんは何かあるのだったら自分が全て引き受けるといいつつ、また私たちにお金を持って寄越すのでしたのよ。まるで女郎の身請けではないかともさえ思いもしたし、だからこそ私たちは受け取るだけじゃ良くないから小さな工場でもそれが唯一の財産だったのだけど、原田さんに譲ったりもしたのです。それでも周りの人はいぎたなく私たちが娘を売ったとさえ陰口をする始末。私は悔しゅうございましたよと言いつのりて、どっと二人ながらに泣き始めるのだった。
いっそのこと裁判でも起こしてとっちめてやらねば腹の虫が治まらぬ。私は悲しいのですと母は阿美と共に訴え、父さん父さん、あなたはどう思います? 男ならここで勇さんの行状をあちらのお父様にお伝えになっては。あまりにも阿美が可哀想で可哀想でとよよと父親に取りすがるのだった。
目を瞑りじっと腕組みをしてた父は思案の様子を見せてから口を開く。母さん、無茶を言うでない。待て待て。俺はそこまで酷い様子だとは思ったことはなかったし、なるほどお前の話をきいてみてはじめて勇君がどのような男だったのか分かった。己の不見識を悔やむ上にお前がどれほど苦しんだかがわかった。だが、阿美。俺の話を聞け。ああ見えても勇君は学もあり立派な大人として社会に貢献している。会社もいくつも持っていて常に働いているような男だ。女遊びもやがて飽きるであろうし俺にも覚えがある。
だからお前は帰れ。今晩は帰れと父は口をすぼめる。そしてよく、訊け。阿美、とじっと阿美の顔を見た。お金もかけず子供のような身なりだった若い頃の阿美を思い出し、毛皮のコート、プラダのバッグ、豪勢な指輪。
かつての阿美を知る者にとって、この七年間の変化は見違えるようだった。癲癇持ちのお前をよくぞここまで身なりのしっかりした奥様にしたてあげたものだ、勇君の様相には確かに癪に触るが、よくよく考えてみればあの男が阿美が成長しないとがっかりするのも仕方がないと思われもする。そうだ、阿美。お前が苦しいのは分かった。はじめはもしや離婚を言い渡されたのか、それとも何かの事件があって今日は帰ってきたのかと思っていたが、なるほど話を訊いてみるとお前の言うことは尤もである。だが、今のお前を作って支えてくれているのは誰だ。勇君ではないか。逆にお前が勇君の必要とする条件を満たすことが出来ては居ないのではないかとさえ思えはしないか。いいえ私もそう考えて努力したのですよ、お父さん。何度も何度も考えて、その結果に今晩家を出てきたんです。いいや。そうじゃないと、父はいう。こと努力と言うものは、二つあってな、一つは己のため、もう一つは他人のため、二つの努力がある。片方が欠けても良くはない。お前がした努力は、外面を作った仮面のような努力であって、お前の中身は昔のまま、そして昔より我が強くなり、わがままな表情になってはいまいか。内と外との努力のバランスをとること、それがお前には一番必要なのではないか。いくら生活や衣服を飾っても、お前の中身はついぞ変わっておらぬ。わかるか?
阿美は泣いて父を責めた。お父さんは何も分かっていない。私がどれほど心を苛んだかお分かりか。勇さんの気に入るような人間になろうとどれほど苦労したか。その私の思いはどれだけ分かってくれます。
それだ、そこだよ。阿美。気に入られるような人間になろうとしてるところが逆説、嫌われる原因なのだ。お前は自分と勇君の間にある接点を見つけなければならない。お前は自分の内側を認めて自らになることを拒否している。拒否しながらそれでいて気に入られようとするのは、本来の夫婦のあり方ではないし、勇君がそう望んでいるとでも思うのか。他人に気に入られようとすればするほど、お前の中からお前は消え去ってゆくのだ。やがて、空っぽだけにになって、自分は愛されていないと涙するのではないか。そのところをよく考えろ。それに太郎はどうする。太郎は原田の子。お前は斉藤の娘。一度縁が切れてしまえば二度とは会うことができなくなるやも知れぬ。その上、弟の登はどうだ。あの目立たぬ子が今の地位で暮らすことができるのも勇君の口添えかも知れぬ。ひとつはお前のため。ひとつは太郎のため。ひとつは登のため。一時の怒りで全てを水の泡にしてしまうのはあまりに無謀。よくよく考えてみなされと言った限り父は沈黙する。お父さんそれはあんまりですと母は目を丸めて父と阿美を見比べた。
阿美は、いいえ、太郎のことを思うと居ても立っても居られませんと胃の中がキリキリ痛むのを感じた。
(ああ男というものは決して女に対して良いことを言わぬ。己の男たる立場を護るためにだけにわれら女を苦しめるのだ。男なんてみんな同じだ。父も勇も同じだ。憎い憎い憎い憎い憎い憎い憎い憎い憎い憎い憎い憎い憎い。いっそこやつらの股間を切り落として女にしてやろうか。いや。ちがう。そんなものに左右されてしまう自らが憎い。悔しい悔しい悔しい悔しい)
離縁ということを言うのも私の我が儘でした。なるほど太郎に別れては生きていても仕方がありません。この家に連れてこようとも太郎を病院に通わせるほどのお金もなく、登の一生にも関わることでしょう。申し訳ございません私が涙を飲んで堪え忍べば物事が総てよき方向で動いていきますもの。私さえ死んだ気になれば四方八方が丸く収まりますものと涙ながらに繰り返すのであった。
合点がいったなら、はよ帰れ。もう夜は遅くなってしまったがまだ大丈夫だ。車を呼んでやろうと電話を取る手が僅かばかり震えている。母はああ、不幸せな娘だと再び泣き崩れるが、阿美はすっくと立って、きっと私の脳がおかしかったんでしょう。もう二度と夫を誹るまいと思いますと玄関に出る。次に会うときは笑ってお目に掛かりましょうと瞼を拭った。ありがとうございました。では、と家を出る。
下
さやけき月の風の音がそよいで虫の音絶え絶えにもの悲しい中をタクシーに乗り込んだ。上野の池のほとりまで辿り着いた時、阿美は思い切って車を止めさせた。窓の外に見える池には茅の穂が幾筋も見え、その合間に映った黄色い月が揺れているのだった。
そして「お客さんここでよろしいので」と運転手が振り向いた顔を見て、阿美はにわかに信じられぬ思いに戸惑った。誰やらに似ていると思い、いくつもの顔が浮かんでは消えて、最後にある若い少年の顔に辿り着いた。男は高校生の弓道部の先輩で、阿美が僅かな時期だけれども相互いに愛した男だった。
やはり分かりましたかと男は頭を掻いてにやりと笑う。
「斉藤の阿美さんだったのだと途中まで気づかず、私はよっぽど鈍でございます」
ぐっと笑った岡本先輩は俺はまさか自分がお前の家から呼ばれようとは思わなんだ。どうだ。結婚したと訊いたが、その後どうだ? 幸せかと問うので阿美の胸にも甘い記憶が沸き立つのを覚えた。岡本先輩は阿美が初めて付き合い初めての男だった。高校生の頃、先輩に憧れて付き合い、二人で深夜の街を徘徊し初めて躯を染めたのも嗚呼、この上野の街だとおもうと阿美はこの偶然、途端の懐かしきに惑い、何年振りですか岡本先輩はその後どのようにしてタクシーの運転手になってしまわれたのです。とても学業ができて、阿美なんかが逆立ちしても届かない大学へ進んだ後の十年。俺の家は没落した。学生の頃に家業が倒産し、学業を中断してバイト暮らし。その後インドに渡って放浪をして戻ったところが仕事も金もない。頼る身内は離散してだだ一人自分の身だけ。その日暮らしさえやってゆければ我が身のことなど詮無いことで、妻子の居ないことが幸いか不幸か、ただ一人日がな一日この車の中よ。そういって、お前は幸せそうだ、昔のままに綺麗でその上金銭も充実した日々を送っておるのだろうと見える。翻って何を楽しみにハンドルを握っているものか。金が貰えれば嬉しいが酒が飲めれば嬉しいが、考えれば何もかも嫌になり、気が向けば客を乗せ、気が向かねばひがな部屋で煙のように生きておる。懐かしさと我が身の空しさと引き替えにこのままお前をどこか遠くまで連れ去ってしまおうかとさえ思ったりするも、君が車を止めてようよう我が執念を抑えきりました。
何をいう。私はかくかくしかじかでと、阿美はこれまでのいきさつを述べ、実は私はこのお池に身を投げようと思ってここで車を止めたのですと泣きはじめる。いっそ恨めしい。昔の我らに戻ることができたなら、けっして互いを離しはしないものの、年月だけがとうに行き去ってしまい、我は子持ち、あなた様は身をやつしておられます。いいえ、私にも実は子がいましたと岡本先輩はいい、学生の頃に僅かばかり交際を持った女性が子を産んで我が家が離散した頃に病を持って二つにもならずに死んでしまった。我も子も捨ててしまいましたと阿美。実は離婚届をテーブルの上に置いたまま家を出てきたのですと初めて打ち明け、もう帰る場所もないのです。実家には家に戻るといい、家には実家に戻るといい残して来ました。ならば思うことも多かろうと岡田先輩は阿美を遅い夕食に誘い、時間がと時計をみるも、そんなものはもう既に必要なく阿美は家を捨て父も母も捨てた。ならば共に暮らさぬかという言葉が出るのも畢竟数時間経過した懐かしいホテルの部屋で、お前は子を産んでも魅力的だ、なんなら俺は身を粉にして働く。私もこれほど身を焼くほどの交わりは初めてだと、ならば太郎を引き取ってもいいの。あの子は私の生き甲斐。いいえ私はあの子を一度捨てた。今更引き返す訳にはいかないと、それならそれで身ひとつで俺の家へ来てはくれまいか。俺はもう一度人生とやらを引き返して生まれ変わることができるやも知れぬ。先輩。いや昔のように真一と呼んでくれ。真一さんあなたは私の腕の傷を見て何も思わないの? 大丈夫だよ。あなたは私の背中の鞭の跡を見て何も思わないの? 大丈夫だよ。あなたは私に首輪を付けてくれるかしら。大丈夫なんだ。あなたは私を犬と呼ぶ意気地があって? 大丈夫。私はあの人によって変わってしまったわ。私はもう以前の私ではないの。私の身体にはあの人が付けた傷跡が数多く残ってる。大丈夫さ俺はお前を愛しているのだからと、朝までにホテルに置かれた具物が足らず近所のコンビニまで買いに走りて身を交え続けた。
月はやがて沈みゆるやかに日が昇り始めると長く語り合った両者はたわわな夢に浮かされたまま、うとうとしかけたところに阿美の携帯がかしましく鳴り響き、お前はどこにいるかと勇の声。父母の元にも居ず、我が家にも居ず、太郎は泣き、テーブルの上には紙の証書。何をしておるとの怒声に阿美はぷつりと電源を落とし、男の胸で泣き始めるのだった。私はずっとあなたと別れてしまったことを悔いております。もう一度初めからやり直したいと思いますのという阿美に真一は気が大きくなったものか隆起して、阿美の頬を叩く。何をなさるのですかと問いかける阿美の背中に腰を下ろして、お前は犬だと始めるのだった。阿美は身を真っ赤にして震え上がる程の興奮を感じるものの、勇との出来事を思い起こして真一でさえも我をもてあそび愚物のように扱うようになるのではないかとも恐怖しつつ、それでもわんわんと吠えるのだった。
なあ、ここで今日は待っててくれ、俺は車を返してくると真一が伝えたホテルはビジネスホテル。阿美はこれまでのこととこれからのこととを天秤にかけ、既に全てが過ぎ去ってしまった一夜を思い起こして先の不安と生来の出来事を思い、さめざめと涙した。部屋に仕付けられた冷蔵庫からビールを取り出し、狭いビジネスホテルの部屋から非常階段にでて望む美しい町並みと足下を流れる車たちや雑踏、人々の行き交う姿を見下ろしてから、深く深く溜息を吐くのだった。疲労感と充実し高揚した血が身の中で静かに鼓動していたが、やはり先々のことなど考えると不意に絶望もよぎってくるのだった。ホテルの部屋で鏡に映して見た自らの醜い姿。肌も一〇年前に真一と見た様子と違え、年齢も重ねたが何一つ身に積み重ねることができず、何も自身も糧もなくただ太郎が我が身に宿り、その太郎のため勇さんのために過ごしてきて、振り返ると様々な出来事があったような一〇年であり何もなかった一〇年でもあったのではないか。蝶よ花よと言われ続けた若い頃に比べて既に自らの身の処し方を知りすぎていて、犬よ奴隷よと言われた時期も、妻よ母よと言われ続けた時期も、我は我の真の姿を見ることなく過ごしてしまったとの後悔を感じ、慌てて安定剤を水道の水で囓りついたが芯から安定するはずもなく、足下で行き交う人々の姿はそれぞれ私事と自己の安定の基盤を保ちつつ日々過ごしているのではないかと嫉妬した。はて、生き辛い世の中よと我の生はここにあり、そしてここにない。どこまで我は我の身体と心を保つことができるのか、我は何のために生きているのかそれすらもわからなくなった。太郎を捨ててしまったのだ。阿美は涙した。真一との快楽は久方振りかに感じた自らの生だった。勇に黙ってることもいっぱいある。私がそれなしになんて居られやしない。何度も逢瀬を重ねた相手もいる。何度逢瀬を重ねても、決して彼らは私を煉獄からは救ってくれなかった。王子様も現れなかった。きっと勇はそのことを知っているのだ。そうに違いない。胃が痛く悲しい。そしてそんなことを思うのは綺麗に澄んだ空がまぶしいせいだと思う。
秋の晴天は乾いて、冷たく天上と地上とを突き放しているように見えた。
阿美はふっと建物から見える上野の池の様子が見たくて錆びた非常階段をカンカンと足音を立てながら四階から八階までの高さまで上り詰めると開かれた屋上があり、かんかんと晴れた晴天の空の下で我は一人だと感じる。
空は雲一つなくやたらめったに人を励ますように澄んで、阿美は訳もなくむかむかとして手のビールの缶を道路に向かって投げた。地上に落下するまでの間、缶の口から溢れた泡沫が軌跡を描くようにゆるやかな弧を描いて道路の真ん中に落ちた。残念ながら車にも人にも当たらず中央分離帯の部分に落ちて、コロコロ転がって後から来た車に轢かれて爆発するように潰れた。不意の衝動に牽引され叫んだ。「ばかやろう」
声が近隣のビルの谷間に跳ね返って広がってゆく。阿美は繰り返し叫んだ。「ばかやろう」「ばか」「ばか」「ばか」「ばかばかばかばか」
声が枯れると共に叫べば叫ぶほど身体の中身の細胞までもが弾け飛ぶように思えて、なんだって出来ると勇気が湧いて来るように感じられた。ふと悪魔に見入られたように私は幸せだと思った。真一が阿美が待ってるはずのホテルに辿り着いた頃、雑踏の人垣の真ん中に阿美の身体が舞う。
これが夢なら醒めないで欲しいと、今ここで別れたら二度と会えなくなるような気がして仕方がない、あなたと離れるのがとても辛い。早く戻ってきてという部屋から出る時の彼女の言葉が何時までも真一の耳の中にいつまでも残り、さてはて原田の家も斉藤の家も岡田の胸にも憂きことなお多く、人生も憂鬱かくも多くか。![[fin]](img/main_lm.png)
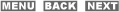
 |
 サイキカツミ サイキカツミ- 新5000円札の顔が怖くてたまりません。余りにも怖いので5000円が手に入ったらさっさと崩してしまいます。お金ってどうやったら溜まるものでしょうか?
- URL:ぞうはな
|
|


