 「ああ、なんて罪深い恋」
その言葉に弾かれたように、先生が私の胸から顔を上げた。
「なんですって」
「ええ、だって、そうでしょう? 」
私は跨っていた先生の膝から降りると、腿を伝う白濁としたものをそのままに、床に落とした着物を拾い上げた。
「父と変わらぬお歳の、しかも、人を教え導く教師と、教え子だなんて」
未だ体は火照り、切れ切れの息の合間に言葉を紡ぐ。
「なんて罪深い恋なのでしょう」
ああなんて罪深い。
ふと思い付いて口に出した言葉。
それは思った以上に甘美に響いて聞こえ、私は一人、何度も反芻してはその度にじわりと滲み出る蜜に酔い痴れた。
それを、
「恋?」
ふいに妙に甲高い声が切り裂いた。
「罪深い恋?」
「先生?」
あとは絞めるだけだった帯紐から手を離し、椅子から立ち上がった先生を仰ぎ見る。
夕陽射し込む窓を背にした先生は暗く染まり、その表情を窺がう事は出来なかったが。
ざあっ、と嬌声の余韻を含んでいた空気が消滅したと本能で感じる一方、意識の端で、そういえばここは教員室だったと今更ぼんやり思い出していた。
「違いますよ」
「何がです」
「あなたはやはり、まだなにも知らず、若いのだね。まるきり」
首を傾げて見せる先生の声に、微かに笑が滲む。
「昔の私です」
私はからかわれているのだろうと思った。
しかし愚かしくも、先生と若い頃と一緒などと言われ嬉しくも感じていたので、
「そうですか」
と答えるに留めた。
「そうですよ。だってあなた、取り立てて罪深い恋なんてものは無いのですよ。恋そのものが罪悪なのですから」
先生は膝まで下ろしたズボンを履き直し、じじ、とジッパーを上げる。
焦げ付くその音を押しのけて、罪悪、という言葉が耳の中を暴れまわった。
「恋が罪悪なのですか」
「罪なのです。恋は」
「なぜですか」
突然先生はふふっと笑いを零した。
「本当にあなたは私のようだ。それとも若いとは皆こういうものなのでしょうかね」
「答えになっていません」
「ああ、失礼。あなたを不愉快にさせるつもりはないのです。ただ、かつて先生に私が質したことを、私が先生と呼ばれる今、逆に質されている。これも共犯者の宿命かと思うとおかしくてたまらないのです」
「共犯者、ですか?」
「恋は罪悪だと、言ったでしょう?私は、今日まで、私の先生からその罪を引き継いできたのです」
「罪悪とは。罪とは、一体何ですか」
先生は隣の椅子に掛けられた背広を取ろうと、ゆらりと背を屈めた。
「とても重く、漆黒の、長い髪に巻かれるような罪。一つですら抱えきれない」
その顔が、さっと陽光に照らされる。
「それでは、私と先生との恋は」
「だから私はね」
ああ先生、あなたは私の震える声を遮り、
「私は今迄たった一度も」
今から私に絶縁を突きつけるのであろうに、
「恋をしたことが無いのですよ」
なぜそんなにも穏やかな笑顔を浮かべていらっしゃるのでしょうか。
言葉で斬りつけておきながら、姿で見惚れさせて、それを罪悪以外の何物だとおっしゃるのです。
「おや、もうこんな時間ですか」
黒の背広を身に纏い、銀縁の眼鏡を掛けると先生は、机上の袱紗と数珠を丁寧に鞄に仕舞い込んだ。
「先生」
「贖罪に行ってきます」
がらりと戸を開けた先生は茜の光を一身に浴びて、真っ黒な影になった。
「今日で時効なんです」![[fin]](img/main_lm.png)
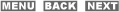
 |
 水屋ナヨキ 水屋ナヨキ- これは冒涜にならないか、と迷いながらの執筆。
しかし眼鏡だけはゆずれません。
- URL:ミズ屋
|
|