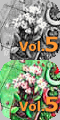- 特集「見る」
- 哲学者からの手紙
- 「書」
- 難しさにこそ、魅力が
- Talk Session
- みることからふれることへ
- 「見る」から「描く」へ
- Novel
- スイッチング・ウォッチング
- 同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
- よくばりな眼
- 秋の夜の夢
- 王子の見た景色
- ちいさなひとひら
- 宣告
- バードウォッチング
- see
- 見る
- Use your eyes
- おしりやぶれたズボン
- アイズ
- 万華鏡の世界
- Coffee Break
- ズレないBookCover
- Series
- メッセージをどうぞ
- おいしい水
- 不愉快なテクスト
- "いろは"の先のCSS
- Player's Side
- from editor
- 次回予告


哲学者からの手紙
坂本秀人 絵描きは目の前の風景をカンバスに描き、カメラはフィルムに像を焼き付ける。こうした置き換え作業にはそのもとになるものが必ず前提されていて、昔の人はそれを「ものそのもの」などと呼んでいた。カンバスに描かれる絵のもとになっている世界の風景のことだ。
情報という言葉が今世紀の流行語だとして、いったいこの「情報」の本体とは何だろうか。河原に落ちている石を拾ってこれをじっとみつめる。さまざまな彩りを含み、光の加減でいろいろな形に変容する。
絵描きはこれを素描する。
カンバスに描かれた絵は世界の中に存在する単一の石を指示している。そして僕らはこの描かれた絵を、情報と呼ぶ。
情報そのものはカンバスという物質に描かれた絵だが、カンバスという物体ではない。カンバスに付随する非物質的なものだ。
もしも情報がそのような性質のものなら、なぜ石そのものを情報と呼ばないのだろうか。カンバスの絵よりもずっと正確かつ、緻密な情報を含んでいる当の石そのものはなぜ情報ではないのだろうか。
そしてなぜ風景そのものが芸術になり得ないのだろうか。なぜ目の前に展開する事象そのものが物理法則になり得ないのだろうか。
世界にもしも人間がいなくて、世界を認識するものがなかったらもとより情報などというものは存在しないと考えるのが妥当だろう。とすると、情報というのは、人間と「ものそのもの」を結ぶある種のインターフェイスの役割を果たしていると考えるべきであろう。つまり、情報は、人間の認識にうまく合ってくれるように対象となるものそのものを加工したものなのである。
実のところ、我々は世界がどのようなものなのか確実に知ることはできない。僕らに見えるもの、それは鼻の上についた一組の眼に残される像だけだ。その像は我々の心や身体の限界によってすでにかなりデフォルメされている。
産業革命が始まろうとしていたドイツにカントという哲学者が現れて、初めて「ものそのもの」(Ding ansich)という言葉を用いる。彼は「ものそのもの」への我々のアクセスが不可能であることを唱え、我々にできることは、せいぜい心に現れた像(表象などという)を加工して理解することだと考えた。折りしもニュートン力学全盛の
時代に再び哲学的逆転をなした時代的な事件である。(しかし、皮肉な見方をすればこのようなことを言っているからドイツは他のヨーロッパ諸国よりも産業革命達成が100年もおくれたのかもしれない。)
つまり石そのものに我々はアクセスできない。せいぜい、眼に写る像や、カンバスに描かれた姿から、石の本性を理解するくらいなものなのだ。
明示的ではないにせよ、情報という発想の起源はここにあると思う。この表象という概念は現代になってラッセルなどが再びとりあげ感覚所与などと呼ばれて今世紀初頭に華々しく登場した論理実証主義のキータームにもなったが、その後は旗色が悪く、少なくとも認識論の文脈で公然とこのようなインターフェイスの存在を唱えるものはいなくなっている。
しかし、記号論的に拡大解釈すれば、カンバスの絵や、写真、さらに網膜の像などを一つのインターフェイスとして考えることができる。そして、それを情報と呼ぼうと感覚所与と呼ぼうと、いずれにしてもそれなしでは我々はものを認識することができない。一方でこの情報は一種の加工品であり、ものそのものではない。また、このような本性から、情報は多様なあり方が可能になる。つまり、世界の様々な側面を別個にとらえたものが、それぞれ独立した情報として機能することができる。このような情報、もしくはインターフェイスの多様性に端を発し、哲学的、物理学的、数学的パラドクスがもたらされてきたと思う。僕が知っている限り、この事態を一つの具体的な場面で指摘したのがニールスボーア(注1)であり、量子力学のコペンハーゲン解釈は情報と宇宙(ものそのもの)とがぎりぎりの線で生み出す奇妙な軋轢の象徴になっているようにも見える。
また自然数論という理論がものそのものに出会ったときゼノンのパラドクス(注2)が生じるのかもしれない。
幸か不幸か、我々は生物の進化論的な過程で認識能力を高めてきた。外の世界が本当はどうなっているかは分からないけれど、少なくともそのような認識能力を備えることで、身を守り、子孫を残すという見事なシステムに進化してきたと思う。ところがこの認識能力というのは実は世界をありのままに知覚するという能力ではなく、我々の生存に必要な認識のフレームワークを構築するということに他ならなかった。
我々は世界に触れることによって、そこから世界に関する青写真を作ることになる。しかし、その青写真は、世界をみつめる視線の角度によって微妙に違ってくる。同じ対象を描写しているにもかかわらず、青写真ごとに、微妙な輪郭のずれが生じてくるのだ。
錯覚というのは、二つの認識上のインターフェイスが衝突した時に生じるものと言えるかもしれない。二つの青写真を重ねて透かしてみたら、ぴったりと一致しない…。
こういう状況がまさに錯覚なのだと思う。
錯覚という言葉は、元来、「正しさ」と「誤り」というものを前提している。しかし、この二つの概念はかなり人為的なもので、本当は、錯覚を単なるフレームワーク同士の衝突とか、「歪み」みたいなものとしてとらえるべきだと思う。
「錯視」における正しさの基準は、科学的事実とか、物理的事実と言われているものかもしれない。しかし、科学理論や、物理学が、我々の経験を通して、しかも、我々の言語を用いて構成されたものであることを忘れてはいけない。
「本当は、同じ長さなのに、違う長さに見える」という錯視現象において用いられる言明は、同じという言葉の背後にある我々の日常的、古典的なメジャーに依存しているけれど、例えば、相対論的な距離というのは、ユークリッド空間における距離とは違うスカラーという規約に基づいているので、相対論を持ち出した途端に、長さに関する「同じ」という言葉の有効性が俄かに怪しくなってくる。
正しさの本当の基準とは何だろうか。
これは難問だ。
雨上がりの空を見ると、飛行機が通り過ぎ、足元には水溜まりができている。飛行機は流体力学に基づいて進むし、水溜まりは表面張力のおかげで、形を保つ。この程度の風景ならば、「見え」と「理論」との間に歪みは生じてこない。見えかたは、そのまま理論でシミュレートすることができる。ところが、ミクロな世界になると、「見え」と「理論」の間の乖離は極端な形で現われてくる。量子力学のもたらした奇妙さや不快感は、まさにこのことに由来する。
いずれにしても、「見え」も「理論」も我々人間の側のストーリーであって、そんなこととは無関係に世界はある。「正しさの規準」という発想そのものが実はとてもローカルなものなのかもしれない。
世界の話を哲学者がするのは気が狂ったときか、死ぬ間際かのいずれかだと思うけれど、あえて、言えば、宇宙は、霧のように姿をもたない実体だ。僕らは、それに認識の光を当てる。そうすると、世界は、ある形になって見えてくるけれど、光の当てかたによって一様にはならない。
それはあたかも、三次元の物体を二次元の平面でスライスするようなもので、当の物体の側面はとらえることができるかもしれないが、それは世界の本性にはならない。
我々は数千年の間、世界のあり方を見つめてきた。そこには幾重にもなった時間の層があり、歴史の中の重みがある。
しかし、それは、霞をつかもうとする森の人の姿とどこか似ている。
世界に姿はない
霧の空間は
認識というレンズの背後で静かに像を結ぶ。
- (注1)
- ニールスボーア。Niels Bohr(1885-) デンマークの理論物理学者。量子力学を創設した代表的な人物であり、その後の量子力学解釈において標準的とされるコペンハーゲン解釈を提唱している。当初から量子力学に対して批判的であったアインシュタインとは、数多くの歴史的論争を残している。彼は、アインシュタインとの論争の中で、これまでの物理論争にはなかった、認識論や、言語論にまで及ぶ議論を展開し、量子力学に端を発した一連の論争の根底が、純粋に物理学的なものではなく、概念的な要素を含んでいるということを指摘している。古典的な物理学が、我々の常識的な「見え」を反映したものにすぎず、対象の状況によっては、そのようなフレームワークを放棄せざるを得ないことを主張する。特に古典的な「実在」という一見あたりまえの物理概念が単なる「常識」以上のものではないとする議論は半世紀が過ぎた現在も未だに論争の焦点になっている。→戻る
- (注2)
- ギリシアの哲学者ゼノンの名前のつけられたパラドクス。話はアキレスと亀の逆理と同様である。先行する亀に、どんなに足の早いアキレスでさえもおいつくことはないという。t1に亀がいた場所に、t2においてアキレスは追いつくかもしれないが、その時点では亀もt2-t1時間分だけ先に進む。この繰り返しを無限に繰り返してもアキレスは亀においつくことはない。これは物理的事実ではない。事実は、アキレスはあっというまに亀を追い抜いてゆく。しかし、何故事実ではないのかわからないというのがこの逆理の本質だ。これは、自然界が連続的であるにもかかわらず、この議論で用いられる無限概念が、操作無限だからだと僕は思う。つまり、自然数論というのは元来自然なものではなく、我々人間の身勝手なフレームワークなのかもしれない。一個、二個、三個…とものを分割して考えるというのはもしかしたら単なる「見え」にすぎないのかもしれない。これは古典的な物理実在像が、単なる「見え」に過ぎないとしたボーアの議論とパラレルに見える。ただし、ここでの議論は少し「悪乗り」だと思うので、酒飲み話程度に思ってもらえればよい。まだまだ多くの数学者がこの問題に取り組んでるのだから、そう軽率なことを言ってはまずかろう…。→戻る

 坂本秀人(さかもとひでと)
坂本秀人(さかもとひでと)