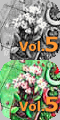- 特集「見る」
- 哲学者からの手紙
- 「書」
- 難しさにこそ、魅力が
- Talk Session
- みることからふれることへ
- 「見る」から「描く」へ
- Novel
- スイッチング・ウォッチング
- 同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
- よくばりな眼
- 秋の夜の夢
- 王子の見た景色
- ちいさなひとひら
- 宣告
- バードウォッチング
- see
- 見る
- Use your eyes
- おしりやぶれたズボン
- アイズ
- 万華鏡の世界
- Coffee Break
- ズレないBookCover
- Series
- メッセージをどうぞ
- おいしい水
- 不愉快なテクスト
- "いろは"の先のCSS
- Player's Side
- from editor
- 次回予告


よくばりな眼
茶石 文緒 僕の恋人は眼球を持ち歩いている。眼窩に嵌まった自前のそれではない、生のつるりとした眼球をひとつ、肌身離さず持ち歩いているのだ。
彼女によれば、それは9年前に亡くなったふたごの妹のものだという。目の前で交通事故に遭った妹は、まるで小さなメッセンジャーのように、こぼれ落ちた眼球を彼女の足下へ遣わした。アタシヲマモッテ、誰かに踏まれたり、汚されたりしないうちに。彼女は息を潜めてそれを拾い上げ、素早くポケットに隠した。その日以来彼女はそれを、自分だけの秘密として守り通してきたのだ。
「ねえ、こんなこと、おかしい? 私のこと、狂ってると思う?」
つきあい始めてまもない頃、僕はその秘密を知らされた。薄暗いカフェのテーブル。目の前には小さな眼球が水晶の占い玉の如く鎮座していて、無言のまま僕をじっと見つめていた。
確かに最初は相当驚いたし、テーブルの上に眼球が転がっているさまは、確かにグロテスクと言えなくもなかった。でも、僕は彼女に本気で恋していたし、自分で自分のことを、眼球ひとつで思いを翻すような安易な男だとは思いたくなかった。僕は軽く宙を見つめ、自分の中に広がる領分を素早く計測した。好きな女を受け入れる場所があるのなら、プラス小さな眼球のひとつくらい、どうにでもなるような気がした。彼女を愛するならその眼球も「込み」ってこと、そう結論を出して僕は頷いた。
「うん、わかった。仲良くやろう」
その答えに満足したのか、彼女はようやく、温んで泡の沈んだメープルラテに口をつけた。僕は煙草を吸いたいと思ったが我慢した。なんたってその眼球には瞼がないのだ。煙など吹きかけようものなら、ひどくしみるに違いない。
こうして、僕と彼女と妹(眼球のみ)の日々がはじまった。
妹は一言も話さない。身動きひとつしない。その瞳に感情らしきものが宿ることもない。ただ小さな眼球の姿で、僕たちを見ているだけだ。
本来は二人のものであるはずの空間に、第三の視線が在るということ。それに最初は軽い異物感を感じたが、すぐに慣れた。僕たちはそういう世の中に生きている。他人に見られるだけでは飽きたらず、自分で自分にレンズを向けることも当たり前。自分たちは見るものであり、同時に見られるものになる。境界線は限りなく薄く、立場をシフトすることはあまりにも容易い。
彼女は幸福な体験だけを妹と分かち合おうとした。退屈なものや残酷なものは見せる価値がない。自分が幸福だと感じる場面だけを選んでは妹の眼球を袋から出し、その虹彩に映してやった。
とりわけ彼女が好むのは僕と二人きりでいる場面。妹の眼前で彼女はことさら、甘えたがりの猫のように僕に体を預けた。それはどこまでも自然でありながら、隅々まで神経が行き届いて美しいシミュレーションでもあった。
「わたしが幸福なのを見せてあげて。それで、あの子も幸福になるの」
そんなとき、彼女の意識の一部は必ず妹のために割かれている。妹の目から見て美しく見える角度と表情を彼女は知り尽くしていた。手を重ねるときには必ず僕の手が下になる。入念に施したマニキュアが隠されてしまっては意味がない。それは僕の気を惹くためであると同時に、妹の眼を愉しませるためでもあった。
感想を訊く事ができないので、その映像を妹がどのように受け止めているのかは解らない。でも、僕にとっても、普段は毅然としている女が蕩けるように僕に甘える様を見るのは心地よかった。彼女はまるで自分に暗示でもかけるように僕との恋にのめりこんでいたが、その背を押しているのは他ならぬ妹の存在だった。妹が見つめるほど、彼女は僕に近くなる。妹に関して突っ込んだ話をしないのは、姉妹の絆への敬意や遠慮よりも、僕と妹の利害が一致していることが大きかった。
その時、僕たちは夕暮れの砂浜に座っていた。天気は生憎の曇りで、色鮮やかな夕陽などは望むべくもない。でも、それでよかった。そのほうが何の思惑もなく、自然に体を寄り添わせることができたから。
妹も少し離れて僕たちを見ていた。妹の眼球にはきっと、互いの存在が世界の全てとでも言いたげに抱き合う二人の姿が映っている。不思議だな、と僕は思った。もしかすると妹が見ている世界のほうが、今ここにいる僕たちの世界よりも真に迫っているんじゃないかとふと思う。
自分なりのリアルが欲しくて、僕は彼女をじかに見つめた。あまりに近いせいで、色の失せた頬や紅の削げたくちびる、摘んで除けてもすぐに落ちかかってくる細い髪のひと筋が、個々に切り取られた存在のように克明に見えた。波打ち際に上がったガラス瓶のような、透明で虚な美しさ。
「それは、僕といるのが、幸福だってこと?」
「そう。今が一番幸せ。こうしてると、嫌なことも全部忘れそうなくらい…」
言ってしまってから、彼女は自分の言葉に怯えたように口を噤む。どうかした? 僕に訊かれると彼女は首を振る。なんでもない、と口では言うけれど、表情がぎこちないのは誤魔化しようもない。
でも、僕はそれ以上は何も問わない。彼女にとって妹を亡くしたことこそが、他でもなく「嫌なこと」に違いないのに。それなのに今、よりによって妹の目の前で、その重要な前提を忘れかけた。自分の中の変化に、きっと誰よりも彼女自身が驚いている。
もうすぐきっと、彼女は本当に僕ひとりのものになる。そのときを想像するだけで、背筋にぞくりと甘い戦慄が走る。でも、今は、まだ早い。妹は見ることに、姉は見られることに、きっとまだ飢えている。合わせ鏡のように際限なく増幅していく眼差しの循環に、第三者である僕が乱暴に割り込むことはできなかった。
今の僕にできるのは、姉の優しい共演者として、妹の眼を歓ばせる恋人を演じてみせることだけ。僕は彼女を引き寄せ、口づける。暖かなニットのコートにそっと手を入れると、長い毛足が手の甲をくすぐる。服の上から彼女の胸を柔らかく掴むと、なだらかな眉がぴくりと震えた。
一連の仕草の間、僕は妹の視線を感じている。それは蜘蛛の糸のようで、見えないけれど、身動きする度にふと、引きつれるような感触が付きまとう。まるで糸に吊られた木偶のパペットだ。僕は笑いそうになるが、それでも隠れて秘密を伝えることくらいはできる。僕は無言で、衣服の下に隠された指先に、そっと力を込めてみる。
二ヶ月後、初めてのクリスマス。僕は彼女を抱くために、山間にある小さなオーベルジュを予約した。我ながら身の丈に合わない贅沢だとは思ったが、妹の存在が、僕にその選択をさせていた。
旅に出る前夜、僕は車のドリンクホルダーを改造して「妹の席」をダッシュボードにしつらえた。ただ見ることしかできない、眼差しだけの妹。今となっては僕は妹に親しみの感情すら抱いていた。美しい姉の姿をひたすら追い求め、その表情に幸福の靄がかかる瞬間だけを記憶の中につないでいこうとするものたち。そういう意味で僕と妹は、性別も、生と死の境目も超えたある種の同志だった。
吹雪いた翌朝の山はよく晴れて、予想以上に美しかった。真白に凍てついた道路は陽光を跳ね返し、光の砂を撒いたように煌めいていた。葉をすっかり落とした樹は白い山肌の上で、エッチングのように細かな枝の造形を晒け出していた。
頭上には灼けたように濃い蒼の空。窓を閉め切った車の中は暖かく、ウィンドガラスだけが外気の張りつめた冷たさを伝えてくる。大きく緩やかな、上りのカーブを過ぎたとき、路上に何かがうずくまっているのが目に入った。動物だ、と思った瞬間、迂闊にも僕はブレーキを踏み込んでいた。
グリップを失ったタイヤが浮き上がり、重力が失われる。水上を滑るような不確かさで車がスピンする。視界が大きく一回転する時間は、歪んだように長く、静かだった。車が止まると、僕は思わず眼を閉じ、深い溜息を吐いた。対向車がなかったのが幸いだった。
「大丈夫? ごめん、怖かっただろ」
彼女は応えない。膝の上で手をぎゅっと握って前を見つめている。視線の先にあるのは、打ち捨てられた動物の骸。
「見なくていい」
僕は「妹の席」を取り外した。両面テープで止めただけの細工は簡単に毀れた。彼女に預けて車を降り、軋む雪を踏みしめてそれに近づく。思った通り、野生のキツネだった。人間に餌をねだろうとして路上に降り、車に撥ねられたのだろう。
不自然にねじ曲がった胴体からして、生きていないのは明らかだった。脇腹のあたりでもつれた毛皮が少しえぐれて、肉が見えている。瞼が薄く開いたままの眼は既に乾き、色がなかった。軽い吐気を堪えながら黙って見下ろしていると、不意に自分の中の弱い部分がその肉隗のように抉られ、露にされたような心地がした。
頭の中で、そうして立ちつくしている少女の姿が浮かんだ。9年前の彼女。こんなふうに、動かなくなった妹の亡骸を見たのだろうか。分身のような存在が一瞬にしてただの物体になり、路上に転がるさまを見ていたのだろうか。そして、足下に届いた小さな眼球。さっきまで同じ世界を、そして何よりも、彼女自身を見つめていた眼。ああそうだ、そんなものが目の前にあったら、見捨てていけるわけがない。
僕は浅く息を吸い込み、コートのポケットに突っ込んでいた革手袋をつけた。素手で触るわけにはいかない、野生のキツネは伝染病の宝庫だ。ゆっくりと腰を屈め、息を止めてその死体を持ち上げた。轢かれて相当時間が経っているのか、手袋越しに熱は伝わってこない。動かない骸を道端の溝に置き、不快な感触ごと捨て去るように革手袋を脱いでその上に放った。素手で雪をすくい、深く埋めてやる。路上に散った血の染みも雪を被せて消した。
作業を終える頃には、手は芯まで凍えて赤く腫れ上がっていた。けれど、そんなものは、どうということもない。刺すような冷たさは死体の感触を忘れさせてくれてむしろ有り難かった。
僕は車に戻る。彼女は少しだけ顔を動かして僕を見た。何も言わなかったが、手にそっと指先を添えてくれた。触れた場所が痺れるように痛んだが、暖かな車内で、すぐに感覚は戻ってきた。
「脅かしてごめんな。あとはゆっくり行こう」
頬はまだ引きつっていたが、敢えて笑ってみせる。ハンドルを握る手に力が戻ったのを確かめて、僕は車をスタートさせた。
車に故障はなく、時間の遅れもほとんどなかった。無言のまま車を走らせ、ようやく辿り着いたのは、輝く雪に包まれた一軒家風の宿。エンジンを止めると全ての音が雪に吸い込まれるように消えてゆく。
最初に僕たちを迎えたのは、よく躾られた物静かな番犬だった。優雅な毛並みを持ったアフガンハウンドで、歩く度にサラブレッドのように身体が上下に揺れた。恭しく膝元に座られて、ようやく彼女の表情が少しだけ和らいだ。
部屋に通されたあと、午後はほとんど別々に行動したようなものだった。同じ建物で、同じ光景を見ていても、心だけはべつべつの思いを追っているように乱れていた。あまりにも手持ち無沙汰だったが、同時に、その時間が必要なものだということもわかっていた。
あまりにすることがなかったので、僕たちはバスルームに湯を張って、順番にゆっくりと入浴した。彼女(と妹)が先で、次が僕。裸で湯に浸かりながら、彼女と、そして妹と出会ってからの数ヶ月のことを思った。
短い間に、僕は自分がとても強くなったような気がしていた。狂気の縁を歩き続けてきたような女と、それ以上に無防備で傷つきやすいひとつの眼球を、自分が守るのだと思っていた。でも、こうして湯の中で膝を丸めていると、自分自身がとても敏感で、弱いもののように思えた。身を覆うものは何もなく、ただ全てを外気にさらしている、あの眼球のような存在。
でも、その感覚は、決して悪いものじゃなかった。手足に絡んだ視線の糸が溶け、柔らかな肌触りの湯の中に滑り落ちていく。それにつれて僕は少しずつ、演じることから解き放たれていった。
ああ、やっとだ、と僕は呟いた。僕たちが温め続けていた物語はようやく柔らかに熟れていた。ナイフなんかなくても容易く皮を剥ける果実のように、噛み砕かなくても舌の上でゆるりと蕩けるショコラのように。もう演技などする必要はない、自然が促すままに振る舞えばいい。その静かな直感を、僕はひとりで、ゆっくりと確かめた。
彼女に血の香りを味わわせたくなかったので、僕は厨房に掛け合って、食事のメニューから肉を抜いてもらった。僕たちのために既に素材を仕入れていたシェフは厭な顔をしたが、道中で遭遇した小事件の話をすると納得してくれた。メインを魚料理に変えたコースは魔法のような鮮やかさと生命力で、内省的になっていた僕たちの心を、外界へ、そしてお互いへと再び開いてくれた。
食事が終わる頃には、冬の夜は、驚くほど速く降りてきた。僕はシェフに心からのお礼を言い、酔っ払った振りをして飲み残しのワインを部屋に持ち帰った。満ち足りた気分でソファに身を預けていると、彼女がするりと僕の脇に滑り込んできた。彼女は重いセーターを脱ぎ、白いキャミソールドレスに薄手のカーディガンだけを着ていた。暖色の明かりを受けて、アルコールを含んだ肌が桃色の熱を持っている。襟元に黒々と彫り込まれた鎖骨の影が美しく、滑らかな窪みに手を差し入れたいと渇くように思った。ああそうか、見ることができないから触れたくなるんだ。僕は意味もなく納得し、温んだグラスを少しすすった。
部屋は静かだった。漆喰の壁にウォルナットの梁が黒く映え、暖炉の炎が揺れるたびに影が微妙に動いた。ゆっくりと視線を降ろすと、サイドテーブルの上の妹と眼が合った。少し青みを帯びた白、そしてジェリイのように柔らかな琥珀色の虹彩。亡くなってから9年が経つというのに、それは今も瑞々しかった。感情があるのかないのか、黒い瞳にただ炎を映して輝いている。
「ねえ、ありがとう」
不意に彼女が僕を見上げて言った。今更感謝される筋合いなんて、と意外に思いながら、僕は問い返した。
「改まって、どうしたのさ」
「今日の、いろんなこと。来る途中のキツネのこととか、食事のこととか。それに……妹のことも。気味悪いって言われても仕方ないのに、こんなに大事にしてくれて」
「そんなの、大したことじゃないよ」
僕は照れ隠しに笑ってみせた。妹にはむしろ感謝していた。妹がいなければ、きっと僕たちはこんなに早く、こうして一緒に旅なんかしていなかっただろう。
「妹の事も、さ。気味悪いなんて思ってないよ。君が大事にしてるものを、一緒に大切にしようとしただけだから」
「優しいのね」
唇は微笑んでいたけれど、声は痛々しかった。何か言いたいのに、言葉にするのが不安でたまらないみたいに、半端に顔を伏せている。やがて、黙っていることに耐えられなくなったのか、そろそろと探るように言葉を引き出した。
「あなたは優しいわ」
「相手が君だから」
少しおどけて言ってみたが効果はなかった。投げかけた言葉は届かずに滑り落ち、彼女はただ首を振るだけだった。
「でも、私は……私は、だめなの」
「どうしてさ」
僕は少し面食らって問い返した。彼女の声はあまりにも痛みに満ちていて、さっきまでの甘い調和の予感からは大きく色合いを変えていた。
「私はだめ。そんなに優しくなれない。あの子だってきっとわかってる。きっと私を憎んでる」
一度話し始めると迷いが解けたのか、彼女は一気に言葉を吐き出した。
「妹のために私の幸せを見せてあげたいなんて、そんなの嘘。本当は、妹に頼ってるのは私のほう。わかってるの。あの子を利用してた。あの子が望んでるから、あの子のためだからって……でも、本当は、全部」
でも、本当は全部、彼女自身の望み。あの子は欲張りだから、全部見たがるから、願いを叶えてあげて。それは彼女が自分の欲望を叶えるための免罪符だ。恋人に抱かれたいのは彼女。ふたりで旅をしたいのも彼女。それを見て妹が喜ぶから、なんていうのは、いつのまにか、うわべだけの口実になっていた。
「あの子、私を憎んでるわ。嫉妬してるかもしれない。自分だけが幸せになって、見せつけてるって……」
でも、それは真実じゃない。だって、妹には感情なんかないんだから。妹が嫉妬していると思うのは、自分だけが抜け駆けしている自覚があるから。見せつけていると思うのは、彼女自身が妹への配慮を忘れかけているから。妹の視線は、すべて鏡の中を覗き込む彼女自身の感情の裏返しだ。
「そうよ。あの子は何も言わない。結局は、私が独りでぐちゃぐちゃ考えてるだけで、何を思っても、何を言っても、全部こっちに跳ね返ってくるの。妹は変わらないわ。いつまでも綺麗なままで、楽しい夢だけを見て、私がずっと傍にいると信じてる。でも、私はあの頃のままじゃいられない。私だけがどんどん変わっていくの」
妹の眼差しは、生きているころと変わらない子供っぽい執拗さで彼女につきまとっていた。先へ行ってもいいけど、決して行き過ぎないで。眼の届かないほど遠くへは行っちゃ駄目。それは彼女の背を押すと同時に足枷にもなっていた。妹さえいなければ、あの視線がなければ自由になれるのに。そう叫びたくても、妹が本当にいなくなってしまってからは、そんな思いを抱くこと自体がタブーになっていた。
彼女は僕を見つめた。黒く深く煌く眼は、初めて妹を締め出して僕だけを見つめていた。
「私を軽蔑する?」
「いいや」
僕は即答した。そんなこと、あるわけない。正直、僕だって、そんな立派な人間じゃないのだから。それは確かに、妹の境遇に同情しなくもなかったけど、本当は君と同じ。君ともっと近づくために妹が必要だった。我ながら狡いと思わなくもなかったけど、それでも君が妹のために僕を愛するのが嬉しくて、妹の存在を積極的に受け入れようとした。
「結局僕だって、自分のことだけ考えてた。でも、もうやめよう。お互い、妹の存在に頼りすぎてた」
僕は彼女を抱きしめた。腕の中で彼女の心が剥き出しになるのを感じた。それはまるで熟れた果実。傷ついてはいるけれど、傷口の中は柔らかく、唇を触れて吸うだけで甘い味が溢れ出してくる。僕はずっとそれを待ちこがれていたのだ。
「…どうすればいいの、私」
「そのまま見せてあげればいい。君が幸福になるのを」
そして、僕はそのまま、ソファの上で彼女を抱いた。彼女が狼狽えても僕は構わなかった。はじめからそうするつもりでいたかのように、心の一部は気持ちいいほど落ち着き払っていた。
妹は相変わらず僕たちを見ていたが、それはもう大きな意味を持っていなかった。妹がいくら見つめても、細胞の中にまで入り込むことはできない。肌と肌が擦れ合う匂いや、口づけの水音、そして粘膜を蕩かすもどかしい熱までは感じ取ることができない。張りつめた肌の下で細波のように繰り広げられていく無限の変化、それを記憶に刻むことができるのは、彼女自身と、そして触れている僕だけだ。
それはとても甘美な体験だった。深く沈み込むと同時に、高い処から見下ろす静かな視線に守られるような。天使の眼差しの下で秘密を持つのは、きっとこんな感じだろう。微笑と同時に涙を運んでくる。どんな顔をしたらいいか解らずに、僕は少し頬を歪めた。最後にはもう、彼女の白い腿しか眼に入らない。彼女は大きく脚を広げ、きつく瞼を閉じて妹を忘れた。僕だけを求め、何度も名前を呼び、そして、静かになった。
終わったあと、彼女はシャワーを浴びにいった。水音を聞きながら、僕は少しぼんやりとして、つるりとした眼球を見つめていた。バスルームへは連れていかなかったんだ、と思うと、むしろ僕自身が覗き見したい欲望に駆られた。お湯に打たれている彼女はきっと、妹にも、僕にも見せない表情をしている。幸福でも不幸でもない、真空の顔。それが誰にも見られずに排水溝へ流れて消えていってしまうことに、切ないほどの儚さと物惜しさを感じた。
僕はふと妹に触れたくなって手を伸ばし、爪を立てないようにそっと摘み上げ、手のひらに載せた。触れるのは初めてだった。それは冷たく濡れて、どこまでも無垢な輝きに満たされている。ああ、と僕は呟いた。君はとても綺麗だ、でも姉さんはもう、そんな眼をしてはいられない。見ただろう? 彼女が僕に抱かれて、君のことを忘れるのを。彼女は大人になる、君の視線を振りほどいて前へ進むんだ。僕の言うこと、わかるかい?
無言で呼びかけると、やがて、眼球から透明な水が滲み出した。それは滑らかな眼球を覆うように溢れ出し、僕の手のひらをあっという間に満たした。涙なのか、愛し合うときの、あの潮のような潤いか。いとおしさに突き動かされて、僕は妹のつややかな表面に口づけた。溢れ出す水は止まらず、手からこぼれて床に落ちた。僕は喉を反らせてその水を飲み干す。それは妹の意志そのもの、身体の中に流れ込んでくる。僕は笑みを浮かべた。わかるよ、今なら伝わってくる、君が何をしてほしいのか。
僕は窓辺に歩み寄り、ウォルナットの艶やかな窓枠を片手で跳ね上げた。窓の外には静かな雪が降っていて、冷気が一瞬で全身を打った。僕はもう一度妹に口づけ、愛していると囁いた。そして腕を振りかぶって、小さな珠を力の限り放った。しんと降り積む雪の中へ。果ての見えない夜の底へ。
振り返ると、彼女がバスタオルを身体に巻いただけの格好で、黙って立ちつくしていた。僕のすることを全て見ていたのかもしれない。非難したいのか喜びたいのか解らないというような、いくつもの感情に引き裂かれた顔をしていた。
僕は一言の謝罪もするつもりはなかった。雪が吹き込まないようにしっかりと窓を閉め、急がず彼女に歩み寄った。こわばった肩に腕を回すと、僕に身体を預けて、彼女は泣き出した。痛みと安堵をそのまま声にしたような嗚咽。彼女はやっと、妹を失ったのだ。妹を意識したシミュレーションではなく、ただ自分の悲しみのために、彼女は止めどなく涙を流した。
僕は彼女を抱きしめ、肩に押し付けられた頭を撫でた。濡れた髪が頭に張り付いて、彼女の頭蓋骨のかたちをくっきりと感じ取ることができた。それはひどく小さくて、その中にふたつの眼球がきちんと収まっていることが奇跡のように思えた。その精緻な奇跡、彼女が生きていることに感謝しながら、僕は彼女の頬を両手で挟み、流れ落ちる涙に口付けた。それは妹と同じ味がした。
僕たちは額が触れ合う距離で、黙ったまま互いを見つめ、何者も介さずに眼の中でしっかりと結び合った。そして、もうひとつの視線の喪失を追いやるように瞼を閉じて、清らかで厳粛なキスをした。
- Profile
 茶石文緒(ちゃいしふみお)
茶石文緒(ちゃいしふみお)- ナイトクラブ
- 最近デジカメが壊れて一眼レフに持ち替えました。レンズのクセの強さが、難しいけど面白い。写真うまくなりたいです。
- Trackback
- Ping 送信 URI: