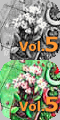- 特集「見る」
- 哲学者からの手紙
- 「書」
- 難しさにこそ、魅力が
- Talk Session
- みることからふれることへ
- 「見る」から「描く」へ
- Novel
- スイッチング・ウォッチング
- 同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
- よくばりな眼
- 秋の夜の夢
- 王子の見た景色
- ちいさなひとひら
- 宣告
- バードウォッチング
- see
- 見る
- Use your eyes
- おしりやぶれたズボン
- アイズ
- 万華鏡の世界
- Coffee Break
- ズレないBookCover
- Series
- メッセージをどうぞ
- おいしい水
- 不愉快なテクスト
- "いろは"の先のCSS
- Player's Side
- from editor
- 次回予告

いつか、心が帰る場所
茶石文緒 きっと誰にも、秘密の場所がある。
実際にそこへ行ったことがあるかどうかはこのさい問題ではない。自分の心の一かけらがひっそりとそこに在り、「本体」の自分を待っているのだと思えるような場所が、きっと誰にもあるはずだ。それがハワイや沖縄だといって住み着いてしまう人もいるし(そういう人はとても幸福な人だと思う)、スペインはアンダルシアだといって譲らない人もいる。けれど、わたしにとっての「その場所」は、残念ながらそんなに華やかな佇まいではない。もう10年も前に写真を撮りに立ち寄った、一棟の、朽ちた廃墟だ。
札幌から車で離れること1時間。もとは介護施設だったというコンクリート造りの建物は、そのとき既にに打ち捨てられて数年が経っていた。ドアを止めたベニヤは先客によって破られていて、わたしたちは比較的容易に忍び込むことができた。
中の荒れようは相当なもの。壁紙は剥がれてコンクリートが剥き出し、階段は朽ちて崩れていた。手すりなどあてになるわけもなく、一段ずつ足下を確かめながら、やっとのことで最上階に登り切ると、いっさいの仕切りがない広い集会室があった。
その空間に足を踏み入れたときの感覚は今でも覚えている。後ろめたさも不気味さも一瞬で消え去り、深い安堵だけが胸に満ちてきた。すべてが持ち去られたあと、古い紐や紙屑、コンクリートの瓦礫だけが散乱するがらんとした広間。そのオブジェの影をくっきりと際立たせるように舐めていく斜めの西陽。それ以外に色と生命の兆しが無いからこそ、光だけが恐ろしいほど際立って美しく見えた。
わたしはその場に立ち止まり、ゆっくりと深く呼吸した。ここで立ち止まってもいい、手に持った荷物を降ろして休んでもいいのだと、目に見えない何かが優しく告げていた。その場にいた同行者の存在も、自分を棘のように引掻き続ける些細な苛立ちや憎しみも忘れた。自分の心が居るべき場所を見つけたのだと思うと、幸福感でほほえみながら、同時に泣きそうになった。
華やかさも、神秘もない。ただ惨めなだけの場所、なのにどうしてこれほどまで魅せられたのか、自分でもわからない。ふと、ここにピアノを置いて弾きたいと思った。調律の狂った古いピアノの蓋を開け、誰にも聴かれない歌を弾く。堅いコンクリートに反響する音は、きっと調子外れで、気が狂うほど美しい。その音色に包まれながらここで死ねたらいいのにと願うほど、その一瞬の感覚は甘く幸福だった。
あれ以来、そこには一度も行っていない。写真を取り出して見返すこともない。けれど、わたしの一部は、きっとまだそこにいる。実体のない幽霊のように、広間を彷徨いながら待っている。わたし自身がいつか戻ってくる時を、その廃墟のように何もかも無くし、崩れ去る一歩前の姿で、ただ身体の抜け殻を横たえにくるだけの時を。逆に言えば、その時が来るまで、わたしはその場所をもう一度訪れる必要はないのだ。あまり深くとらわれてしまっては、きっと自分の破滅を早めるだけ。急ぐ必要はどこにもない、どれだけ遠くへ隔てられても、あの感覚を思い出す間もないような目まぐるしい生活をしていても、あのとき結ばれた絆が断ち切られることは、きっとないのだから。
Keaneの「Somewhere Only We Know」という歌には、不思議なノスタルジイが宿っている。「帰りたい」という切実な感情、しかもこの世のどこにもない、失われた場所だけを指すベクトル。遠くを見ていながら、けっきょくは自分の内面しか見つめていないような、透き通った寂しさ。一歩間違えれば、安っぽいセンチメンタル・バラード。そんなものを好きだと言うのは微妙に気恥ずかしいのだけれど、そのセンチメントに心を浸すために、同じ歌を繰り返し聴いている自分がいる。
ビデオクリップがまたいい。ステージを終えたKeaneのメンバーがタクシーを降り、森の奥に分け入っていく映像。木の葉の落ちた森にはしらじらしく寒い光が射している。じめじめとした落葉を踏みしめる度に、腐葉土の冷たい香気が立ちのぼる。靴を濡らして歩いた先、暗い洞窟の奥で彼等を待っているのは朽ち果てたアップライト。かつての少年の玩具は、今では煤けたように色が失せ、精密なメカニズムも雨風に打たれるまま。まるで崩れかけた廃墟のようだ。
まともに鳴るはずもない古ピアノ、それでも弾かずにいられない。眼を閉じて弾くうちに、足下にひたひたと黒い水が満ちてくる。それはきっと、懐かしいと同時に命取りな、約束の場所のイメージだ。
映像の中のピアノ弾きが夢想する場所。沈んでいくならこんな場所がいいと思っている、彼だけの秘密の場所。本当に訪れるのは最後の瞬間だけでいい。今はざわめきに流されるように、慌ただしい時間を生きるしかない。時が来るまで、ピアノはきっと彼を待っている。
それまでは、ただその場所を、夢のはざまに見つづけて。
- Profile
 茶石文緒(ちゃいしふみお)
茶石文緒(ちゃいしふみお)- ナイトクラブ
- 最近デジカメが壊れて一眼レフに持ち替えました。レンズのクセの強さが、難しいけど面白い。写真うまくなりたいです。
- Trackback
- Ping 送信 URI: