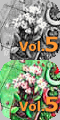- 特集「見る」
- 哲学者からの手紙
- 「書」
- 難しさにこそ、魅力が
- Talk Session
- みることからふれることへ
- 「見る」から「描く」へ
- Novel
- スイッチング・ウォッチング
- 同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
- よくばりな眼
- 秋の夜の夢
- 王子の見た景色
- ちいさなひとひら
- 宣告
- バードウォッチング
- see
- 見る
- Use your eyes
- おしりやぶれたズボン
- アイズ
- 万華鏡の世界
- Coffee Break
- ズレないBookCover
- Series
- メッセージをどうぞ
- おいしい水
- 不愉快なテクスト
- "いろは"の先のCSS
- Player's Side
- from editor
- 次回予告


同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
添野 慎太郎 駅前の喫茶店で冷めた紅茶を啜り、なんともなしになにかを考えていたら、髭面の店長がサービスで洋梨を出してくれて、洋梨というのはよくすべるくせにざらついていて、その歯ざわりがとても久しぶりだったものだから、せつないときを知っていますか? と問われているような気がして、あぁそう言われてみればそれとよく似た肌を知っているな、などと思い耽りそうになっていたのだが、そんなことよりも冷めた紅茶と洋梨じゃ、いくらなんでも店長を小バカにしていると思い、ブレンドを追加注文した。
渋く沈んだ紅茶を飲みほして、そういえばさっきまでなにを想っていたのだろう? と自問自答を繰り返すと、散歩をしながらふらふらとここまで来てしまったことを思い出していたらしい。例えば、すれちがう人々が暑さに顔を歪ませながらも笑って歩いていて、いや、そんなことよりもビルとか公園とか止まれの標識とか学校とか工場とか踏切とかコンビニとか川とか電柱とかの風景であり、それらを眺めつつ、すべてが溢れたはずの気持の中に、まだ澱のようなものが残っていることを思い知らされて、それを認識してしまうと、いまにも巻き込まれそうな焦燥が落ちてきて、ついふらふらと、駅前まで来ていたというぐあいである。
ドミノ倒しでもやろうと思いついたが、手元にはそれを楽しむだけの物体の数がなく、なんで突然ドミノ倒しなど思いついたのかと虚しくなりかけたのだが、去年の冬の真夜中に息の白さを競い合って、その後抱きしめると、ドミノ倒しみたいね、と言われ、全体重を預けられて、そんなことが洋梨のざらつきの感触からよぎり、ドミノまで思考が行き着いたのだと分かり、熱いブレンドを啜ると舌にまとわりつく酸味が懐かしいような温度だったので、その冬の真夜中の場所が神社であり、抱きしめたのは境内へ続く長い階段を昇りきる手前のところであり、君が一段上のところからそう言い、そこで吐く君の白い息は張りつめた大気の冷たさに融けて消えていって、その漂いを追っていると、君の目の前で、ここにいること、がとても不思議なことのように感じて、君と同じ段に昇り、もう一度君を抱きしめたことまで思い出していた。
こういうせつなさを突然ぶち壊す輩がいるんだ、この世の中には……。
「だってさぁ〜、コバヤシがさぁ〜、殴ってくれよってツラしてんだもん、しょうがねぇーよぉー」
「いや、でもコバヤシってけっこういい奴だぜぇ〜、マツダがもっと大人になればセンコーだってさぁ〜、もっとアタマ使わねぇーと、だってソンするだけじゃねぇ〜」
「そりゃ、分かるよ、分かる。だけどさぁ〜、あれっ!? おい、マスダ! ちがうちがう、あっちあっち」
「え?」
「なんかすごくねぇ、あのおっさんの顔」
「うわっ、ほんとだ! 眼が飛んでんじゃん」
「だろ?」
「やべぇ、なんか見てるよ、おい!」
「うぅっわぁっ! マジ、やべぇじゃん、見てる、見てる、見てる!」
どうしようもなくぶっさいくな女のような顔をしてニキビ面の若い男が二人、気色悪く風景の真ん中に陣取り、それまで積み上げてきたイメージを壊して、壊して、壊していき、だからもちろんキレてみようと、そう、最近のワケモノはキレやすいとか、見境ないとかいうから、一応用心して、中指を立てて様子を窺ってみることにし、念のため左手に洋梨が入っていた皿をテーブルの下に潜ませて、もしマツダかマスダがこっちへきたらこの皿でぶったたいて、その後、マツダかマスダがすぐさま加勢にくるだろうから、その時はしょうがない、ブレンドを顔面にぶっかけて、あのワザをかけるしかないだろう、グレートドルフィンラリアート、いやしかし、このワザを出すまでもなく店長が止めに入るだろうし、大丈夫だろう、きっとグレートドルフィンラリアートは温存できる、などと妄想しているふくらみの端から店長がマツダとマスダに、サービスですから、と言い洋梨をテーブルにおいていやがる。
ちょっと、違う気がするな、それは違う気がするよ店長さん、つまり、どうしようもなくぶっさいくな女のような顔の輩に洋梨のサービスはねぇーだろうが、って、でもグレートドルフィンラリアートをお見舞いするその前に、どうしようもなくぶっさいくな女とはどういう女のことを言うのだろう? と店長は冷静に問いかけてくるだろうね、もちろんそれには答えられないから、ドルフィン的に構えた右腕はどうすることも出来ず、そしてその輩に対する洋梨サービスまで許すことにするが、とにかく誰かを殺せ! 状態になってしまった右腕のドルフィン化の処理に困り果て、加えてワケモノがキレてくる気配は一向に感じられず、しかたがなくドルフィン化した右腕で自慰行為をして渦巻いた殺気の沈静化を謀ろうとしたが、窓ガラスの外面に水滴があり、とりあえず乱暴になったドルフィンはそれで静まることができた。
気づくと輩はいなくなっており、窓の外で降りしきる雨の音を感じながら、グレーに染まりつつある街の頭上に、狂気を捨て、再び風景の真ん中をイメージしようと試みた。
繁華街の入り口の雑居ビルが建ち並ぶ隙間に螺旋階段があって、それが何処のビルのものなのかよく分からぬまま昇ってみようとしたら、突拍子もなく君のことがよぎってしまい、想像よりも階段が気味悪く捩れて絡まっていることに気づき、なぜだか無性に、逃げなきゃいけない、と焦り、螺旋階段は昇らずに繁華街へと走り始めたら、急に小雨が降りだしてきて、それでも顔面に雨滴がぶつかるのが心地よくて、それを拭うと侘しさなのかなんなのかわからないものが追いかけてくるようで、ただわかるのは君のことが憎くて、とても憎くて、それでもこれっぽっちの狂気すら生まれてこなかった。
街の解放がオレンジとかエメラルドグリーンとかピンクとかであるなら、空の解放は水色しかなく、それじゃあ、君の解放は何色だったのか? と息を切らせながら呟くと、水溜りに片足を突っ込んでしまい、舌打ちをして止まった。
テーブルの隅に置いてあった占いクジをやってみようとしたが、百円玉がないので二千円札を店長に両替してもらうと、店長が二千円札をどういうふうに両替すればいいか訊ねてきたので、とりあえずブレンドと紅茶の代金を支払えば、九百円くらいのお釣だからそれを貰う、と言うと、彼は、あははは、と意味があるのかないのか分からぬ笑いをしながら、五百円玉一枚と百円玉四枚と十円玉四枚を渡してきて、それで占いマシーンは星座別にコインを入れるところがあり、乙女座なのに間違えて蠍座のところに百円を入れてしまって、畜生、君が蠍座だったから間違えたんだ、と頭を抱えて蹲っていると、大丈夫だよ、それね、何処の星座に入れてもクジが出てくる順番は決められているから、と店長が宥めてくれて、んじゃ別にこんな穴を意味ありげに十二個も作るなよ! とキレながらクジを広げると、大吉、なのに、待ち人現れず、でまた頭を抱えて蹲った。
鮫肌だからね、?を合わせるのに抵抗があるのよ、ほら、こことか、このへんとか、ざらっとしてるでしょ? でもね、こうして触られるのってけっこう好きだったりして、矛盾してる? 指ではよく滑るのよ、でも?を重ねるとざらついてるでしょ? 温度が、ほら、温度のあいだに一枚、藁半紙があるみたい。
こういうもどかしさを突然打ち破ってくる女郎がいるんだ、この世の中には……。
「鼻毛をね、鼻毛を抜いたの、こないだ」
「えー、でもそれがどうしたの?」
「ちがうの、手でね、手で引っこ抜いたの」
「やだぁ、まじでぇ、やっぱ痛いの?」
「またぁ、ミサも抜いたことあるでしょう」
「ないよ、ない、ない! 手でなんか、ないよ!」
「あたし、タバコ吸うからかなぁ〜、超、伸びるの速いよ」
「ふーん、よくわかんないけど、それで?」
「あっ、それでね、鼻毛ってさ、切るとこんなんじゃん? ちり紙とかにこのくらいしかないでしょ? でもさー、抜くとぉ〜、かなり長くてぇ〜、なんつーか、氷山の一角? って言うの? まじで」
「ミキってバカ」
「それでね、それでね、もっと楽しいこと発見したの! 例えば、左の鼻毛を手で引っこ抜くとするでしょ? そうすると左目だけから涙が出てくるのね、そんで、右を抜くと右目だけから涙出てくるの! 超面白くない?」
「おもろい、すごいおもろい」
「でしょー」
「あれ? ミキなんか、ほら、あっちあっち」
「え?」
「なんかやばくない?」
「あ! 見てるぅ〜」
「でしょ? 見てるよねぇー、絶対見てるよねぇー、キモくない?」
「見てる、見てる、見てる! うわっ! 抜いてる? 鼻毛抜いてるよ!」
「やだ、まじで? ぬわっ! ほんとに抜いてる! キモ! これ飲んだら帰る?」
「うん、でよ、出よ! 飲んだら即行、出よ!」
ミキだろうがミサだろうが、今すぐグレートドルフィンラリアートを顎下にぶち込んで、白目出して口から泡吹いて倒れたところにこの抜いた鼻毛をパラパラかけて、ガハハハ、と仁王立ちしてやることにしよう。だが、そんな仁王立ちの瞬間に、ドルフィンを喰らっていないミキだがミサだがが、店の電話から、いやケイタイで、何処かの誰かに悲鳴の電話をするだろう、そうなったらしょうがない、もう一度だけ鼻毛を抜き、それを握った手のままグレートドルフィンラリアートをお見舞いするしかない、などと、どんどん膨らむ棉飴のような世界で、左目から涙を流していると、綿飴の糸の先端から店長が現れて、サービスの洋梨をミキとミサのテーブルに運んでいやがる。
ふぅー、またか、またおまえか、それでも堂堂巡りの世の中だからしょうがないっていうことにしたはいいが、熱く火照ってドルフィン化した右腕のやり場が見つけられず、もう雨は慰めてはくれず、しかたなく店を出ることにし、金を払おうとすると、あっ、御代は先程いただきましたよ、って、店長は憐れむような眼をしやがって、それでそんな眼をした後で、自慢の髭をさすっていたりするので、ふてくされ無言で店を出ると、雨が強くなっており、傘立てにミキとミサのと思われる傘が二本あって、どちらか一本を盗って帰ろうとしたが、二本のうちの一本を盗ることが、ミキとミサにとってつまらぬ効果をもたらしそうな気がして、二本とも折ってやり、そのまま濡れて帰ることにした。
びしょ濡れになって部屋に戻り、もちろん君がいなくなってしまったから、誰もいないのは分かっていても、ただいま、とかほざいて薄ら笑いを浮かべたりして、玄関の鏡にそんな顔をした自身が在り、そのツラにドルフィンしたくなる。
カーテンを閉めぬままソファに身を投げ出し、しばらく放心していたが、なにかの拍子にふと、起き上がり窓ガラスを見れば、外はただ黒くて、口紅、アイライン、ペディキュア、メンソール、携帯、浮かんでくるものたちの匂いと夜とのコントラスト。
きっとそうだろう、
同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま。
- Profile
 添野慎太郎(そえのしんたろう)
添野慎太郎(そえのしんたろう)- WRITING-HIGH
- イメージを見る。それは、誰かに、見られている、ということ。
- Trackback
- Ping 送信 URI: