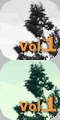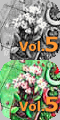- 特集「見る」
- 哲学者からの手紙
- 「書」
- 難しさにこそ、魅力が
- Talk Session
- みることからふれることへ
- 「見る」から「描く」へ
- Novel
- スイッチング・ウォッチング
- 同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
- よくばりな眼
- 秋の夜の夢
- 王子の見た景色
- ちいさなひとひら
- 宣告
- バードウォッチング
- see
- 見る
- Use your eyes
- おしりやぶれたズボン
- アイズ
- 万華鏡の世界
- Coffee Break
- ズレないBookCover
- Series
- メッセージをどうぞ
- おいしい水
- 不愉快なテクスト
- "いろは"の先のCSS
- Player's Side
- from editor
- 次回予告
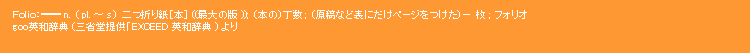

王子の見た景色
オカヤマ 常経国の王子・遮照が邪眼の持ち主と見なされた理由は、ひとえにその異常な生い立ちに起因している。母君の胎から取り出されたとき、すでに瞼が開いていたのである。
まだ産声を揚げぬうちから炯々と見開かれ、まっすぐこちらを見つめる視線を受けて、王子を取り上げた産婆は気が動転し、息を詰まらせ死んでしまった。そこで母君は自ら産褥の疲労をおして産湯を使わせ、産声を揚げさせようと尻を叩いたり強く揺すってみたものの、赤子は口をきっと結んだまま、黒曜石のような瞳で我が母を見つめていたという。その母君も翌日高熱を出し、しばらくせぬうちに身罷った。
この凶事に慌てふためき、いかなることかと問う王に、魔術師の返した答えがその後の王子の運命を決定づけた。
「邪眼でございましょうな」
誰彼の区別なく、凝視すれば死に至らしめ、一瞥するだけで禍をもたらすという邪眼。生まれたばかりの王子はこの危険な視線の持ち主なのだろう、そう魔術師は言った。
かように物騒な瞳は潰してしまうべきか、いやいっそのこと王子を殺した方が良いのではないか。問いを重ねる王に、しかし魔術師は首を横に振る。星がそれを許さないのだ、と。
王家に赤子が誕生するとその星の行方を占うのは宮廷の習わしだった。その占いによれば、このたび生まれた王子は尋常ならぬ才の持ち主であり、その特異な才によって常経国は末永く栄華を保つという結果が出たのである。
おそらく王子の才とはこの邪眼に関係があるのではないか、そう答える魔術師に、ただでさえ迷信深い性格であった王は赤子を生かしておくことに決めた。確かに邪眼は世にも稀な力である。そのことは否定できない事実だった。
しかしこのまま邪眼を放置するのはあまりにも危険である。そこで王は生まれたばかりの王子から視線を奪った。邪を払う紅い絹にまじないを施し、二つの瞳を刺繍した目隠しで王子の目を覆ったのである。固く結び目を作り、錠前を差し込み、鍵なしでは目隠しを外せないようにしたうえで、名前も「遮照」とした。
生まれて間もないうちに視力を奪われた遮照王子は盲人として育てられ、盲人として成長した。奪われた視覚を補うべく、他の感覚は人並み以上の発達を見せた。王子は幼いうちから音曲に才能を発揮し、笛を吹かせれば楽士が蒼褪めるほどの腕前となった。また極度に研ぎ澄まされた指先の神経は、ほんのわずかな起伏も見逃さず、本物そっくりの彫刻を生み出すのである。
だがしかし王子は決して盲人ではない。紅い目隠しを透かして陽の移ろいを知覚できたし、目の前を誰かが通り過ぎたとき、耳に頼らずとも立ち止まれた。昼夜を問わず監視するお付きの者の目を盗み、こっそり目隠しをずらしてみれば、鼻骨との隙間に生じた視野は、狭いながらも実に鮮やかで美しいものだった。
他のことではわがままひとつ言わない遮照王子が、こと靴に関しては贅沢を言い、日に何度も取り替えるのを見て、余人は訝しく思っていたのだが、何のことはない。王子にとって視界とは、ほんの小さな隙間から見える自分の足元だけなのだ。そのわずかな世界の彩りを、王子は大切に慈しんでいたのである。
王子の世界は穏やかだった。異腹の兄弟たちは王太子の座を巡って暗闘し、その閨閥をも巻き込んで陰険な宮廷闘争に明け暮れていたが、鬼子として育てられた遮照王子に肩入れする者など誰もいなかった。そもそも遮照王子の母は身分の低い女性であったため、強引に太子に推そうとする声もなく、王子が頼るべき実力者もいない。遮照王子は毎日笛を吹き、粘土をいじり、ときおり目隠しをずらしては、鮮やかな色彩の靴に目を遣るだけの暮らしぶりだった。
だが遮照王子が十五の年、常経国を危難が見舞った。西の大国・槙堵が隣国を併呑し、遠征の勢いをかって常経国に侵攻する構えを見せたのである。
槙堵国の特使がもたらした降伏勧告の書状は宮廷を震撼させた。
闘わずして降るのは恥だと拳を振り上げる者。闘ったところで到底勝ち目はない、ならば属国として従い国家の安泰を計るべきだと諭す者。いやまずは一戦交え、常経国侮りがたしの印象を植え付けてから和睦すべきと申す者。いろいろ議論紛糾し、一向に方針が定まらない。そうするうちにも返答の期日が迫り、否が応にも結論しなければならなくなった。
書状によれば常経王自ら、国境地帯に陣を張る槙堵王・瀝霜のもとを訪れ、返答しろとのことである。この言い種自体がすでに常経国を侮ったものであり、王は屈辱のあまり顔が紫色に変わったが、しかし無視すればそれこそ亡国の危機。何としたら良いものかと考えあぐねているときに、ふと遮照王子のことを思い出したのである。
王子の邪眼をもってすれば、槙堵王の命を奪えるかも知れぬ。国王が死ねば遠征軍も撤退せざるを得ないであろうし、上手くすれば槙堵国の相続争いで、常経国のことなどに構っていられなくなるのではないだろうか――。
過日、魔術師の残した予言が鮮やかに甦る。遮照王子の才によって常経国の栄華は保たれる、そう予言は告げていたのだ。思い出し、王は確信する。邪眼の鬼子はこの日のために生まれてきたのだ。物静かな刺客として生を受け、徒手空拳の暗殺者として今日まで育てられてきたのだ、と。
返答期限の日、早朝。遮照王子は輿に載せられ、背後からそっと目隠しを外された。長年にわたって彼を監視してきたお付きの声が言う。
「決して顔を上げてはなりません。歩くときも常に下を向くように。視線を上げるのはただ一度、憎き侵略者の前に立ったときだけです。そのときがきたらじっと瞳を見つめるのです。かの男の死を願うのです。それが我が国を救う唯一の手段、王子が生まれてきた理由なのです」
王子はその言葉を上の空で聞いていた。四方を囲まれた輿の中、そんな場所でさえ世界は明るく鮮やかなのだ。驚きをもって我が手を見つめる。何度も粘土で形作った人間の手。だがこんなにも玄妙な造作をしているとはいまだかつて知らなかった。
王子を載せた輿が担がれる。王のあとに続いて国境地帯へ進発する。言いつけ通り、王子は決して顔を上げなかった。窓も開けず、頭も回さず、じっと自分の掌を眺めている。たかが掌ひとつをとってみても色彩は様々、変化も様々。握り、開けば動くのは指だけではない。それに付随し手の甲にはしる筋、骨、血管も奇妙な変化を現す。実に世界は美しいものだ。
陽が高く昇り、やがて傾き、斜めに差して、ようやく一行は国境地帯へ辿り着く。輿から降りる王子。顔を上げずとも周囲の物音から、大勢の兵士たちが整列していることが聞き取れる。
呼ばれ、槙堵王・瀝霜のもとへ歩みを進める父。その踵を追って王子も進む。黄昏の陽射しに染められた地面は朱色であり、黄金色であり、どこか緑の色も差す。細長く引き延ばされた父の影は黒ではなく深い藍色だ。靴の刺繍糸でしか色を知らない王子にとって、変化に富んだ黄昏の光は眩暈がするほどだった。
今日という日のことを決して忘れまい、王子は誓った。宮廷に戻ればまた光を奪われる。目を封じられ、景色を失い、自分の足元を垣間見るだけの日々に戻る。だからこそ今日目にした色の重なり、混ざり合いを、自分は死ぬまで忘れない。この奇跡のように美しい世界を――。
「常経国王子・遮照どの、おもてを上げられよ」
言われて我に返る。そうだ、自分は暗殺者として出向いたのだ。邪眼。ひと睨みで生命を奪う悪魔の視線。
本当に自分の視線が禍を招くのだろうか。王子にそんな自覚はない。物心ついたときからそう言われ、皆から恐れられていたために、いつしかそういうものだと納得していたが、一度たりとて邪眼で人を殺したという記憶はない。赤子の頃、母と産婆を睨み殺したという罪深い話を聞き、恐れ、否定してきた自分の視線。だが殺した憶えなどこれっぽっちもないのだ。
「――遮照王子」
「はっ」
意を決して顔を上げる王子。睨み殺せる自信などない。しかしやらねばならぬ。国のために、目の前の侵略者を呪殺せねばならないのだ。
槙堵王・瀝霜は威風堂々たる男だった。感覚的に「重い」男だった。今まで指でなぞるばかりで、この目で人の顔など見たことのない遮照だが、ひとめ見るだけでこの男は偉大であり、剛直であり、人に優れた資質を持つ人間だと確信させるものがあった。世界は美しいばかりではない。力強く、そして大胆でもあると王子は知った。
「このたびは大王様のお越し、我ら常経国一同、謹んでお待ち申し上げておりました――」
言いつつ、無礼は承知で瀝霜の瞳を射竦める王子。一瞬たりとも視線を外さず、しかしよどみない口調で、異国の王を歓迎する旨を告げ、王の支配を喜んで受け容れると述べる。
従属国の王子が向ける挑戦的な視線を受け、しかし槙堵王・瀝霜は眉ひとつ動かさない。怒るでもなく、鼻白むわけでもなく、じっとその視線を受け止め、黙って口上を聞いている。むしろ睨みつける遮照王子の方が汗ばみ、息が詰まり、頭痛がしてきた。
ようやく王子の口上が終わる。だが邪眼の効果は一向に現れない。それどころか何を勘違いしたのか瀝霜は愉快に笑い、侵略者を真っ向から見据える王子の大胆さに賛辞を示したほどであった。
困惑を押し隠し、一礼して下がる王子。わけがわからなかった。どういうわけか全く、邪眼の効果はなかったのだ。
長年にわたり目を塞がれ、いつしか呪力を失ったのか。いや、そもそも邪眼など存在するのだろうか。魔術師の言葉を真に受けた父の誤解なのではないか。全ては不幸な偶然と、それに便乗する迷信から生じた勘違いなのではないだろうか――。
そんな疑問が次々に沸き上がる。
そしていまさらながらに気付く。王子はいまだかつて一度も父の顔を見たことがなかった。十五年にわたって彼の光を奪い続けた父。そしてこのたび侵略者の命を奪うべく、一時的に光を貸し与えた常経国の王。果たして父はどんな男なのだろうか。王たるからにはやはり槙堵王・瀝霜のように、周囲を圧倒する存在感を宿した男なのだろうか。
――見てみたい。
心にきざした誘惑を何とかして抑えつけようとする。邪眼はひとめで禍を招く。子供の頃より擦り込まれてきた戒めの言葉。しかし邪眼の効果などありはしないことを、たった今、王子は経験したばかりだった。
そっと視線を横へ遣る。
運悪く、こちらを窺っていた父・常経王と視線がぶつかった。
最初、常経王は何が起こったのか理解していない様子だった。全身に疲労をまとった中年男は二、三度素早く瞬きする。
だが瞬後、落ち窪んだ瞳が大きく見開かれ、心労にえぐられた頬が硬直する。
ひゅぅう、と大きく息が吸い込まれる音が聞こえた。
「――馬鹿者、見るなっ」
叫ぶまもなく蒼褪める額。苦しげに心臓を押さえ、窮屈に身体を折り曲げ、喉で息をする常経王。
「胸が、胸がくる……」
言葉が途切れ、ぜいぜいと喘ぎ、血の気の引いた顔色が、すぐに真っ赤に腫れ上がる。
やがて目を剥き、泡を吹き、常経王は息絶えた。
騒然とする陣幕。さすがの瀝霜も椅子から腰を上げ、急な変事に立ち竦んでいる。だがもっとも困惑していたのは遮照王子その人であった。
――どうして?
邪眼は効かぬはずだった。なのに一瞬目が合っただけで父は死んだ。ならば邪眼は効くはずだ。なのに異国の王は、じっくり睨みつけられたにもかかわらず、実に快活にその視線を受け止めていた。
「暗殺だ」誰かが叫ぶ。
「毒を盛られた」何者かが騒ぐ。
あちこちで両国の兵士が争い始め、陣幕の内は大変な混乱となった。怒号が飛び交い、剣を打ち合う音がする。ぼんやりしている場合ではなかった。王子はその場を逃げ出した。
入り乱れる兵士。暴れる者、取り押さえる者、落ち着けと触れを回す者。大勢の者が一斉に、てんでばらばらに動き回っていた。慣れない王子が目を開けていては彼らの動きに幻惑されるばかりだった。王子は視線を足元に落とし、自分の靴だけ見つめて駆けた。
突然に王を失い、常経国は混迷の極みに陥った。王を失ったばかりが原因ではない。まだ後継者たる王太子を決めていなかったのだ。
五指に余る王子たちが、我こそはと王座を主張し、それぞれを支援する貴族、豪族たちが互いに牽制し合い、争いは容易なことでは終息しそうにもなかった。ついに槙堵王・瀝霜が強権を発動し、ひとまず王位は長兄が継ぐこととなったが、不満を抱くその他の王子たちは、ならば次の太子の座を奪い合うという有り様だった。
その中で遮照王子だけは例外だった。王の死が彼の邪眼によるものと知れ、彼は国を追放されたのである。邪眼によって母を殺し、そしてこのたび父をも死に追いやった罪は重い。死罪にすべしとの声もあったが、迷信深い常経国の廷臣はいまだにあの予言を憶えていた。それに加えて遮照王子は政治的影響力も皆無、ならば殺すまでもないと放逐に決まったのである。
遮照王子は輿に揺られ、槙堵国との境まで運ばれた。持ち物といえば一袋の砂金と愛用の笛だけ。供回りは誰もいない。
輿から下ろされ、目隠しを外される。これは大臣の言いつけだった。どうせ異国に放逐するなら、せいぜい邪眼の禍を振りまいてこいとの考えだった。
陽が落ちるまで真っ直ぐ進め、決して振り返ってはならないと言われ、邪眼の王子はおとなしく従った。目の前に広がる原野の奥行きは、遠近感に慣れない王子を不安にさせ、慣れるに従って魅了した。
全てを失った代償として、王子は光を取り戻した。故郷を追われた悲しみに暮れる一方で、しかし王子は黄金の太陽に心を奪われ、白銀の月に陶然とする。
だが飛び跳ねる瞬間の野ウサギの脚、雨露に濡れたスミレの含羞、きらめく小川に身を翻すしなやかな魚の尾、どれもが一瞬現れ、瞬きをしたあとには消えてしまうものだった。いまさらながらに知ったこの事実を王子はひどく悔やみ、何とかしてこれを留めておきたいと強く願った。
――またいつ光を失うとも限らない。だから今のうちに光に満ちた世界を留めておこう。
なかば脅迫的な思いに駆られ、王子は絵を描き始めた。道具などない。焼け残った炭を用い、割れた皿や平たい石に、人の絵、花の絵、獣の絵を描くだけだ。だがその簡素な手法で描かれたものですら、目のある者に王子の画才は隠しようもなく、やがて物好きな商人の宅に招かれ、そこで初めて彼は絵筆と顔料の存在を知った。
王子の画風は類を見ないものだった。そっくりに描くというだけではない。実に見事に万象の内実を描き出し、見る者に生々しい既視感を与えるのだ。王子の絵は目に頼って描かれたものではない。盲人として過ごした時代に否応なく鍛えられた触覚が平面の絵に起伏を与え、研ぎ澄まされた聴覚が目に見えない音や風までも捉えるのである。
やがて王子は遮照の名を捨て、自ら号して「恵照」と名乗った。流浪の絵師・恵照は旅先で一宿一飯を乞い、その代償として絵を描く。興が乗れば戯れに笛など吹き、やんやの喝采を浴びるのも楽しいひとときだった。
乞われれば東へ、気紛れに西へ。どこにでも気軽に恵照は旅をした。どんなに退屈な土地でも、何かしら描くに足るものを発見し、そのたびに次はどこへ行こうかと心が騒ぐ。
だがどうしても故郷へ足を運ぶのは躊躇われた。
あれから十余年、常経国は地上から消えていた。再三にわたる内紛に業を煮やした槙堵王・瀝霜はとうとう常経国に代官を派遣、直轄地にしてしまったのである。つまりもはや誰憚ることなく、恵照は郷里に戻ることができたのだが、それでも彼は二の足を踏んでいた。
異国で暮らす十数年、彼の邪眼は一度として禍を引き起こさなかった。その事実について、彼はひとつの推論を得ていた。彼の邪眼は常経国の人間にしか効果がないのではないか、と。だからこそ槙堵王は無事であり、父・常経王は死んだ。そしてその仮説に基づいてみると、やはり常経の地に行けば、またいらぬ禍を引き起こす危険があるのだった。
だが恵照三十一歳のある日。旅宿で知り合った行商人が常経の出身だと聞いて彼の心は激しく揺らいだ。もはや常経の人間にすら邪眼は通用しないのだ。そう思うと望郷の念は抑えがたく、とうとう彼は故郷へ旅立った。
初めて目の当たりにする故郷は想像以上に美しかった。どこにでもある田園地帯、さほど豪奢でもないかつての宮殿、がやがやと猥雑な市場、しかしその全てが美しい。古くに馴染んだ訛り言葉、香辛料を利かせた料理、乾燥した風を掴めば指先でさらさらと空気がほぐれる。
何も変わらず、しかし見るもの全てが初めての故郷に立ち竦み、恵照は懐かしさに涙が滲む。槙堵国の支配を受け、しかし故郷は変わらない。そこに人が住む限り、たとえ名前は変わっても、依然ここは常経国なのだ。
常経で過ごす初めての夜。恵照は酒場の隅から聞き覚えのある声に耳を傾ける。酔漢の濁声をかいくぐってみれば、ぼそぼそと独り言を呟く初老の男がいた。恵照は不案内な旅人を装って近付き、この土地のことを尋ねるふりをする。
酒を奢り、話を聞くうちにようやくその声音を思い出した。過ぎ去りし少年時代、常に背後から聞こえてきた声だったのだ。
「こう見えてもわしは昔、王子のお目付役をやっていたのだよ」
そう自慢げに語る老人は恵照の正体にまるで気付いていない。酔いのせいではない。老いのせいでもない。邪眼の王子・遮照とは、常に紅い目隠しをした異形の少年だった。その印象が強すぎて、よもや目の前の男が本人であるとは思いも寄らないのだ。
酔いに任せて老人の口は軽くなり、しきりと往時を回顧し、現在の有り様を嘆く。槙堵王・瀝霜の支配は緩やかで、支配者としては申し分がないことは老人も認めるにやぶさかではない。
「だがね、旅の人。やはり自分の住むところは自分らでやっていきたいと思うのは人情じゃないかね」
知らぬうちに杯を重ね、完全に出来上がった老人は酔眼を真正面から向けてくる。
「しかしまだ希望はある。今にきっと追放された王子が戻ってくる。そういう予言があるのだよ、この国には。そしていつの日か王子の手によって常経国は復興されるはずだ」
昂奮した口振りに狂信的な熱が宿っていた。
「何しろ遮照王子は普通の人間ではない。邪眼の持ち主だからな。たとえ仇なす者がいたとしてもひと睨みだ。嘘じゃないぞ、本当のことだ」
言いつつ、それが邪眼と気付きもせずに、老人は恵照の瞳を睨みつける。もちろん何も起こらない。起こるはずがないのだ。
「――そうですか」
枯れた思いが口から漏れる。
邪眼の呪力はすでに失われたのか。いや、そもそも邪眼などはじめからなかったのか。
もとより恵照に判るはずもなく、ただ視線を逸らすのみだった。
恵照はその後二十数年にわたって各地を遍歴し、行く先々の風景を絵に残した。時を追うごとに彼の名声も上がり、当代随一の画家と誰もが目すようになったが、しかし彼は旅をやめなかった。そしてある冬の日、旅先に投宿した富豪の家で、風邪をこじらせた恵照は呆気なく死んだ。遺族はなく、遺言もなく、ただ膨大な量の絵画が各地の愛好家に残されたのみだった。
恵照の死から数年後、槙堵王・瀝霜も崩御した。死後、例に漏れずお家騒動が勃発し、槙堵国は急速に衰退した。その弱り目を狙って北方の異民族が侵攻し、瀝霜の死から二十年も経たずして槙堵国は滅亡した。
異民族は新たな王朝を樹立するにあたって、前時代の影を一掃した。懐古の情が民族意識を再燃させ、反乱を生む萌芽となり得ると考えたのだ。法制を改め、習俗を強要し、人々の暮らしも変化を強いられた。二世代もすればかつての暮らしぶりは影を潜め、都市の景色も様変わりした。
しかし絵師・恵照の残した絵画は偉大な芸術品として美術を愛する者に秘蔵された。代々受け継がれ、あるいは人に譲られ、時代が降るにつれて顔料の鮮やかさは失われたが、しかし恵照の手による確固たる描線は、数世代の時を経てもなお、見る者に生々しい既視感を抱かせずにはいられない。
およそ目に映るもの全てに関心を持った恵照だが、彼が最も好んだ画題は故郷の風景である。現存する作品数、実に七十四点。戦火によって失われたことを考えれば、いかに彼が故郷の景色を愛したか容易に想像できる。
現在、恵照の作品は世界中の美術館に展示されており、その多くは常経国の風物である。
それを初めて見る者は、常経国という聞き覚えのない地名に首を傾げる。だがしばし見つめるそのうちに、あたかも自分がその国を訪れたことがあるかのような錯覚を抱く。再びその絵を見る者は、瞼を閉じても在りし日の常経国を思い浮かべるようになる。三度その絵を目にした者は、歴史学者でもなければ知ることのない、この小さな王国に懐かしい感情を抱くに至る。
かくして王子の画才によって、常経国の繁栄は末永く画布の上に留められた。地図にその痕跡すら残さない亡国ではあるが、しかし数百年の時を超えて、今もなお常経国は活き活きと命脈を保っている。
了
- Profile
 オカヤマ(おかやま)
オカヤマ(おかやま)- 20%off
- 台風で避難勧告の電話がかかってきましたが、シカトぶっこいて家で寝てました 。これじゃ死んでも文句言えないわな。
- Trackback
- Ping 送信 URI: