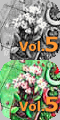- 特集「見る」
- 哲学者からの手紙
- 「書」
- 難しさにこそ、魅力が
- Talk Session
- みることからふれることへ
- 「見る」から「描く」へ
- Novel
- スイッチング・ウォッチング
- 同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
- よくばりな眼
- 秋の夜の夢
- 王子の見た景色
- ちいさなひとひら
- 宣告
- バードウォッチング
- see
- 見る
- Use your eyes
- おしりやぶれたズボン
- アイズ
- 万華鏡の世界
- Coffee Break
- ズレないBookCover
- Series
- メッセージをどうぞ
- おいしい水
- 不愉快なテクスト
- "いろは"の先のCSS
- Player's Side
- from editor
- 次回予告


秋の夜の夢
ハシモト ――夢をみている。
公園に一人、なにをするでもなくブランコに座っていた。燃えるように赤くたぎった夕焼けが、世界を薔薇色に塗り替えていく。子供たちを呼ぶ母親の声が聞こえはじめると、ひとり、またひとりと砂場で遊んでいた小さな影が少なくなった。
やがて藍色の薄い闇が訪れると、落ち着きを取り戻した空に冷たい月が輝きはじめ、公園の街灯に灯りがともった。風が死んだ春の宵闇に身を震わせて、ブランコから立ち上がると、溜息が自然とこぼれ出た。辺りに人影はない。砂場に忘れられたスコップやじょうろ、それと作りかけの砂の城ばかりが、月光に照らされて、細い陰を投げている。
公園には誰もいない。今日もこなかった。
もう慣れた。期待しているわけじゃない。
自分自身の惨めに言い訳し、家に帰るために足を踏み出した。日課だ。毎日毎日、いつもこの公園で、こうして夜を待っている。
もう、夢見ることさえ諦めたというのに。
朝がやってきたことを知らせた目覚ましを殴りつけるようにとめてから、俺は寝起きの頭をかきむしった。失敗したのだ。今日と明日はバイトがないのだから、何も早起きをする必要なんかない。
大学にも行かず、定職にもついていない二十歳前の男の特権といえば、二度寝くらいのものだろうと、もう一度枕に顔をうずめたとき、やけに気分の悪い夢を見たことを思い出した。
顔を上げると、カーテンの隙間から差し込んだ光が眩しかった。何がそんなに嬉しいのか、燦々と輝く太陽は秋になっても休むということを知らないらしい。
「公園か」
もちろん、夕方の公園で寂しく夜を待っていた記憶など欠片もない。そんなセンチメンタルな願望を抱いたこともない。とすれば、あれは俺の夢ではなく、助けを求める誰かのSOSだ。
「誰だよまったく。俺とシンクロする霊なんか滅多にいないってのに」
事実、この十年間、肉親や同居人以外とシンクロしたことは一度もない。
「よっぽど相性が良いのか」
そうなると、俺はよっぽど運が悪い。
夢に出てきたのは、見覚えのある公園ではあった。馬鹿母親の昔の住処だったこの街に越してきてから三ヶ月、一度も訪れたことはなかったが、外観から想像するに、駅への道すがら通るあの公園だろう。訪れたことがないのだから、まだ見ていない霊が棲み家にしていても、たしかにおかしくはない。
無視して寝ることもできたが、さすがにこのままでは目覚めが悪い。食パンだけの食事とシャワーを十三分で済ませて、行きたくもない公園へと足を向けることにした。
扉を開けると、外は馬鹿じゃないのかと意味もなく悪態をつきたくなるほど晴れていた。ボロアパートの鉄扉は開け閉めするたびに耳障りな音を立てる。ボロアパートだから仕方ない。料金を払っていてもたまにガスが止まる。停電はくしゃみと同じ割合で起こる。水道が連続一週間出続ければ、その週のうお座は間違いなく運勢一位だろう。
おまけに幽霊が出るとの噂つきなので、八部屋あるアパートは半数以上が空室だ。静かこの上ない。しかし廊下の電気は当然のようにつかないので、夜は足元に注意が必要だ。
それら全てをひっくるめても、風呂トイレ付きで月二万円の家賃はいまどき破壊力のありすぎる魅力だった。たしかにこれで、幽霊さえ出なければ満室になったかもしれない。
誰だか知らないが、幽霊が出るなんていう噂を最初に流した奴は、なかなか見る目がある。
「どうした、早く行かないのか?」
「うるせえ。死人が朝から喋るな」
後ろからかけられた同居人の言葉に悪態をつく。幸い俺には幽霊が見えるので、別にポルターガイストごときを怖がる必要はない。本当ならこんな、中学時代に失恋した程度の未練で自縛霊になったできそこないはさっさと成仏させてしまってもいいのだが、防犯面に役立つのでしばらく使ってやることにした。
だいいち、未練を残した奴を成仏させるのは骨だ。そんなめんどうなことはしたくない。ふつうは自分が死人だってことにさえ気付かせてやれば勝手に消えてくれるものなのだが、この馬鹿はよっぽどこの世が好きらしい。
「君、年上に向かってその口の聞き方はどうだろう」
「中坊のナリして何言ってんだ。女にふられた程度で自殺した馬鹿に説教されるいわれはねえ」
「ふられたんじゃない。失恋と、自己嫌悪」
「違いも、意味も分からん」
「人を一人見殺しにした。その責任感さ」
「結局わからん。夜には帰る。じゃあな、成仏しろよ」
「いやだね」
振り返らずに手を振って階段を降りた。朝になると幽霊が消えるなんて誰が決めた。奴らには昼夜の区別なんかあるわけがない。年も取らなければ眠りもしない。完全無欠のできそこないどもこそが、幽霊だ。
公園は親子連れで賑わっていた。無職のプータローに向けられる世間の目は厳しい。
「あのブランコか」
残念ながら、夢で見たブランコは鼻水をたらしそうなクソガキによって占領されていた。蹴り飛ばして散らしても良いのだが、子煩悩の馬鹿親に通報されるのは困る。だからガキは嫌いだ。ガキと、声のでかい中年親父と、電車の中で図々しいババアと、幽霊ほど世界でうっとうしいものはない。
「夕方にでもまた来てみるか」
夢で見たのは夕方の光景だったから、それでも用は足りるだろう。踵を返すと、はて公園前の通りに、夢では見覚えのない信号があった。
信号が新たにつけられる理由なんて限りがある。子供の通学路になったか、道路工事の関係で車の通りが増えたか、そこで交通事故があったかだ。
「ここで死んだかな」
たぶん、間違いはないだろう。そうすると、死んだ年代も特定できそうだったので、目的地を駅前の交番に変更した。
「あー、そんなの分からないね」
態度の悪い中年の警官は、どことなくエスパー伊藤に似ていた。
「調べてもらえませんかね?」
「え、調べるの?」
「はい、どうしても必要なことで、ダメですかね。なんとかお願いしたいんですけど」
どうせ暇してんだろうが晩年下っ端が、という言葉は飲み込んだ。頼み事は下手に出ながら図々しくというのは、俺がたったふたつだけ、電車などに出現する強欲ババアから教わったこの世の摂理のうちのひとつだった。
「ちょっと時間かかるよ」
露骨に嫌そうな表情でいうおっさんの顔を百発脳内で殴ってから、俺はにこやかに笑った。
「ええ、待ってますから平気ですよ」
不満そうな一瞥だけを残して、おっさんは奥の部屋へと消えていった。こうして無人交番はできあがる。俺が泥棒だったらどうするつもりだったのだろうと思ったが、その疑問はすぐに解消した。おそらく、どうもしなかっただろうという解答が見つかったからだ。
「あいつ、なにが楽しみで生きてるのかね?」
いつの間にか隣にいた俺と同年代らしき男に問い掛けると、そいつは乾いた笑いを漏らした。もちろん、その声は俺以外には聞こえない。
「何の楽しみもなくたって生きていける奴がほとんどさ。みんな漫然と生きている」
「なるほど」俺は頷いた。「たしかにそうだ」
「だろう?」男は得意そうに笑う。「あんただって漫然と生きてるくちだろうに。何か楽しみがあって生きてるわけじゃないだろう?」
「正解だがな」通行人が怪訝な目を向けてきたので声をひそめた。「何でわかった?」
「やる気のない顔をしてる」
今度は俺が笑った。
「おまえはなかなか見る目があるらしいから、お礼に良いことを教えよう」
「良いこと?」
奥から肥満気味の体を揺すっておっさんが戻ってきたことを横目で確認し、なるべく独り言に見えるように呟いた。
「おまえはもう、死んでいる」
ケンシロウは日本の少年の、永遠の憧れだ。
「え、うそっ?」
「ホント」
叫んだ瞬間には、男の体は薄くなっていて、そのまま一秒もたたずに消えうせた。ただの浮遊霊のほとんどは、自分が霊だと自覚すると消えていく。同居人みたいなのは稀だ。
それにしても、なかなか愉快そうな霊ではあったが、ただ漫然と死んでいる奴に、ただ漫然と生きている上にやる気がないなどと中傷を受けるとは思わなかった。
「分かったよ。いい? メモする?」
調べ終わったらしいおっさんが半分しか開いていない目を俺に向ける。
「あ、いいです、言ってください」
なんだよ、五分もかからないで調べられたじゃねえか馬鹿、とは当然言わない。
「あ、そう。――あの信号がつけられたのは十一年前の春。当時中学生だった女の子が車にはねられたのが原因。残念ながらその子は即死。その子の名前と運ばれた病院と通っていた学校の名前は順番に―――」
心底めんどくさそうに言うおっさんは、どうして警官になんてなったのだろうと思うと、日本社会の歪みの本質が見えてくるような気がした。地域住人の申し出を嫌そうに受理するような人間が警官に向いているなら、俺はきっと保父さんになれるだろう。
とにかく、知りたいことは分かった。もう用済みだ。図書館に行く手間がはぶけた。
「サンキュ」
片手をあげて言った。家に帰るのもかったるかったので、公園に戻る前に漫画喫茶かどこかで時間を潰そうと思った。考えなきゃならないこともできた。おっさんがきょとんとしているのが笑えたので、振り返ってもう一度「ありがとさん」と付け加えてやった。お願いを聞いてもらうまでは丁寧に、用がすんだら偉そうに。電車ババアの哲学その二。
夕暮れにはまだ早い午後四時。料金を払って漫画喫茶を出ると、傾きはじめた太陽の光が、赤みをましてきたところだった。ポケットから取り出したサングラスをかけて、再び公園に向かう途中、ふと自分が不機嫌になっていることに気付く。
もともと俺は公園が好きではない。散歩で公園に訪れるようなのんきものには一生かかっても分からないだろうが、小さいころ、親とも友達とも一緒に遊べず、ずっと仲間はずれにされていた俺のような境遇で育った人間なら、公園嫌いの理由も察しがつくだろう。
俺の霊視は珍しいことに、母親譲りでも父親譲りでもなく、ただの突然変異だ。まだ十五のときに母親が死に、それ以降、妙なものが見えるようになった。ひょっとしたら俺は単に気の違った馬鹿野郎で、幽霊と思って見ているものもただの幻影なのかもしれないと思ったことも何度かある。
それにしても、生まれてはじめてみた霊が母親だった俺にとって、この能力はなかなか因果だ。半分は妾のような立場にいた母親なんて好きになれるわけもなかったが、それでも唯一の肉親をなくしたショックは人並みにはあったのだろう。
そういえば父親もいたが、認知されていない。母親の生前はややっこしいごたごたがあったらしいが、今は月に十万のおこづかいをくれる足長おじさんにはそれなりに感謝している。高校にも大学にもいかず、かといって定職にもつかず、こうして気ままに暮らしていられるのは、たぶんそいつのおかげだからだ。
公園の入り口から、親子連れが手を繋いで出てくるのと入れ違いに、中に入った。仲良さそうに帰っていく親子連れ、友達連れ。羨ましいとは思わないが、その幸福を幸福と自覚してなさそうなはなたれどもにも憎悪を覚える。
街灯の長い影が伸びている。俺は入り口付近の木に寄りかかって、サングラス越しに空を眺めていた。雲が茜に染まっていく。夕暮れの景色は物悲しいなんていうセンチメンタリズムは俺の中にはなかったが、血をぶちまけたような夕焼けはどうしても好きにはなれない。
その赤い光を一身に浴びて、存在感のない少女は、制服をまとってブランコの上に座っていた。
黒髪が夕日を透かし、真っ赤に燃えて見えるその姿は、凄みさえ感じさせるほど美しかった。
話し掛けなかった。風の死んだ夕暮れ。宵闇はまだ舞い降りていないし、公園には何組かの母子がしつこく残っているのだから、まだそのときではない。
夕焼けがおさまりつつある頃になってようやく、最後の一組が帰って行った。街灯にあかりが灯り、辺りをうっすらとした闇が覆いはじめた。俺はサングラスを取り、寄りかかっていた木から、少女の方へ移動した。
「あんたは、気付いてるな」
細い顎を上げて、少女はブランコに座ったまま、俺を見すえた。それは、さっきから分かっていた。自分の透けている体にも、自分が誰にも話し掛けてもらえない理由にも、少女は気付いていた。
「放っておいてください」
「よく言うぜ。自分から呼んだくせに」
意外そうに目を瞬いた少女の美貌は、目も眩むほどだった。黒曜石の瞳は吸いこまれそうなほどに深く、色白の顔に、控えめな赤の唇がよく映える。霊じゃなかったら拝み倒してでも口説いたに違いない。
「呼んだ? 私が? あなたを?」
「俺は生粋の能力者じゃないから、霊に呼び寄せられるなんて稀なんだけどな。夢にまでシンクロして助けを求めてきたのはあんたの方だろう?」
「知りません。私、別に助けて欲しいなんて思っていません」
「そりゃあ、あんたは自覚してないだろうな」俺は頷いた。「そういうもんだ。でもな、霊を見つけてそのまま放っておくわけにもいかねえんだ」
むろん、嘘だ。放置してきた霊なんて腐るほどいた。俺は慈善活動で除霊をやってるわけでもなければ、それを商売にしているわけでもない。ただ、自分の利益になることにしか使わない。
だから、もう少しこの少女のことを知るための手段としてこの切り札を持ち出すのは、俺にとっては実に正当な理由だった。絶世の美少女と一秒でも長く関わっていたいと願うのは、この上もなく不純で、ゆえにこれ以上ないほど純粋な欲望だ。
「自分が死んでいることも知っている。誰かに復讐したいわけでも、達成したい目標があるわけでもない」指を三つ折ってから、俺は隣のブランコに座った。「残って何がしたいんだ?」
「ここにいたいんです。邪魔しないで下さい」
うっとうしそうに手を振る少女の細い手首を掴んで、こちらを向かせた。霊に触れるにはそれなりの集中が必要なので、ここまですることは滅多にない。
「誰を待っている?」
「なんのことですか?」
「『公園には誰もいない。今日もこなかった』。あんたの夢だろう?」
「なるほど」少女は腕を振り払って、溜息を吐いた。「シンクロとか夢とか、よく分からないことを言ってたけど、そういうことなんですね。驚いた。霊能力者って本当にいるんですね」
「俺も信じたくないけどな、どうやら存在するらしい」そして、と俺は言った。「霊もいる。ここに」
じじじと、公園の隅で白熱灯が悲鳴をあげている。雲の切れ間から顔をのぞかせた白い月が、少女の、さらに白い首筋を濡らした。
「十一年だぞ。あんたが死んでから、もう十一年だ。そろそろ諦めていい頃だとは思わないか?」
「それは私が決めることです。私のことを何もしらないあなたには分かりません」
「新野早苗。享年十五歳」
驚いた表情を必死に隠しながらこちらを見る少女がかわいかったので、ついふきだしてしまった。
「交通事故の記録なんて、調べれば出てくるさ」
ああ、そうですね、と気のない返事をして、少女は月を見上げた。夜が深くなった。そろそろ帰る時間なのかもしれない。
「どうしてここにこだわる。誰を、何を、どうして、いつまで待っている?」
二度目の問いも、はぐらかされた。
「なんでもいいでしょう? あなたには関係ありません」
「おおいにある。俺が知りたがっている。ついでに、あんたのことはやけに気にかかる」
「そんなの」少女は首を振った。「そんなの、あなたの都合じゃないですか」
「もっともだ。だが残念ながら、俺はワガママなんだ。――一明日の夕方まで待つ。明日また来て、そのときにも答えないようだったら、強制的にあの世に送ってやる。ただし、正直に言ったら力になってやる」
この場で吐かせることも可能だったが、そんな横暴は好きじゃなかった。不満そうに抗議を口にしようとした少女から視線をそらして、立ち上がった。ブランコが、甲高い金属の声で、鳴いた。俺は、公園の出口に向かって歩きはじめた。
「私、あなたみたいな人、嫌いです」
叩きつけられた拒絶は、むしろ心地良かった。
叫ぶように、しかし静かな声音で、少女は言った。
「自分勝手で、人の都合なんて考えないで、何でも好きにやってしまう。そのくせ希望をもたせるようなことを言って、最後には何もしてくれない。そんな残酷ってない。嫌いです。本当に、大嫌いです」
立ち止まって、振り返った。思ったとおり、少女は泣いていた。美しい瞳から、真珠よりも輝かしい大粒の涙が、ひとつふたつと零れ落ちていく。
「私はここにいたいんです。待っているんです。別にいいでしょう? 死んだ後くらい、自由にしたっていいじゃないですか。誰にも迷惑かけません。どうして好きにさせてくれないんですか」
俺は首を振って、再び出口に向かって足を踏み出した。
「明日また来る。文句ならそのときに言え」
あんたのためだ、なんて白々しい台詞は吐けなかった。
月が翳った。街灯の頼りないあかりだけが、帰り道を照らしてくれる。
「いやだよ。まだここにいたいよ……」
もはや背後の声は遠い。
夜道を歩いていく母子の姿を幻視した。背中の細い母に手を引かれて歩いているのは、俺か少女か。
どちらにせよ、救いは欠片もありはしない。
「やあ、帰ったね」
「失せろ」
陽気に笑いかけてくる同居人に絶対零度の一瞥を投げて、服を脱いだ。
「こりゃ、ずいぶんご機嫌ナナメだ」
「聞こえなかったのか?」
睨みつけ、射抜き殺さんばかりの視線に憎悪を込める。そこには、決して拭えぬ過去があり、俺を今までずっと縛り続けてきた、得体の知れない世界というばけもののように巨大な不条理が立っていた。
「失せろって言ったんだ。おまえらはいちゃいけないものだ。うせろ、消えろ。俺の目の前からいなくなれ。帰れ帰れ帰れ。みっともなく残りやがって。人の迷惑の一つくらい考えろ。存在価値のねえクズどもはとっとと成仏して塵になれ」
「何があったかは分からないけどさ、それは君らしくもない台詞だ」
シャツを脱ぎ捨てて、風呂場のドアを開けた。今日ばかりはガスが止まっていても構わなかった。冷たいシャワーで頭を冷やすのも悪くはない。
「俺らしい? 女に振られた如きで自殺したできそこないに、俺の何が分かる」
脱いだズボンを投げつけると、同居人はそれを受け止めようと両手を掲げ、それから寂しそうに笑った。ズボンは当然のようにやつの体をすり抜け、壁にぶつかったベルトが騒がしい音を立てた。
「こんな体さ。触れもしない、君みたいな人以外には見えもしない。何もすることができない。そんな体さ。今の僕はね」
「だったら、さっさと消えちまえばいいだろ。どいつもこいつもどうでもいいことにこだわりやがって」
「それでもなんだ」
月明かりに透けて、同居人の体はあまりに脆そうに見えた。
「こんなみっともない体になっても、それでもまだ諦められないことがある。忘れられないことがある。みっともないし情けない。そんなこと分かってる。でもさ、それでも残っていたいと思わせる、大事な何かが僕たちにだってあるんだ」
質量のない体を震わせて、幽霊は吼えた。
「君にはどうして、そんなことも分からない!」
「うるさい」
風呂場へ入り、ドアを閉めた。
「負け犬が偉そうに語るな」
奥歯を噛んだ。
それでも俺は生きている。おまえら幽霊と一緒に、死んだようになって、それでも俺は生きている。目的もなく、目標もなく、ただ意地だけで、俺は生きている。見捨てられた自分のために、見捨てた奴を見返すために、負け犬になって死ぬことだけは選ばなかった。
生きてる価値さえなかった。母親にとって、俺は道具に過ぎなかった。妾の立場。俺の存在だけが、父親を繋ぎとめておく切り札だった。だから、それは俺でなくても良かった。俺は何も期待されなかった。ただそこにいるだけで、あるだけで、俺は完結していたから。
だから、生きてやろうと思う。母親が死んで、価値のなくなった体で、だからこそ生きてやろうと思う。誰にも与えられなくても、自分のために、自分の意思で。
死んだ奴が偉そうに言うな。死んだら終わりなんだ。死人には償いも謝罪もできやしない。だから俺は、今でも一人で生きている。
シャワーから出ると、同居人の姿はなかった。ベッドに倒れこむと、夜の闇より重い濃紺の睡魔が、厚い緞帳のように降りてきた。
きっと今夜もあの夢を見る。
待ち人は、もう来ないのだろう。
そんなことは知っていた。分かっていた。だからこれは儀式みたいなものだと思っていた。毎日毎日、日が暮れるまでこの公園で待っていること自体に意味がある。まだ弱い自分を苛め抜くことに意味がある。
それでも、と思ってしまう。
それでも、寂しいと思ってしまう。
そんな自分は弱いのだろうか。
そして今日も日が暮れた。
帰ろう。腰を浮かせて、公園の出口へ向かうと、ちょうど道路にサッカーボールが飛び出してきたところだった。ただ呆然と、何も考えずにその光景を見ていたら、女の人の叫び声が聞こえた。
「危ないからやめなさい!」
裏路地から、それこそ球みたいにまっすぐ、小さな男の子が飛び出してきたのと、車がヘッドライトを閃かせて加速したのはほとんど同時だった。
気がついたら死んでいた。男の子が無事だったかどうかは分からなかったけど、興味もなかった。自分の危険を考えず、男の子を突き飛ばしたのはなぜだろう。
羨ましかったからだ。途方もなく、羨ましかったからだ。
魂とかたぶんそういうものが空に上っていく途中、ただぼんやりと、死にたくないと思った。それは、明日のテレビ番組が楽しみだったからでも、好きな人がいたからでも、やりたいことがあったからでもなかった。
ただ、待っていたかった。もしかしたらくるかもしれない人を、もう少しだけでも。
行儀よく膝に手を乗せて、背筋を伸ばしてブランコに座っていたかった。髪も染めず、スカートも短くせず、真面目に、ただ待っていたかった。遠めからでもすぐにそれと分かるように、行儀よく、もう少しだけ。
気がつくと、ブランコに座っていた。私が死んだ春ではなく、秋の頃に。こちらへ戻ってくるのに、二つの季節を越えてしまったのだと気付いた。
それでも良かった。安心して胸をなでおろした。
これでまだ、あの人が来るのを待っていられるのだから――。
起き抜けにトイレに行き、唾を吐いた。
なにが「放っておいてください」だ。こんな夢を見せやがって。放っておけるわけがないだろう。
こんなの、放っておけるわけがないだろう。
悪態をついて、水を流した。「助けてください」と叫ぶ声を、聞いた気がした。
夕焼けの公園で、少女はやはり一人で座っていた。良くも悪くも、少女ほど浮世離れしたという形容が似合う存在はいないだろうと、つまらないシャレを思う。紅蓮の炎をあげる落日が投げる光は、少女に影を与えない。はるかかすむ稜線に落ちていく今日というひと時への決別は、何度も繰り返した絶望のリピートだ。
ブランコは動かない。新野早苗はブランコに座っているわけではないからだ。幽霊は物体に触れることができない。ただそこにあるだけの、ぶさいくな世界の矛盾。救いがたい世の中の齟齬。修正されるべき誤り。
それが、やつらだ。
まだ公園には客がいたから、俺は話し掛けなかった。昨日と同じく、距離を取って、あまりにも美しすぎる早苗の姿を眺め続けた。車にはねられて血まみれになった死の瞬間でさえ、早苗はこんなに赤くはなかっただろう。
太陽が落ちる。そして早苗は、人知れずまた落胆の溜息を吐く。何もなくなった体から、ただ寂寥と悲哀だけを滲ませて、また期待などしていなかったと自分をごまかし、涙を流さずにさらさらと泣く。
そんなのはもう、未練ですらない。ただの、夢見ることさえはかないだけの、淡い淡い幻想だ。
「どっちにするか、決めたか?」
じゃりっと、公園の砂を踏んで、早苗の前に立った。俯いた早苗の白い顔に、濡れたように真っ黒な髪がかかっていた。宵闇のほかには何もない。星が、音もなく輝いている。
「話します」
諦めたように呟いて、少女は髪をかきあげた。
「話しても話さなくても消えなきゃダメなら、話します」
それは決意だった。それは、この世という地獄よりもおぞましい場所に、最後まで希望を探し続けていた少女の、可憐なまでの決意だった。この上もなく辛い裏切りを十年以上も受け続けて、命も体も失って、心までぼろぼろに傷つきながら、それでも信じることを選んだ少女の、泣きたいほどに哀憐な決意だった。
「頭のいい人間は嫌いじゃないな」
目をそらして言った俺の足は震えていた。足のない早苗は俺を見なかった。その先にあるまぼろしは、きっと昨日、俺が見たものと一緒だったのだろう。
母と子。どこにでもある、けれど、俺たちには与えられなかった光景だ。
「誰を待っているんだ?」
もう分かっていることを、俺は尋ねた。
「母を、待っています」
答えた薄い手は、小刻みに震えていた。強く握り締めた拳は、しかし何ひとつ殴ることもできない不完全な激情の具現だった。早苗の母がここに現れたとしても、もはやその手を握ることさえできなければ、その顔を殴ることもできない。消えてしまった早苗の体は、誰かに抱きしめてもらうことさえできなくなった、できそこないだ。
「ここで、捨てられたんです。母に。六歳でした。父に死なれて、私をこの公園に残して、母は他の男の人のところへ行きました。祖父母もいなくて、親戚もいない私を捨てて。母のお腹には、その人の赤ん坊がいたのだと思います。私は、母にとって邪魔な存在でした」
起伏のない声で、少女は淡々と語った。
「でも、私にとって母は母でした。たった一人の肉親でした。母にとって私は邪魔でも、私には母が必要でした」
不公平でしょう? そう言って、早苗は暗く微笑んだ。
「母は小学校に上がったばかりの私に向かって言ったんです。待っててねって。いつか迎えに来るからって。私が良い子にしてたら、きっと迎えに来るからって」
月光が、冷たく降り注いでいた。早苗は、泣いていた。透明な、地面に落ちても決して砂を濡らさない涙を流して、早苗は泣いていた。
「私、良い子にしてました。成績も良かったし、校則も守ったし、学級委員もやりました」
嗚咽は、俺以外の人間には聞こえるはずがなかった。けれど、早苗の喉からもれる切なげな吐息は、この国にいる全員が聞いているのかもしれないと思った。誰もがそうした不安を持って生きていて、死んだあとも、こいつらはそういうものに縛られている。
救われない。どこまでも。
しゃくりあげる早苗の細い肩は透けている。誰にも抱きしめられることのない、存在しない細い肩。この醜くよごれた世界に、これほど美しくて純粋なものはないのだと俺は思った。
「待ってました。ここに、毎日毎日、母がいつきても平気なように通って。膝に手をそろえて。一目で私だって分かるように。良い子にしていたんだって分かるように、ずっと待ってました。小学校を卒業しても、中学校に上がっても、ずっと待ってました。ずっと、ずっと」
早苗は泣いた。でも、でも、と叫びながら、早苗は何よりも清く、何よりも貴い涙を、惜しげもなく流した。
「でも、母は来なかった!」
それほどに悲痛な叫びを、俺は金輪際聞くことはないだろう。誰よりも、早苗は哀れだった。
「ひょっとしたら私に気付かないで、帰っちゃったのかもしれないと思って、それだけが不安で、今からでも迎えに来るのかもしれないって。そのときに私がいなかったら、母はきっと悲しむと思って。だから私、ずっとここで待ってるんです」
俺は吐息した。
そんな無駄なことのために、来るはずのないそんな馬鹿親のために、君は十一年も待っていた。
「夢だって知ってました。来るわけないって分かってました。それでも、母が来てくれるかもしれないって、手を振って迎えに来てくれるかもしれないって、私の手を引いてどこかに連れて行ってくれるかもしれないって、そう願うことの、何が悪いんですか!」
「悪くない」
誰も君を責めることなんてできないだろう。
「何も悪くはない。けれど」
知っているだろう?
「それは、叶わない願いだ」
「そんなのまだ分からないじゃないですか!」
「分かるんだよ!」
自分で出した大声に、誰よりも俺が驚いた。俺も泣いていた。早苗と俺は、ほとんど全く一緒だった。ただ一つ違いがあるとすれば、俺は生きていて早苗は死んでいるということだけだ。
それは、あまりにも絶望的な差異だった。
「君の母親はもう死んでる。ろくでもない男の妾になって、息子をろくに育てもせず、下らない趣味に没頭してたあの女は、もう死んだんだ」
気付いていた。
新野という苗字。不自然なほどに合致する年齢差。幼い頃の記憶。酒に溺れて漏らしていた母親の愚痴。その欠片を拾い集めて、俺は気付いた。姉がいるのだと。その、どこかにいたはずの姉の顔が、少女の横顔とだぶった。
顔だけは美しかった母に、早苗は似ていた。
母親は、早苗の父親に死なれてから、俺の父親に取り入った。そして早苗へのあの残酷な言葉を、俺は母の腹の中で聞いていた。新野。その苗字を聞くたびに、母は露骨に嫌な顔をした。まるで、思い出したくもない過去の汚点をえぐられているかのように。
「どうして?」
「俺が成仏させたからだよ。この手で、この能力で、無理やりあの世に送ってやったからだよ。酒の飲みすぎでポックリ逝って、みっともなくこっちにへばりつこうとしたから、蹴り上げてやったんだよ」
俺は、きっと世界で俺にしかできない抱擁を、早苗にしてやった。この街で霊に触れられるのは、少なくとも俺の知る限りは俺だけだった。泣きたくなるほど頼りない肩は、十一年間背負い続けた荷物のせいで、悲しいくらいに震えていた。
「来ない人を待っていても仕方ないだろ? だから、もう逝け。せめて、俺が送ってやる」
母を送ったこの手で、天国にまで押し上げてやる。
だって俺は、君の唯一の家族だから。
俺には、そんなことしかできないから。
「おとうと……?」
手を引かれて、母親と並んで歩く。そんなどこにでもある光景。誰にでも与えられる幸せ。当たり前の日常。そういうありふれた、ささいな、だけどかけがえのない生活が、君の見た夢だったなら。
せめて、母ではないけれど、家族として、弟として、俺がその手を引いてやりたかった。耐えて、耐えて、耐えて、涙を拭くことしかできなかったその手を、しっかり握ってやりたかった。
その、白くて細くて、どうしようもないくらいに悲しい、手。
「ほら、手、出せよ」
早苗は、静かに右手を差し出した。俺は笑って、その手を握った。
念じる。強く。
――せめて、こいつを天国に。
「そういえばあいつ、俺が九歳だった夏に、ふらっとどこかに消えることがあった。ひょっとしたら、この公園に来てたのかもな。丁度、あんたが向こうから帰ってこようとしてたときに」
早苗は意味ありげに笑い、俺の頬を両手で包んだ。手は、冷たかった。
「ありがとう」
最後に、早苗はそう言った。泣き笑いの、なんだか中途半端な表情を残して、早苗は逝った。消えた。もう俺にさえ、その姿は見えない。天国にいけたのかどうか、俺が死ぬまで分からないままだろう。
けれど、間違いなく、天国にいけたはずだ。もしも本当に神様なんてものがいるのなら、あの薄幸の少女を、せめて死んでから救ってやらないはずがない。
俺はその場に膝をついた。ひどく疲れていた。だから、もうこれ以上幽霊の相手をするのはごめんだった。
「お疲れ様」
「なんでおまえがここにいるんだよ」
なのに、同居人はにっこり笑って、どうせ触れられない手で、俺の肩を叩いた。
「見事だったね。君は偉い。ありがとう。これでようやく僕も成仏できる」
「おまえは関係ないだろうが馬鹿」
「おおありさ。僕の未練は彼女だからね。彼女に振られて、落ち込んで、学校から帰る途中、車にひかれそうになった男の子を見た。僕は一瞬、目を瞑った。だから動けなかった」
「そのびびったお前の代わりに、新野早苗が犠牲になった」
俺は鼻で笑った。
「できすぎだ。そんな都合のいい話があるもんか」
「あ、やっぱりバレた?」
「当たり前だ」
「うん、もちろん嘘だけどね。君だって嘘をついただろう?」
さあな、と俺は首をかしげた。
「彼女が丁度いなかった期間にだけ母親が顔を出していただって? それこそ、都合が良すぎるよ」
「でも、ありえなくはないだろう?」
みんな、そうして生きている。
挫折と苦悩と絶望だらけの世の中で、胡散臭い一握りの希望だけを信じて、そのためだけに生きている。だから、嘘でもこじつけでも強引でも、それはきっと、罪になることはないだろう。
「ま、どっちでもいいんだ、正直ね。いい加減、この世にも飽きたから、僕もそろそろ向こうに行くよ。じゃあね、お世話になった」
早口でそこまで告げると、同居人は霧のように消えた。仮面のような笑顔が張り付いたままだった。存在自体が嘘くさい奴だったのに、嘘が下手だっていうのは何とも皮肉だ。
俺は公園の砂場の上に寝転がった。疲れていた。暗い空。藍色の雲。闇を切り裂くように、大きい月が、金色に輝いていた。
寝転がった俺の隣に、作りかけの砂の城と、放り出されたシャベルがあった。俺はその冷たい玩具に触れて、顔を覆った。姉と母と一緒に、この砂場で遊ぶことができたとしたら、それは何てかけがえのない幸福だっただろう。
嗚咽が漏れた。そんなものが、俺たちの見た夢だった。
頭上には月。夜明けまでにはまだ時間がある。
俺はシャベルを握り、砂を掻いた。一人だった。けれど不思議と、寂しくはない。

 ハシモト(はしもと)
ハシモト(はしもと)