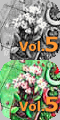- 特集「見る」
- 哲学者からの手紙
- 「書」
- 難しさにこそ、魅力が
- Talk Session
- みることからふれることへ
- 「見る」から「描く」へ
- Novel
- スイッチング・ウォッチング
- 同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
- よくばりな眼
- 秋の夜の夢
- 王子の見た景色
- ちいさなひとひら
- 宣告
- バードウォッチング
- see
- 見る
- Use your eyes
- おしりやぶれたズボン
- アイズ
- 万華鏡の世界
- Coffee Break
- ズレないBookCover
- Series
- メッセージをどうぞ
- おいしい水
- 不愉快なテクスト
- "いろは"の先のCSS
- Player's Side
- from editor
- 次回予告


バードウォッチング
岩井とおる
暗闇だって悪くはない、と思う。
暗闇では見ようとすればするほど見えなくなるんだよ、と智司は教えてくれた。理由を聞いたらあいかわらずわけのわからない難しい話(光を感じる細胞がどうのこうのとか言っていたけれど何一つ頭の中に入ってこなかった)をして、もちろん千恵にはわからないだろうけどねと笑っていた。暗闇でものを見るためのコツは、何かを集中して見ようとするのではなくてできるだけ広く漠然と見ることなのだそうだ。暗闇は決して見つめてはいけない―これがわたしが智司から数多く(とてもとても数多く)教えてもらったことの一つだ。
でも本当は、この言い方は正確じゃない。わたしはもともとそんなことは知っていた。でも知っているからと言っていったい誰が暗闇を見つめることをやめられるのだろう?やめられるはずがない。でも智司はそうじゃなかった。見つめてはいけないものは見つめない、それが智司だった。素敵でまっすぐな生き方でまぶしいほどに羨ましかった。わたしにはそんな風な生き方はできない―でもいつしかわたしは暗闇をあまり見つめなくなっていた。夜が怖くなくなっていた。
もちろん本当に光が全くないところでは、どんなに視野を広げようとしてもなにも見えるわけがない。いくら一点を見つめ続けようとしても、どんなにその暗闇の広がりを感じようとしても、完全な暗闇は完全な暗闇のままだ。そこではそもそも、眼なんていうものはぜんぜん役に立たない。わたしがいまいる暗闇は、そういう種類の暗闇だった。そしてわたしは自分から望んでここにいるのだ。セックスをするのに視覚は必要ない、これがわたしの性生活におけるささやかなポリシーである。
智司はわたしの顔のすぐ右横に座っている。たぶん十五センチくらい離れたところだ。何も見えなくたって、いる場所くらいは分かる。気配。わたしの感覚は鋭敏なセンサーとなって彼の温かみを察知する。そして守られているのだ、と思う。光がないからこそ、触れ合っていないからこそ、わたしは守られていると感じることができる。光がなかったり触れ合っていなかったりしたら不安になるような関係なんて、いったいどんな意味があるのだろう。
表情まで推しはかることはできない。視線を感じることもできない。そのかわりにわたしは想像する。智司はわたしの体をなめ回すように見る。山歩きをしているから少しは締まっている足、濡れてしまっているのを悟られたくないからぎゅっと閉じている性器のちょっとだけ濃いめに茂った陰毛、おなかの真ん中にある愛すべきおへそ、最近また少し大きくなってきたかもしれない胸。それから視野は顔をとらえる。目隠しをした自分の顔ほど想像しにくいものはない。絶対に光を通さないようなアイマスクを智司は買ってきてくれた。変じゃない?とたずねたら、うんすごく可愛いよ、となんともシリアスな声で言ってくれた。その声は、もしかしたら本当にアイマスクをしたわたしは可愛いのかもしれないと思わせてくれる。確かにもともとわたしは自分の目と眉毛のバランスがあまり好きではないのだ。それにしても自分に見えないものをそう言ってくれるのはすごく大事なことだと思う。
想像の中で智司の目は顔から再び胸にうつる。薄桃色の、本当に透き通るくらいにきれいな薄桃色の(とたった一つだけ自分の体の中で自画自賛できるような)乳首を智司は突き抜けるくらいに凝視する。光があるところでは―と智司は言っていた。注視すればするほどそのものが良く見えるようになるのだ。
眺めてばかりいないでそろそろ触ってくれてもいいのに、と思っていたら智司が突然立ち上がった。そういえば智司は服を着ているんだったかしら裸だったかしら。裸じゃないとすれば、やっぱり少し不公平だ。いくら見えないと言っても、見えないところにこそ気を使うのが紳士の身だしなみ、みたいなところはあると思う。
触って確かめてみたい。でももちろん触ることはできない。わたしの手首は頭の上で縛られているのだ。最初は少し怖かったし、いまでも嫌がるフリだけは一応するのだけれど、この不自由さにすっかりやみつきになってしまった。ヒトは自由が好きだなんて、そんなのは嘘だと思う。たとえばもしいつでも智司に会うことができて、好きなときにキスしたりセックスしたりできて、ほかの男の子とだってなんの後ろめたさもなく奔放に遊んだりできるとしたら、わたしはきっとひどく混乱してしまう。自由になるというのはきっと、高層マンションの屋上から飛び降りるみたいなものだ。自分を縛るものも、支えるものも何もない。三六〇度、あらゆる方向に世界は広がっている。それなのに、落ちていくことしかできない。たぶんこれが自由の本質だ。選ばれたヒトだけが、その自由を享受することができる。けれどわたしには翼なんかないから、こうやって手を縛られて、視界を遮断されて、せめて想像だけは軽やかに宙を舞っているのだ。わたしの趣味―笑われるかもしれないけれどバードウォッチングなのだ―をバカにする智司にだって、もちろん翼は生えていない。生えていないから、こうやってわたしを一時的に思うがままにもてあそんで喜んでいたりするのだ。でも智司はバカじゃないからそんなことはちゃんとわかっている。お互いさまだ。わたしがなんでバードウォッチングを好きなのかといったら、鳥は自由を強く想起させるからだ。鳥たちには翼がある。でもだからといって鳥たちが自由なのだと誰かが考えるとしたらそれは大きな思い違いだ。あの翼は具体としての翼であって象徴としての翼ではない。その証拠に、満足に走ることさえできないではないか。そしてそんなところが、いうまでもないことだと思うけれど、たまらなく愛らしい。
智司はしばらくそのまま突っ立っていた。どうやって遊ぼうか考えているのだ。思案しながらジーンズをひっかく音がして、ああ智司はやっぱりまだ服を着ているのだ、と思う。そして急に自分の姿が恥ずかしくなる。ジーンズの中で大きく固くなっているだろう(というか、間違いなく固くなっている)性器のことを思う。きっとそろそろ我慢できなくて、触れるか触れない程度にわたしの体を愛撫し始める頃だ。その瞬間のことを想像して、わたしのヴァギナはパブロフの犬みたいに濡れ始める。
ところが予想に反して智司はそのままわたしから離れていく。あまり遠くない玄関に静かに向かう足音、足をスニーカーの中に入れるために何度か踏み鳴らす音、チェーンを外す音、鍵の開くカチッという音。どこに行くの?と尋ねても返事はない。控えめにドアの閉じる音がして、鍵が閉まり、音が消えた。蚊取り線香(といってももちろん電気のやつだ)のライムの香りが鼻をつく。
智司がこんなことをしたことは一度もない。そのことでわたしは少し不安になる。でも何も言わずに出て行ったところを見ると、きっとわたしを焦らすために出て行ったのだ。最近放置プレイもマンネリだからこういう展開も悪くない。智司がしばらくして帰ってきて何食わぬ顔で(といってももちろんその顔を実際に見ることはできないのだけれど)優しく触ってくれることを考える。
外から覗いてみたいなんて考えが浮かんだのは、焦らす間の時間つぶしに千恵の部屋をぼんやりと見回していた時だった。こういうプレイを始めたばかりの頃はじっと体を眺めたりしていたけれど、最近は少し見飽きてしまってこうやって部屋を観察していたりする。ニュートンの運動方程式のごとく完璧でシンプルで美しい千恵の部屋にあって、今日は珍しいことにバードウォッチング用の双眼鏡が床にほっぽりだしてあった。これを使えばむかいのマンションからこの部屋が覗けるだろうと思ったのだ。
千恵との付き合いはもう長い。でもなぜバードウォッチングなんかが好きなのかということだけはどうしても理解できない。鳥は自由を象徴しているのだと千恵は言う。しかし渡り鳥なんてあんなに時間と労力をかけて、比喩でもなんでもなくて死に物狂いで生息地を往復するのだ。そんな動物のどこが自由なのか僕にはわからない。そういう当然の疑問を伝えると、鳥自身は自由じゃないことくらい知っているわよ、わたしが言っているのは象徴としての自由なの、と彼女は力説する。不自由さが自由を象徴するなんてことは僕には到底理解できない。それでもそういうあり得ない(と僕は思う)世界があることは認めるし、結局のところ人はみんな別々の世界に住んでいる、というのが僕の基本的な考え方だ。僕の世界は千恵の世界と違って不自由は自由を象徴し得ないけれど、それでも響きあうところが多いからこうして一緒にいられるのだと思う。
双眼鏡を持って外に出て、まっすぐに向かいのマンションに向かった。向かいのマンション大きいけれど、千恵のマンションのように新しくはない。自動ドアもなければオートロックもない。エレベータは軋みながらゆっくりと上がり、なんとか七階へ辿り着く。外に設置されている千恵のマンションの向かいの非常階段に出た。千恵の部屋も七階だ。僕は双眼鏡を手に取り、千恵の部屋を探そうとレンズをのぞいた。双眼鏡は確かに高性能のようだった。千恵のマンションの白いタイルの汚れまで鮮明に見ることができる。視界を少し下にずらすと部屋が見えた。まだ昼間なのにカーテンがかかっている。隣の部屋には視界をずらす。カーテンはかかっていないけれど誰もいない。千恵の部屋はその隣だろうか。そう思って覗いた部屋で僕は奇妙な光景を目にする。
その部屋にはほとんど何もなかった。カーテンもないから僕は極めてクリアにその部屋を観察することができた。部屋にあるものはただ一つ、二段ベッドだけだ。ベッドがあれば当然あるべき布団や枕までもがそこには存在していない。二段ベッドの木の枠組みとはしごが、なにかの象徴のように部屋の隅にたたずんでいる。千恵の部屋とほぼ同じ間取りのワンルームのはずなのに異様に広く見える。真っ白な壁、輝くようなフローリング(たぶん念入りにワックスをかけているに違いない)。クローゼットの扉は取り外されている。扉はどこに行ってしまったのかわからない。とにかく、この部屋にはなにもないのだということを証明する、ただそれだけのために扉は取り外されたのだという気がする。この分だとユニットバスの扉まで取り外されているのではないかと思われたけれども角度の関係で見ることができなかった。
部屋から目を離せないでいると音もなく二人の男女がその部屋に入ってきた。当然(すくなくとも僕には当然に思われたのだけれど)彼らは身に何もまとっていなかった。どうやって全裸でこの部屋までやってきたかということについては、何ら情報を得られなかった。常識的に考えればおそらくバスに入って出てきたのだろう。洋服はバスにおいてあるのだろう。しかしそうした合理的な思考はこの部屋においてはひどく不適当なように思われた。つまり、この部屋にはたとえバスにだって何も存在してはならないのだ。
二人は美しかった。人気俳優にも劣らない綺麗な顔立ちと、雑誌の「Tarzan」に出てくるモデルのような体つきをしている。男の鼻筋は通っていて高い。目は大きく二重で唇は薄く締まっている。髪は茶色で長く、軽くウェーブがかかっている。背は百八十はあるだろう。胸板も厚く腹筋はたくましく割れている。ペニスも文句のつけようがなかった。もしかしたら、太すぎて痛がる女性がいるかもしれない。でもきっと男のテクニックがあれば大丈夫なのだろう。女も鼻が高く、透き通るような目をしている。唇は少し厚くどこか隙のあるような印象を与える。足が長い。身長も百七十くらい。ヒールをはいた彼女と僕が並んだら見上げる形になってしまう。余計な贅肉は一切ついていない。大理石のような白い肌。胸も大きい。しかも垂れていなくて上にキュッと上がっている。腰のラインはルネサンスの彫像を髣髴とさせた。そしてどこまでも真っ直ぐにのびる細い足。完璧だ、と僕はつぶやいた。まさに完璧なカップルだ。完璧すぎてそこにはエロティズムの介在する余地すら残されていなかった。カミソリ一枚その完璧さには入り込むことができない。女の陰毛はきれいに剃られていて白い肌が露出していたが、それさえもエロティックというよりは無駄なものは一切必要ないという決意表明にすぎなかった。二人は会話やアイコンタクトを交わすこともなくまっすぐに二段ベッドに向かった。男が先に慣れた動作ではしごをのぼる。手の動き、足の動き、どれをとっても非の打ち所のない実に優雅なのぼりかただ。女はそのはしごの下で待っている。あまりの立ち姿の美しさに、生きていないようにさえ思える。男は二段ベッドの上で飛び込む前のような体勢をとった。北島康介がアテネオリンピックの平泳ぎ百メートル決勝の舞台に立っているかのような緊迫感と集中力がみなぎっている。そしてもちろん北島康介より遥かにさまになっている。音のない笛が鳴り、男は飛んだ。
飛んだ。男の行為はそうとしか表現しようのないものだった。飛び立ったその瞬間から手を広げ動かし、揚力を得ようとしていた。その顔の端正さやバランスのとれた体つきとあいまって、実に自然な飛行姿勢であるように僕には思えた。悲壮感などかけらもなく、自信に満ちた表情で手を動かしていた。その瞬間瞬間だけをとってみれば間違いなく飛行は成功していたように思われる。けれども男はその狭い部屋において、向い側の壁に激突することもなく、一度も体が浮くような気配すら見せることなく地面に落ちた。手をはためかせて(それはこれ以上ない動かし方に見えたのだけれど)自分の体重を支えるに十分な揚力を得ることに失敗して床に近づくと、手を前に伸ばしあごを上げてバレーのフライングレシーブのような格好で床の上をすべるように着地した。完璧なレシーブだった。そしてすぐに立ち上がり、小さく首をひねり、次やっていいよ、と女に目で合図をした。失敗したのだろう、たぶん。しかし僕にはそれを失敗と言い切れる自信がなかった。男が首をひねらなかったら、成功だと思ったかもしれない。女は目でその合図に答え、相変わらず無表情でその梯子をのぼる。
女も全く同じことを繰り返した。優雅に着地し、首を小さくひねり、男に合図をする。そして男が再びベッドにのぼる。その飛行練習(たぶん飛行練習だと思う。それ以外になにか適当な名称や目的を思いつくことができない)を僕は飽きることなく見つめていた。彼らは毎回毎回まったく同じように飛び、同じように着地した。そこには進歩とか学習とかそういうものは一切なかった。あるいは、それはもう既に完成されていたのかもしれない。その方法では空を飛ぶことはできないとか、たとえば窓から飛んでみようと試みたら死んでしまうとか、そういうことは彼らにとってどうでもよかったのかもしれない。確かに、梯子をのぼるところから首を小さくかしげるところまで、それではどこを直せばよくなるのかと言われても答えようがなかった。どこを直したところでそれは到底もとの美しさにはかなわないのだ。彼らは身をもって、どんなに努力しても人は飛ぶことなんかできないのだと示しているようだった。
女が十六回目の飛び込み体勢に入る頃、「彼女放っておきすぎじゃないのか?」と後ろから男の声がした。僕は、「いいんだ」と答えて、それから我に返って双眼鏡を手からすべり落としてしまった。手と足が震えて言うことをきかない。なんとか相手にさとらせまいと必死に震えをとめようとするが、とめようとすればするほどに震えはひどくなる。相手の次の一言を待つ。しかし彼は沈黙を守っている。首にひもをかけていたので双眼鏡は所在なげにぶらさがり、僕のペニスの先端に当たっている。知らない間に勃起していたのだ。そのことに気付くとなぜか震えが軽くなったので、思い切って振り向いて相手の顔を見た。三十代半ばくらいの男でスーツを着ている。たぶんセールスマンかなんかだろう。さっきから端正な顔ばかり見ていたのを差し引いても、相当に醜悪な男だった。左手に仕事用の黒い革のカバン、右手に双眼鏡を持っている。この男は僕と千恵の部屋を覗いていたのだ。男の眼を睨み付けると、男は不当ないいがかりでもつけられたように苦笑いして、同類なんだから仲良くやろうぜと言って双眼鏡を目にあてた。同類じゃない、と僕は思う。お前はただののぞきじゃないか。そう叫び、殴りかかろうとするのを何かが押しとどめた。もっと狡猾に、もっと決定的に、もっと確実に打ちのめすべきだと僕の心は告げていた。
男は僕に背を向けて無言で階段をのぼっていく。僕もそれを追った。一階分のぼった先で、なにかしらの決定的な違和感を覚えた。その違和感の正体に気付くまでに少し時間がかかった。男が
「な、こっちの階の方が見やすいだろ」
と気味の悪い笑いを浮かべて体を揺すりながら言い、僕はようやく理解した。
柵がない。
柵がない非常階段―それはすでに非常階段ですらない気がした。非常階段が安全性の確保のために存在するのであれば、柵の欠如はその目的にあまりに大きく反していた。薄い黒い金属の板でできた踊り場は、そのまま宙に通じていた。ひどく不安定で、僕を生につなぎとめてくれるようなものはそこには何一つ存在していなかった。風が僕を揺らした。ふわっと体が浮くような気がした。意識が黒い金属の、その先の明るい世界へと吸い込まれてゆく。
落ちる。
そう思った。僕があと二歩踏み出した先には男がいて、さらにもう二歩踏み出した先は、空中だった。あと四歩踏み出せば、僕はどこまででも落ちていけるのだ。飛ぶ練習をしておけばよかった、と思った。飛ぶことさえできれば僕はいますぐにでも千恵の部屋へ飛んでいける。でも僕はそんなことはできない。いや、僕だけではない。誰にもそんなことをすることはできない。たとえあのカップルだって、落ちたら死ぬしかないのだ。それでも僕は魅せられたように死に向かって進む。気がつくと足元にはなにもない。ずっと遠くに地面が見える。いつも千恵の部屋から見下ろしていた並木道。いつも千恵の部屋に来る時通る並木道。その愛すべき地面が僕に向かって加速度的に近づいていく。僕は微動だにできず、硬直したままなすすべもなく落ちていく。直立不動のまま落ちていく。直立不動のまま―
直立不動のまま、もちろん僕はまだそこにいた。もう一人の僕は僕の中に帰り、僕は僕自身となって男を見ている。男はやはり直立不動で双眼鏡をのぞいている。僕の存在を、いや僕だけではない、千恵以外のあらゆる存在を無視して彼は双眼鏡の先を凝視している。僕は視線を少し下に落とした。僕と死との間には相変わらずまだ四歩もスペースがある。僕はこのまま階段を下りる事だってできる。その事実を確認して僕は少し落ち着きを取り戻す。まだ大丈夫だ、僕はまだ落ちはしない。
恐怖にうちかった後に僕に残された選択肢は一つだけだった。いま思えば、なぜその選択肢しか残らなかったのかわからない。けれども、確かにその時にはその選択肢しか残らなかったし、それは本当に自然なこと、自分の部屋に好きな女の子と二人きりだったらその子とベッドに入る、ということくらいに自然なことだったのだ。僕が、いや僕だけではない、おそらく僕の立場におかれたほとんどの人がこの柵のない非常階段においてできる、そしてせざるをえないことはたった一つだ。たとえ彼がこの場所に立つまでそんなことは絶対にありえないと思っていたとしても、彼はそのたった一つのことしかできないだろう。その一つのことを、絶対にしくじらないように、慎重にかつ大胆にやりとげるだろう。この僕がそうであったように。
昔から、醜い顔が嫌いだった。女性もそうだし、男性もそうだ。むしろ男友達にその傾向が強いように思う。中学のときも、高校のときも、大学に入っても、親しい友達はみな整った顔立ちをしている。理由を尋ねられてもよくわからない。けれども人はみな、美しいものに魅かれるべきものだと思う。美しくないものを忌み嫌うのは、当然だとさえ思う。
男は千恵の部屋を覗き続けている。後ろ斜めからだけれども、その大きな口が歪んだり、丸く潰れた鼻が膨らんだりするのがわかる。他の部分は微塵も動かない。その表情だけが男という人間を語っている。お前が美しければ助かったかもしれない、と僕は思う。お前のような醜い男は千恵を覗き見する事すら許されないんだ、お前に美しいものはふさわしくない。
僕は千恵にメールを打つ。
To chiew628@t.vodafone.ne.jp
Sub Re: Message from SkyMail
できるだけ速く双眼鏡を用意して向かいを見て。
絶対いいものが見られるからさあ。急いでね。
送信はせず、いつでも送信できる状態にして男に話しかける。
「いま千恵なにしてる?」
「寝てるみたいだぜ?」
予想に反して男は即答した。
「寝てる?」
「ああ寝てる」
僕も双眼鏡で男が見ている方向を覗く。千恵は確かに寝ているように見える。
「そんなにずっと見てて飽きないの?」
と僕は尋ねる。
「そりゃあの子、きれいだからな。正直羨ましいよ君が」
「そうか?」
「ああ。あんな子と一度でもできたら死んでもいいよ。俺には絶対無理だからな。こんな顔じゃさ」
僕の中で、なにかが色褪せて行くのが分かる。こんなはずじゃなかった、と僕は思う。一度くらい寝かせてあげてもいいんじゃないか、そう思っている自分がいる。けれども同時に、もう決めてしまったことはもう変えられないこともわかる。僕はなぜか泣いている。男に悟られないように涙を拭う。一度大きく、深呼吸する。隣の部屋を覗いてみる。そこでは相変わらず完璧なカップルが完璧に不完全な飛行練習を行っている。僕は少なからず混乱する。なぜ僕らは彼らの存在に一度も気が付かなかったのだろう、隣人なのに。彼らの着陸は、そんなわずかな音すらしないほどに完璧に衝撃を吸収しているのだろうか。しかし同時に、僕は目的の部屋を見つけた事で安心する。これで男の注意を千恵からそらすことができるはずだ。
「なあ、隣の部屋って覗いたことあるか?」
「空き部屋だろ?なんか二段ベッドだけ置いてあるけどさ」
と男は答えた。
「いやほんとは空き部屋じゃないんだ。いま覗いてみろよ、面白いぞ」
男は双眼鏡を動かす。そして女が二段ベッドに登る。素晴らしい体だ。あれだけ飛び込んでもあざ一つない。飛び込みの姿勢をとる。丸く締まったお尻を窓側に突き出す。ピンク色のヴァギナが見える。そこにだけは少し陰毛が茂っている。そして女は飛ぶ。
醜い男の顔が固まる。微動だにせず、彼らの飛行練習を見つめている。僕はメールの送信ボタンを押した。
あいしあうーふーたーぁりーしーあわせのーそらー
大塚愛のにぎやかな声でわたしは飛び起きた。「さくらんぼ」の着ウタは智司からのメールだ。見ようとして手首が縛られているのに気が付いた。いつの間に寝てしまったのだろう。これじゃあ放置プレイもなにもあったものじゃないわ、と苦笑する。放置していたって安心感を与えることができる智司は本当にすごいと思う。
手首をほどいてメールを見た。手首は実はわりと簡単にほどける。でもほどけないことにして楽しむのが、二人の暗黙の了解だ。
智司
10/10 16:12
Re: Message from SkyMail
できるだけ速く双眼鏡を用意して向かいを見て。
絶対いいものが見られるからさあ。急いでね。
いいもの?双眼鏡?
本当に焦っているみたいだ、珍しく漢字を間違えている。こういうメールを智司が送ってくる時は大体きまって本当に楽しいことが起こる。智司は、わたしを(たぶんわたしに限らず女の子を)びっくりさせて喜ばせるのがとてもうまい。
わたしは急いで双眼鏡をクローゼットから取り出した。うちにある中では一番高性能の、三脚に固定して使うタイプのやつだ。双眼鏡をいっぱい持っている、というといつもすごく驚かれる。なんでそんな役に立たないものをたくさん持っているのよ、双眼鏡なんか一個で十分じゃない、と。でもみんななんにもわかっていないのだ。わたしに言わせればみんなもっといっぱい無駄なものをもっている。テレビだとか、ぬいぐるみだとか、得体のしれないダイエット食品だとか、似合いもしないような洋服だとか。でもそんなことを言おうものなら、あなたには優しい彼氏がいるから寂しくならないのよ、とか、どうせ食べたって太らないからわたしたちの気持ちなんかわからないのよ、とか、あなたは綺麗だから何着たって似合うものね、とか言われるに違いない。みんな、全然わかっていないのだ。
確かに智司は本当にいい彼氏だと思うし、わたしも自分では色々不満はあるにせよたぶん世間一般的に言ったら綺麗な女の子だと思う。でもそんなんじゃ全然足りない。わたしにはまだまだ足りないものがあって、それを埋めるために見つけたのが双眼鏡なのだ。双眼鏡は奥が深い。三つも四つも種類を持っていて、それを使いこなしてこそバードウォッチャーだと思う。
わたしは裸のまま双眼鏡を覗きこむ。ほどなく智司を発見した。わたしの双眼鏡を右手にもち、左手を振っている。その前には男が一人いる。男はハンサムな智司と対照的に、ブサイクだ。あんな男と寝る女なんていないんじゃないか、と思う。男はわたしの部屋を覗いているのかと思ったが、どうやらそうではないらしい。男は真剣な顔をしてまばたきをすることさえ厭うように双眼鏡を覗いている。たぶん、わたしの隣の部屋かその隣くらいを見ているのだと思う。
わたしは手をあげて智司に合図した。その時にはもう、智司がなにをしようとしているのかがわかった。鼓動が速くなる。ついに見られるのだ。鳥ではなく、ヒトが空を飛ぶところを。翼もなく、空を泳ぐ術も知らず、自分が望んでいたはずの完全な自由の中で、ただ恐怖におびえて落ちてゆくヒトの姿を。
僕は千恵が手をあげたのを確認し、男を力の限りに突き落とした。男の体は空中に放り出された。声もなく、男は重力によって下へと落ちてゆく。手が宙を泳ぐ。それは「飛ぶ」という行為からはおよそかけ離れた行動であった。もし、隣人の彼らであればもっと優雅に落ちていけるのだろうか。この男も練習さえしていればもっとマシな落ち方ができるのだろうか。でもそんなことは誰にもわからない。僕らにわかることは、男は、ただ、どうしようもなく落ちているということだけだ。その想いをおもんばかる人なんかどこにもいない。男はたった一人で、ただ一組のカップルに、客観的に、あまりに客観的に眺められながら落ちていく。
わたしは男が落ちるのを双眼鏡で追う。動いているものを視界にとらえ続けるのは意外と難しい。けれども男をとらえ続けるのは簡単だった。ただ落ちているだけだからだ。そこにはどんな意思もないからだ。鳥は違う。鳥は意思をもって翼を動かし、たまに予想もつかないような方向に動く。でもこの男にそんなことはできない。自然の法則だけにしたがって、男は落ちている。手を無駄にうごかし、恐怖で口をだらんと開け、目を見開いて、でもどんなものも見ることができずにただ落ち続けている。一緒にリンゴでも落としてみたら面白かったかもしれない。一度空中に出てしまえば、ヒトだってリンゴとおんなじなのだ。あの無意味な手の動き!あれだったら動かさないほうが断然マシだと思う。ヒトは空中ではこんなに無力なのだということを、男は体全体で表現していた。三六○度、空間はあらゆる方向に広がっている。でもどんなに必死にもがいても、ベストを尽くしたとしても(たぶんあの動きはベストを尽くしているのだ)ヒトは落ちてゆくしかない。バランスが崩れて、頭が下になる。男の手のもがきはますます激しくなる。落ちるスピードは増してゆく。男は死へとまっすぐに向かっている。この世界でいちばん死に近いヒト。絶望が男のブサイクな顔を支配する。もうその顔は、ブサイクですらない。
男が地面に墜落するのを待たずに、僕はその場所を離れた。一階下に降り、エレベータに乗った。誰にも会わない。完全に匿名的な巨大な団地の中で、僕はその匿名的な住人の一人になる。そこにアイデンティティなど存在しない。匿名的世界においてはあらゆる人間は交換可能なのだ。だから男を殺したのは僕だけではない。殺したのは僕であり、二〇三号室の住人であり、七〇四号室の住人であり…そうしたあらゆる匿名的な人間の集合体なのだ。そんな犯人を捕まえられるはずがない。逃げる必要などないのだ、自然に振舞えばいい。なにひとつ悪いことも間違ったこともしていない。僕はあの男を突き落とすべきだったし、千恵はその光景を見ることを真剣に欲していたのだ。
―そう何度も自分にいい聞かせ、震えを静めようとする。鼓動は少しおさまってきた。大丈夫、何も問題はない。
外の道路に出たとき、千恵からメールが来た。
「気を付けて帰ってきてね」
その短い一言に、多くのことが詰まっている気がした。コンビニに寄って千恵の大好きなハーゲンダッツを買っていくことにする。僕はいつものとおりクッキーアンドクリーム、千恵にはいつものとおりグリーンティー。部屋に帰った時に迎えてくれる千恵の顔を想像する。その笑顔はきっと、僕になにもかもを忘れさせてくれるだろう。本当にあの男を落として良かった、と思わせてくれるだろう。
男が地面にたたきつけられるところは木の陰になって良く見えなかったけれど、それでもわたしは充分にヒトの落ちる光景を堪能した。こんなことを言ったら、鬼畜だとか血も涙もない冷たいやつだとか、他人の死を喜ぶ最低なやつだとか、間違いなくそう思われるだろうけれど、どうでもいい男の死なんて本当にどうでもいい。智司はわたしがそろそろこういう種類の破壊を必要としていると、知っていたのだと思う。
本当はこんな自分は好きじゃない。そんなのは当たり前だ。でもわたしはこうやってしか生きていけないのだ。偽善だって大嫌いだし、強がっている人間だって大嫌いだ。汚いものも嫌いだし、臆病な人間も嫌いだ。わたしは嫌いなものに押しつぶされそうで、そしてそうしたものを必死にやっつけていかないと生きていけないのだ。落ちていく醜悪な顔をしたのぞき、彼は絶対に報いを受けなければならない人間なのだ。それはわたしの全ての嫌いなものの象徴だった。智司がそれを壊してくれた。でもわたしはいつまでこんなことを続ければいいのだろう。あらゆるものに毒づいて、気に入らないと壊して、壊せないといらいらが募って―。自由?そりゃ自由がいいにきまってる。でも自由なんていらない。わたしにはそんなものはふさわしくない。ほんとうは、誰にだってそんなものはふさわしくない。自由なヒトなんかみたことがない。自由ぶっているヒトならいくらでも知っている。わたしはそういうヒトたちに容赦できない。そしてわたしの周りからはどんどんヒトが離れていった。
きっと当分は大丈夫だ。でも当分大丈夫だからといってそれが何になるだろう。この世界は汚いものに満ちていて、あいつらはまたすぐにわたしの周りを覆い始めるのだ。今度は一人殺すだけじゃすまないかもしれない。わたしの望む世界にとって不必要な人間がこの世界には多すぎるのだ。自立と自由を求める人間たち―真の自立や真の自由がどんなものかも知らないくせに。自分の能力も知らないで度を越した見返りを要求する人間が多すぎる。わたしはそいつらを全部、東京タワーのてっぺんから東京中に振りまいてしまいたい。智司に早く帰ってきて欲しい。智司に抱きしめてもらわないと、どうにかなってしまいそうだった。智司とのつながりだけがわたしをこの場所につなぎとめている。もしそのつながりがなくなってしまえば、わたしはどこまでも落ちてゆけるだろう。クモの糸を突然出せなくなったスパイダーマンみたいに、なんで?なんで?と叫びながら落ちてゆく。離れ業で鉄棒をつかみ損ねた体操選手みたいに、両手を上に必死に伸ばしながら、わたしは落ちてゆく。なんでもっとちゃんと縛っておいてくれなかったの、とわたしは思う。
インターホンが鳴った。最初わたしはそれが何の音なのかわからない。インターホンは続けて鳴る。この鳴らしかたは智司だ、と思う。誰にもわからないかもしれない。でもわたしにはわかる。この鳴らしかたは智司の鳴らしかたなのだ。鍵を持っているのにわざわざインターホンを鳴らすあたりが智司らしいと思う。わたしは涙を拭い、とびっきりの笑顔を用意してドアへと向かう。わたしの、必死にかき集めてようやくちょっと見えるくらいの優しさも、わりと毎朝街をジョギングしてあんまり肉がつかないようにしている体も、千恵ちゃんってあんまり笑わないよねとほかの男には言われるけれど実はこっそり鏡の前で練習していたりする笑顔も、全ては智司だけのためにあるのだ。
千恵がドアに向かってくるのがわかる。僕は途端に怖くなる。足が震え、手の力が抜けてハーゲンダッツの袋を落としてしまう。僕らだって突き落とされたら落ちるしかないのだ、抵抗することなんかまったくできない、ただ落ちていくしかないのだ。今日はたまたま落とす側になっただけ。いつ僕らが落とされるか、そんなことは誰にも分からない。もしかしたら敵は、すぐ背後に迫っているのかもしれないのだ。
鍵が開いた。千恵は玄関で僕がドアを開けるのを待っている。入ってくる人がドアを開ける、というのが僕らの一風変わった決まりだ。玄関の中で抱き合うためにはその方がいいのだ、と千恵は言う。後ろを振り向いてみる。当たり前だけれど、誰もいない。でもそのことは僕を安心させはしない。僕は隣の住人のことを考える。彼らはなんで飛ぶ練習なんかしているのだろう。もしかしたら、彼らは落ちることに怯えて飛ぶ練習をしているのかもしれない。でも実際、そのことは何の効果もあげていない。僕らにできることは、ただ落とされないように、必死に何かにしがみついているか、あるいは何かに縛り付けてもらうことだけなのだ。そしてそれもできなければ、落とされる前に落としてしまうしかない。見つめてはいけないものは見つめてはいけないんだ、僕はいつもそう千恵に言ってきたはずだった。でもいま僕は見つめてはいけないものを見つめているのだった。僕は目を閉じる。見つめたって、どうしようもないのだ。いいな智司、絶対に、見つめては、いけないんだ。
「智司どうしたの?」と千恵の声がする。僕は目を開く。でも入っていくことができない。ただ立ち尽くしたまま、タイル張りの床に転がっているハーゲンダッツを見ていた。僕と千恵のハーゲンダッツを見つめていた。それを拾い上げるためには、もう少し時間が必要だった。
- Profile
 岩井とおる(いわいとおる)
岩井とおる(いわいとおる)- Going On
- 見ると見えない。見なくても見えない。そんなものをきっとあなたは見る。
- Trackback
- Ping 送信 URI: