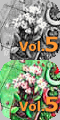- 特集「見る」
- 哲学者からの手紙
- 「書」
- 難しさにこそ、魅力が
- Talk Session
- みることからふれることへ
- 「見る」から「描く」へ
- Novel
- スイッチング・ウォッチング
- 同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
- よくばりな眼
- 秋の夜の夢
- 王子の見た景色
- ちいさなひとひら
- 宣告
- バードウォッチング
- see
- 見る
- Use your eyes
- おしりやぶれたズボン
- アイズ
- 万華鏡の世界
- Coffee Break
- ズレないBookCover
- Series
- メッセージをどうぞ
- おいしい水
- 不愉快なテクスト
- "いろは"の先のCSS
- Player's Side
- from editor
- 次回予告

不愉快なテクスト
加納 景第二回 如何に書くか
前口上
今回、この文書でとりあつかふのは、「文体」についてであります。前回の「如何に書くか」といふ問ひの当然の回答でせう。しかし、そもそも「文体」とはなにか。どのやうに「文体」を認識することができるのか。文豪は、如何なる文体を駆使し、名文を作り上げたか。これらについて、知らない、分からないかたは、拙稿を読む前に、以下の文書を読むことをおすすめします。
これは最も基礎的な、前提として欲しい知識ですから、これすら知らずに文章を公開してゐる者は、今すぐその筆を折つて、書店に駆け込み、書籍を読み漁ること。
文体は如何にして生まれるか
さて、サブ・テクストの内容からして、文体とは名文であるといふ誤解があるかもしれない。それは、しかし、とんでもない間違ひであります。文体は、名文でなくてよい。
文体とは、スタイルです。スタイル、つまり、その人のスタイル。
たとへば、その人の着てゐる服装。ファッションに関心のある人ならば、どのやうな色の配分で、どのやうに着るのか、といふことについては当然意識的であるはずで、意識的といふことは自分にとつて何が似合ふかといふことを知つてゐるといふことであます。その人に似合ふならば、デザイナーをうならす優れた着こなしでなくとも、その人はスタイリストである、といふことになる。むろん、優れてゐるはうが良いことは言ふまでもありません。ですから、先の言葉(「文体は、名文でなくてよい」)を言ひなほすならば、文体は、名文とは限らない。
ではその文体は、どのやうに作れば良いか。まあ、焦らずに。もう少し、とほまはりしてみませう。
私と貴方が会話してゐるとしませう。そして、貴方は、きのふ体験した奇妙な出来事を、私に説明し、同感したり共感したり、同じく感情をゆさぶられる体験をして欲しいに違ひない。さて、ではどのやうに語ればそれを成し遂げることが出来るのか。
貴方は、感じ入つて欲しい箇所で、大声を出すかもしれない。怖がらせるために、トーンを落として、ゆつくりと話すかもしれない。身振り手振りで慌てふためく様を表現するかもしれない。色々な方法がある。しかし、方法は様々でも、貴方がとる表現の方法は限られてゐるのではないですか?
貴方のふだんの言動は、貴方がどのやうな行為をおこなふか、といふことを周りに規定してゐるはずです。俗に、キャラクター、と言はれる、アレですね。「キャラに合はないことなんかするなよ」なんて言はれます。しかし、そのキャラクターとは、貴方の周りが決めることだけではないはずです。もしそれだけだとするならば、初対面の相手でも貴方のキャラを知つてゐることになる。そんなことはないのですから、むろん、貴方自身が決めてゐることもあるはずです。さて、ここで分かつたことが一つあります。つまり、貴方は、無意識に自分のスタイルを持つてゐる。
私は先に、スタイルをたとへてファッションを持ち出した。「ファッションに関心のある人ならば、どのやうな色の配分で、どのやうに着るのか、といふことについては当然意識的である」。つまり、スタイルをもつとは、無意識に貴方が行ふ言動を、意識することからはじめるわけです。
私はよく、自意識が足りない、徹底してゐない、といふ批判をします。自意識といふのは、「自意識過剰」といふ言葉で悪者扱ひされるのですが、それは、自意識の矛先が自分について周りがどのやうに思つてゐるのかといふ、つまり「周りが決めること」にばかりゆき、それを無様なやり方で態度に示してしまふがゆゑなのですね。私は、「周りが決めること」のほかに「貴方自身が決めてゐること」も挙げましたが、そちらは看過してゐるわけです。だから「無様なやり方」になつて仕舞ふ。ですから、私に言はせるならば、俗に言はれる「自意識過剰」も、自意識が徹底してゐない、といふことになります(参考:Other Voices(2004-05) -Poesia「善人・悪人/自意識」)。
文体は如何にして表はれるか
基礎的な「文体の発生」
ここまでをみると、なるほど確かに「文は人なり」といふのは尤もだな、なんてことになりさうなので、私は「とんでもない」と、かぶりを降つておくことにします。
言ふまでもなく、むろん、その格言は真実の側面をうつしてはゐる。けれども、文章を読んだだけでその人がわかる、といふことにはならない。実際、私のことを、貴方は知りうるでせうか。私は、「出来てたまるか」、と思ひます。
文章は多分に観念的なものです。書き手が感じたこと、考へたこと、行なつたことを、書き手の主観によつて判断し、主観によつて書かれる。そこに、真実を照らし出す客観が存在し得ないことは明白であります。ゆゑに、書き手の自意識の範囲内でのみ「文は『人』なり」であり得るのです。
してみれば、問題は、「貴方の思ふ自分」と「他人の思ふ自分」との「ズレ」といふことになる。さて、そのやうな「ズレ」を、如何にして克服するか。
むろん答へは分かつてゐるやうなもので、それは、「そんなこと知るか」です。
私は前節において、自意識の徹底を説きました。つまり、自意識を徹底させることによって、それ以上行き着く先のない、どうすることもできない点に到達すべきだと言つてゐるわけです。だからこそ、「そんなこと知るか」と言へるのです。
「そんなこと知るか」――文体が、個々人のスタイルに見える、過剰な個性に彩られるのはこのためです。思ひ切りが必要なのです。
その思ひ切りが、どこであらはれるかは、個人差によるでせう。書いてゐるうちに発見することもあれば、思考の末に至るかもしれない。いづれにせよ、語句の選定や文章の調子、長短の違ひといつた、表面的な文体の差異は、小手先の技術ではなく、人間その人の差異なのであります。
抽象論だけでは納得できないでせうか。ならば、プロの作家であり、当代一流の文体を持つ作家、保坂和志氏の文章を引いてみますか。そこには、文体を生み出すためのひとつのヒントが書かれてゐます。
前節で引用したどの文章も、風景のすべてを書き尽くしているわけでなく、何を書いて何を書かないのかの取捨選択がなされていて、その抜き出した風景をどういう風に並べると風景として再現されるかという出力(これが直列にする作業だ)に基づいて書かれている。
意外かもしれないが、これが文体の発生であって、私の考えでは、文体というのはこの作業の痕跡のことでしかない(だから翻訳でも十分に文体がわかる)。
「痕跡」は「成果」と言い換えてもいい。同じ石を描いても、一人ひとりの画家によってまったく違うタッチのデザインができあがるのは、そこに画家の身体が介在しているからだが、小説を書くという行為の中で本当の意味で身体を介在させることができるのは、風景だけなのだ。
(中略)
文体というと、言葉づかいが硬いとか柔らかいとか、センテンスが短くきびきびしているとか、ダラダラと長く続いているとかいう違いのように思われがちだが、これはあまりにも表面的、即物的な見方で、それを文体というなら、誰でもテクニックさえ磨けば、「いい文体」「味のある文体」が書ける。しかし、それは花そのものでなく花の絵を見て花を描くという子どもの絵の域を出ない。
他にも保坂氏は、文体は名文とは限らないといふやうな、私が冒頭で述べたことを言つてゐたりして、重なる点が多い。
風景を描くとはどういふことか
保坂氏の言を借りれば、風景を描くことこそが格好の文体発生のチャンスといふことになるのだが、しかしむつかしいのは、氏が書いてゐるやうに、それは「三次元を文字へ、並列を直列へという強引な作業」のことに他ならず、むろんそれは本質的に「花の絵を見て花を描くという子どもの絵」とかはらないといふことでもある。「本質的に」といふ言葉を「結果的に」と言ひ直してもいい。つまり、一個の花を描写するにしても、それをそのまま映し出すことは、文章では不可能なのだ。
一番よい例が、「音」である。文章表現において、「音」を表すもつとも直截的なものに、オノマトペがある。たとへば、トラックが車と衝突した、といふ場面で、小学生なんかは「ドーン」なんて言ふ。花びらが舞ふ様子を「ひらひら」と言つたりもする。しかし、実際には、トラックの事故現場に絶対音感を持った人がいれば、いや、今のはCのシャープとBフラットマイナーセブンのなんたらとか、コードの近似値を言ひあてて、正確に表現するかもしれない。私は、むろん、そんなテクニカル・タームを知らないから、ふーんとしか言ひやうがないし、多くの人もさうであるだらうから、文章でそんなことを書かれても分からない。同じやうに、たとへばこれは村上春樹氏の最新作『アフターダーク』(講談社)からの引用だが、「小さな店内に流れている音楽はパーシー・フェイス楽団の『ゴー・アウェイ・リトル・ガール』。」なんて書かれるわけで、これは音楽について正確な表現をするための最大公約数と言つてよく、どんな音楽なのかといふ詳細を省き、題名とか奏者などの事実を並べるだけで済ます手なのだが、これもまた「パーシー・フェイス楽団の『ゴー・アウェイ・リトル・ガール』」を知らなければどんな曲かも分からない。聞けば分かつても題名だけぢや分からないなあ、なんて人は結構ゐるだらう。
先ほどテクニカル・タームと言ったが、音の正確な表現にそれが必要になるのは、一般化された音の言葉がないためである。「『ぷー』と鳴った」なんて書かれても、それがなんの楽器のどの音なのか、それともおならの音なのか、まつたく判然としない。
「音」は、極端に文章にしづらい例だが、同様に絵画的な、写真的な景色、どんな花なのかとかどんな色かたちをしてゐるのかといつたものも、本質的に文章で正確に表現することはできない。ただ、「音」よりは一般化された言葉が豊富なので、想像しやすく書き易い。「あかい花」で「ばらの花」で「その赤も紅に近い」とか「莖には棘がある」とか、なんとでも、一応は書ける。むろん、その「赤」は「紅」でもなくどちらかと言へば「臙脂」であるとか「棘」とは言ふが顕微鏡でみれば先端は平らだとか、本当に正確な描写であるわけではない。
だから、これも「思ひ切り」によつて切り捨てるべき問題である。問題は、どこまで突き詰めて考へて切り捨てたか、といふことであり、それはすべて文体といふかたちで表はれるといふことだ。その地点において、初めてこのやうな悩みをナイーブだ、筆にインクをつける前に考へておけ、といふ批判が可能になるわけで、もつと言へば、これは哲学的な問題にまで発展し、私はこれまでカント的な、対象は人間の主観にア・プリオリに備はつた形式でしか論ずることはできず、「物自体」について語ることはできないといふ立場で論を起こしていたが、それは如何か、といふ問題を小説化することも可能であるはずで、そこまで問題にする必要も、思考の中では必要だらう。
形づくる
思考は大体において行動と密接不離の関係にある。したがつて、己のスタイルを築き上げる作業も、創作の行動が必要になるだらう。むろん、先ほども言つたやうに、はじめに思考をきはめておくといふ人もいらつしやるだらうから、一概には言へないが、それに限界を感ずる人はまづ書いてみるのも手でせう。その際には、保坂氏のアドバイスのとほり、風景を書く練習をしてみるのは効果的だと思ふ。
しかし、やつてみればわかるが、これが中々納得のゆくものにはならない。もちろん、普通の小説の作法は身につけてゐるといふ前提のはなしだから、それなりには出来るかもしれないが、自分にしか書けない、自分が作り出したと思へる、スタイルを作り出すことは、やはりむつかしい。私はこれができればプロだと思つてゐるから、それで十分なのだが、第一回にも言つたやうに、そんなところで満足するやうであるならば、たとへプロになつたとしても、或いはアマのまゝであらうとも、進歩することなく、ただ、惰性と弛緩の産物しか生まれない。私たちはさういふ作家を山ほど知つてゐるはずです。そして、さういふ作家は、早晩に自己模倣に陥り作品は平板化してゆきます。
話を戻しますが、なぜ既成の小説のやうな描写しかできないのか、といふ問題は、前節で説明した、文章の限界があるからです。限界があるから仕方ない?冗談ぢやない。限界があるから挑戦するのだ。浅田彰氏の文章を引く。
ドクサとはいえ、それに深くかかわることによってはじめて、ドクサを強引に横へズラせる運動、あのパラドクサの運動が、真にクリティカルな出来事として炸裂しうるのではなかったか。
精神論を振り翳すなと言はれさうだけれども、物質的な限界はおよそ思考の停止にあり前進することのない迷走にある。それを正すことが出来るのは、精神的なパラダイムの転換しかない。それは歴史が証明してゐる。さらに注意しておけば、私はこれまでに、精神論的な話しかしてこなかつた。なぜなら、かたちにあらはれた作品は、貴方自身の才能によるもので、私のアドバイスや論理によつて生まれるものではないからです。究極的には書き手の才能の問題である、といふことは、お忘れなきやう。
次回予告とコメント
- 次回予告
- 次回は、「如何に書くか」の続編、「『構成』について」です。そして、プラスアルファでいくつか。
- コメント
-
- 今回は文書をふたつに分けての作業で中々大変でした。私よりも文書量の多い方がたくさんいらつしやいますが、尊敬できることだと思ひます。
- どうなるFolio!?に関して、色々と言ひたいことがあるのですが、今は一先づ、これからの私たちを見てゐてください、といふにとどめておきます。

 加納 景(かのうけい)
加納 景(かのうけい)