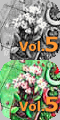- 特集「見る」
- 哲学者からの手紙
- 「書」
- 難しさにこそ、魅力が
- Talk Session
- みることからふれることへ
- 「見る」から「描く」へ
- Novel
- スイッチング・ウォッチング
- 同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
- よくばりな眼
- 秋の夜の夢
- 王子の見た景色
- ちいさなひとひら
- 宣告
- バードウォッチング
- see
- 見る
- Use your eyes
- おしりやぶれたズボン
- アイズ
- 万華鏡の世界
- Coffee Break
- ズレないBookCover
- Series
- メッセージをどうぞ
- おいしい水
- 不愉快なテクスト
- "いろは"の先のCSS
- Player's Side
- from editor
- 次回予告


see
寒竹 泉美1. kiss
kissって全然好きじゃない、kissが気持ちいいって一体どういうことかしら、快感なんて微塵も感じないのに、と思いながら彼女は目を閉じて恋人であるDの唇を受け入れている。kissのときはいつも、彼女は固く目を瞑る。目を閉じた彼女はどこか儚く、夢見がちな少女にも見える。でも、彼女が目を瞑るのは、彼女のまぶたが自然に閉じてしまうというわけではなくて、彼女が必ずkissの時は目を瞑驍アとに決めているからだった。kissのときは必ず目を瞑る、彼女の中で揺るがない決定された習慣。Dの舌が彼女の小さな白いエナメルの入り口を割って彼女の舌に届いた。彼女は一瞬眉をひそめたが、すぐに自分の舌を差し出してDの舌に応える、目はもちろん瞑ったままだ。
彼女が生まれて初めて男の子とkissをしたとき、(それは口の中に相手の舌が押し込まれて彼女の舌や歯や唇を這い回るディープなkissだったのだが、)彼女は目を瞑るという機転がきかなかったために、彼女の視界いっぱいに相手の顔が占拠することになったのだった。彼女が目にしたものは、kissに陶酔して目を瞑っている、のっぺりと間延びした間抜けな相手の顔だった。普段たわいもない冗談を言い合って笑っているときの、整った顔が見る影もない。少女だった彼女は初めて見る相手の表情を、吐き気をおぼえるくらいの激しい嫌悪で受け入れた。彼女は、それ以来、kissの間は決して目を開けない。彼女が成長し少女から女になって、数え切れないくらいkissを行った今も、やはりこの習慣は揺らがなかった。現在の恋人であるDの前でもそれは例外ではないのだけれど、彼女はDとの間の関係に何の不都合も生じない。そもそもDは、彼女がkissの間目を瞑る理由を知らないし、知ろうとも思わない。なぜならkissのときに目を瞑るのは(理由はどうあれ)一般的に広く流通した慣習で、ごく当たり前のことだったから。Dは自身もまた目を閉じてkissをしたり、ときどき目を開けて彼女の顔を眺めたりもするのだった。もちろん彼女の目を瞑っている顔を。
彼女の肩から彼女の腰、それから腰の下の丸い二つの山を、彼女の体の凹凸を彫りあげるかのように、Dの掌が強く彼女の体をなぞっていく。彼女は徐々にDの腕に体を預け自分の足で体を支えるのをやめるのだった。Dの腕が彼女の華奢な腰にまわる。Dは目を瞑ったままの彼女を抱え込むと、ゆっくりとベッドに倒れ込ませた。Dの唇が名残惜しそうに彼女の唇から離れ、一筋の唾液の糸が彼女とDの唇を繋ぎ、きらめいて消滅する。彼女はベッドに沈み込みながらその消滅を待っていたかのようにようやく目を開けて、Dに向かって笑いかけた。
2. sex
彼女は体の快感に溺れてしまうのが得意だった。体の中心の一番深いところから湧きあがる波に抗うことなく、つるり、岸から手を離す。彼女の裸体は小さな無数の泡とともに快感の深海へ沈んでいく。彼女の全身を生温い海水が満たし、彼女の重力が消滅していく。sexは好き、気持ちいいもの、と彼女は思いながら目を瞑ってDの唇が彼女の首筋をなぞっていく感触に集中していた。彼女はsexのときはいつも固く目を瞑る。これもまた、彼女のまぶたが自然に閉じてしまうというわけではなく、彼女が頑なに目を瞑るよう心がけている結果だった。彼女が決めた彼女の習慣。sexのとき、とは言っても男の指が彼女の体を愛撫しているときは目を開けていることもある。でも、相手の男が自分のペニスを彼女の中に挿入し自らの快感を探求し始めた瞬間には、彼女は必ず目を瞑っているのだった。彼女が目を瞑るのは、彼女が生まれて初めて男の子とsexをしたときに、快感のための単調運動を繰り返しながら歪んでいくその顔を見て、彼女がすっかり幻滅してしまったせいだったのだけれど。
Dの掌が彼女の乳房からゆっくりと彼女の中心に向かって下りてくる気配。彼女は光の届かない深海の底で彼の指を待っている。彼女の体の中心から涌き出る熱い泉、彼の節ばった大きな手、指、これが彼女の世界の全てになる。彼女はその泉を満たし溢れさせるものを切望し、その願いは泉の水となってますます彼女の欲望を加速させる。ようやく願いが叶えられた彼女は、暗闇に向かって、最後の空気を吐き出すように小さく熱い溜め息を吐くのだったが、その熱い溜め息の余韻に包まれながら彼女はもっと切実な願いを口走る。やがて次の願いも彼女に与えられ、彼女は暴力的な快感の支配に身を捩じらせながら、いっそう固く目を瞑るのだった。相手の顔を見ないように。自分の深海から浮かび上がることのないように。
3. his eyes
とはいえ、目を瞑った彼女の顔も快感で歪むのだけれど、彼女の恋人や彼女が今までにsexをした男たちは皆、その顔をかわいいと囁いてくれたので、彼女は安心して快楽に溺れることができるのだった。
見られるのは好き、あたしの体を顔を乳房を腰を性器を脚を恋人に見て欲しい、全部を隅々まで見て欲しい、と彼女は願っていた。彼女の望みどおり、彼女の恋人は彼女の体を視線で嘗め回す。彼女はその視線を目を閉じていても体中に感じることができる。sexの最中のDの目は、彼女の裸体をちりちりと焼き焦がしながら全身を撫でまわしていく。彼女の体はその快感に切なく身悶えるのだった。Dの目と快感の深海。彼女は何度も突き上げるような波を経験しながら、今度こそ戻れない、次こそ戻れないと思いながら、波に陵辱されるがままになり、Dの目のリードによってついに戻れない波の向こうに達するのだった、かつては。じゃあ今は?
Dの目。Dの視線。もう足りない、と現在の彼女は思っていた。彼女は現在、視線に飢えていた。彼女の全てを暴力的に突き上げて裏返してしまうようなそんな視線。恋人であるDに不満はなかった。Dと一緒にいると彼女は、帰る場所、戻るべきところに収まったという気がしてほっとする。でも、かつて、彼女がDと初めて出会ったときの、あの貫くような視線。彼女の中心の芯を焼き焦がすような熱い視線。彼女を切望して止まない飢えた視線。彼女はそんなDの視線を思い出す。あの視線がsexには不可欠なのに。現在のDの目は彼女をそっと包み込む冬の光のようではあるけれど、それではこみ上げるような快感には達しない。圧倒的に足りなかった。
4. another his eyes - (a)
というわけで、目を瞑った現在の彼女は、恋人ではない別の男の目を想像している。彼女に視線を送るその男をFとしようか。目をつむった彼女はDのペニスに貫かれながら別の男、Fの目を想像している。彼女の想像の中のFの目が彼女の脳を刺激して彼女のシンクから興奮を汲み上げ溢れさせる。彼女の体の奥に熱い電気が流れ彼女の体が内側から潤っていく。
ふと、Dの声が自分の名前を呼んだのに気づいて、彼女はそっと深海から浮かび上がって目を開ける。ああ、今あたしはDとsexをしているんだ。目をうっすらと開けた彼女は、頭の中でそう確認した。それから口に出して確認するために、彼女は小さく恋人の名前を呟く。名前を呼ばれたDはもう一度彼女の名前を呼んだ。彼女は途端に白々しいような落ちつかないような気持ちになって再び固く目を閉じた。彼女の体はゆっくりと紫色の海の底へ沈んでいく。それから、彼女は、暗闇の中の二つのFの目に見つめられながら呟くのだった、愛してるわ。
4. closed eyes
この物語の中では名前が与えられない彼女の素性を少しだけ話すと、彼女はカレッジの学生だった。そして、彼女がDとのsexの間、暗闇の中に想像する目の主であるFは、彼女の通うカレッジの若い講師だった。彼女がDとのsexの間に想像するFの視線は、退屈で単調な授業の合間に彼女に思いがけず投げかけられ、彼女の知覚を矢のように貫くのだった。彼女は決まって教室の中央の席に座っていたのだが、Fは口では学生たちに向かって単調な講義を続けながら、目は彼女に遣すのだった。まるで教室に相応しくない、一人の男の裸の視線が、彼女に密やかに投げかけられる。
授業が終わって学生たちが席を去り、教室に残っていた人の気配も消え去ったが、彼女は自分の世界から動かないでいた。彼女は誰もいない教室で、中央の席に座ったまま、顔を正面のブラックボードに向けて目を瞑った。薄くて柔らかな幕が瞳にそっと下ろされ、ただそれだけで世界はシンプルで淡い暗闇に退化する。光はまるでぬくもりのようにわずかに感知できるだけだ。形と色と動きがなくなる。目を瞑ると彼女は、宇宙に浮いているようなおぼつかなく不安な気分になるが、彼女の場合、その宇宙に何の恐怖も存在しないと分かるまでにそれほど時間はかからない。彼女は灰色の闇に身を任せると、重力のない宙で手足を伸ばす。存在と光が、温度のように彼女の手足を受けとめ包み込む。
彼女はふと、その宇宙の中に一つの確固とした存在を発見する。消滅寸前の恒星のように巨大な重力と赤い切実さを伴って光っている存在。彼女はその光に照らされる。頭の天頂からつま先までが赤い光に満たされて行く。彼女はうっとりと夢見心地のまま赤い光の中で目を開けた。目を開けると、目の前には「彼」が座っていた。彼、教壇からいつも彼女を見ているFだった。いつの間に近くに来ていたのだろう。ここにはもう誰もいないと思っていたのに。Fは彼女の前の席に後向きに腰掛けて、彼女を見ていた。彼女は突然現れたかのように思えるFに驚くよりも、灰色の温かな闇の中で感じた恒星のような切り立った存在が彼であったことに、どこか嬉しく気分が高揚するような感動を覚えていた。
彼女は吸い込まれるように彼の目を見た。瞬間、彼女は体の中心を貫かれるような感覚を覚える。彼女は不自然に思われないように気を付けながら、そっと視線を机に落とした。一方で、Fは視線を移動させる気配がない。Fは彼女を見ている。一体何を見ているのだろう? あたしの目? あたしの唇? 前髪? 首? 胸? あたしの頭の中で今考えていること、今までのあたしの思ったことが全部見えているんじゃないだろうか。彼女はふとそんな思いに囚われ、そう思った瞬間に彼女の体中の体液が沸騰するような感覚に陥った。あ、いけない、と彼女が平静に戻ろうと顔を上げたのと、Fが口を開いたのは同時だった。
Fの声とその内容は、視線の強さからは想像出来ないほど、どこか遠慮がちで優しかった。ああ、彼は自分の目が既に何をあたしに語っているか気づいていないんだ、と彼女は確信した。彼の目は既に……。それから、彼女はFの言葉に肯いて微笑むと、ゆっくりと立ち上がった。
あとのことは彼女が今まで考えていたよりずっと簡単だった。彼女は恋人に電話をかけて、今日は友達のところに泊まるわ、と告げて一番親しい女友達の名前を告げた。ごゆっくり、とDの返事が返って来た。彼女と彼女の友人の仲をうらやむようなちょっとすねたようなそんな返事。彼女はその返事で平常の落ちつきを取り戻す。それからたわいもない話をして、彼女は電話を切った。ちょっと饒舌過ぎただろうかと彼女は反省したが、すぐにその考えを追い払った。それから彼女はFと一緒に食事をしてアルコールを飲んだあと、Fの部屋に泊まった。あの目に貫かれた瞬間にもう、こうなることは決まっていたのだと彼女は思った。
5. another his eyes - (b)
彼女はFとのsexの最中に初めてそっと目をあけた。そのとき、Fの体は弓なりに反って顔は天井に向かっていたのだが、彼女の視線を感じたのか、そっと彼女に視線を投げかけた。彼女はFと目を合わせる。Fの二つの目。彼女がいつもDとのsexの最中にありありと想像していた二つの目。ああ、でも。少し違う。この目じゃない。あたしを手に入れて安心したような満ち足りたような、この目じゃない。彼女はゆっくりと目を閉じる。彼女の暗闇に現れたのは意外にもDの目だった。彼女はDの目を想像する。見知らぬ男に自分の恋人が抱かれているのをじっと見つめるDの目。Dの目があたしを見ている。内臓の底がひやりとする感覚。それから彼女の全身に電気のように快感が走った。あ、と彼女は思わず声を漏らした。彼女の声を聞いたFの動きは一層力強くなる。彼女はFの勘違いに眩暈がするような後ろめたさを感じた。しかしながら、その後ろめたさは彼女の理性を踏みにじり一層彼女の興奮を増していくツールとなる。彼女はDの目とFのペニスによってどこまでも深海の中に沈んでいった。落ちているのか上っているのか分からない無重力の中で彼女の快感が荒々しく彼女の体を弄び、彼女は彼女という枠を捨てて原始的な快感の流動体になるのだった。
6. love - (a)
彼女とのsexを終えたFはベッドから降りて少し離れた場所にあるチェアに腰掛け、服を着ている。そして、煙草を吸いながら、ベッドに横たわるまだ裸の彼女を見ていた。
「ところで、君に恋人がいるのは知っている」
と、Fは言った。ベッドの上の彼女は、Fの声が聞こえてはいたが、身動きはせずFの言葉に肯定も否定も加えなかった。
「君は、恋人を愛しているの?」
と、続けてFは言った。
「ええ、もちろん愛しているわ」
と、彼女は答えた。
「そう、」
とだけFは言った。あとに言葉が続くような気がして彼女は耳を澄ましていたが、彼女にはそれ以上言葉は与えられなかった。Fは煙草を揉み消すと、立ち上がり、彼女の隣に潜り込んだ。ベッドが軽くしなった。
「おやすみ」
と、Fは言って電気を消した。おやすみ、と彼女は微笑んで眠りに落ちた。彼女の眠りを妨げるものは何もなかったが、Fは暗闇に目が慣れておぼろげに輪郭が浮かぶまで彼女の寝顔をそっと眺めていた。
7. see
それから一週間後の彼女は、Dと言い争いをしている。(FとのことがDに知られてしまったから? 答えはノーだ。)きっかけは些細なことだった。彼女は彼女の誕生日にDと映画を見に行って特別なディナーとワインを楽しんでDの家に一緒に帰ってきた。そして何気なく映画の感想を口にする。Dとの見解が食い違う。感想だけじゃなく、シーンがディティールが、あらゆる面においてDと異なるのだった。
「さっき見たばかりなのに忘れたのか? 君は何を見ていたんだ?」
と、Dは言った。忘れたと決めつけるDにむっとして、彼女は「きちんと見たけれどそんなものはなかったわ」と答えた。それから口論になった。
「君は何も見ていない。映画だけじゃない。いつもそうだ。自分では見ているつもりだろうが、君は本当は何も見てはいない」
「見てるわよ、」と、彼女は反論した。この目でしっかりと。
「いいかい、網膜に像を映すことが見るってことじゃないんだ。僕が言っているのは、もっと本質的な見るという行為についてだ。光がなくても視力を失っていても見ることはできる、分かるかい?」
「ええ、じゃあ、あたしは本質的に見ていないというわけ」
「そう、君は本質的に『見て』いない」
彼女はDにも分かるくらい深々と溜め息をついた。どうしてこんな言い争いをしなくちゃならないんだろう。あたしはただ、映画の感想を言っただけなのに。さっきまであの瞬間まで、あたしは映画の余韻とディナーとワインで幸せな気分でいっぱいだったのに。こんなふうにDと言い争ったあとでは、今夜はとてもじゃないけれど恋人同士のムードには戻れないだろう。もとに戻るには、明日の朝、いや次に会う休日までかかるかもしれない。彼女は急に悲しくなって、Dの言葉に抵抗するのをやめた。君は何も見ていない、そんなふうにDが言うのならもしかしたらそのとおりなのかもしれない。
8. love- (b)
「僕は今、見るということについてずっと考えているんだ。僕の参加しているあの雑誌、」
「ああ、例の」
お金にならないやつね、と彼女は心の中で付け加えた。それから言葉を続ける。
「雑誌の企画で『見る』とは何だって考えるわけ? ジャン・ポール・サルトルのごとく?」
と、彼女は茶化した。Dの理屈に付き合うのはもううんざりだった。雑誌の企画でも何でもいいけれど、あたしを巻き込むのはやめて、と彼女は思っていた。Dは、彼女の語調を敏感に察知し、いらいらした調子で、ちょっと黙って最後まで聞いててくれないかなと少し声を荒げた。ええ、黙るわ、いくらでも、黙るけど聞くのはもう沢山、と彼女は心の中で毒づいた。そして、黙った。それから、彼女は口を閉じると同時に心の目も閉じた。彼女は彼女だけの深海に落ちていく。そこは温かく暗闇で、すべてのものは光となって降り注ぐ。荒々しい波もここでは静謐の雪となる。ここなら何を言われても平気、と彼女はぼんやりと思っていた。
しばしの沈黙の後、ようやくDは口を開いたが、彼の声はどこか疲れきっていてもの悲しかった。
「違う、そうじゃない。サルトルじゃない。僕が考えているのはもっと単純で原始的なことだ」
それからDは、深海の底にいる彼女を見下ろすと、重い荷物を引きずるかのようにゆっくりと言葉を続けるのだった。
「見ることと愛することとは似てると思わないか?」
了
- Profile
 寒竹泉美(かんちくいずみ)
寒竹泉美(かんちくいずみ)- 作家のたまご
- ぱそ子改め寒竹泉美。そろそろ小説はこっちの筆名で。以後お見知りおきを。(小説以外は、ぱそ子だよ!)
- Trackback
- Ping 送信 URI: