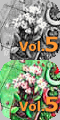- 特集「見る」
- 哲学者からの手紙
- 「書」
- 難しさにこそ、魅力が
- Talk Session
- みることからふれることへ
- 「見る」から「描く」へ
- Novel
- スイッチング・ウォッチング
- 同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
- よくばりな眼
- 秋の夜の夢
- 王子の見た景色
- ちいさなひとひら
- 宣告
- バードウォッチング
- see
- 見る
- Use your eyes
- おしりやぶれたズボン
- アイズ
- 万華鏡の世界
- Coffee Break
- ズレないBookCover
- Series
- メッセージをどうぞ
- おいしい水
- 不愉快なテクスト
- "いろは"の先のCSS
- Player's Side
- from editor
- 次回予告


スイッチング・ウォッチング
サイキカツミカラス
硬い壁面をもった構造物が無数に存在する。山と谷の起伏にしたがってそれらは凹凸し、時に周囲とはまるで違った高さの尖塔が屹立している時さえある。それらの間には細い線が引かれて互いに連結していた。電気が流れているらしいそれは、凹凸の一つ一つをつなぐ血管のようでもある。
それぞれがまるで違った造り。近付いてみると、個別の特徴を持っている建物たち。赤い傾斜で表面のつるつるした屋根。平べったいコンクリートの屋上も、絵が描かれている看板もある。色彩の豊かな森は「あれ」の住まいなのだ。
そう、カラスはおもう。「あれ」らは、我らを追い、憎み、時には我らの安全を脅かす。だが我らは「あれ」には決して負けないだろう。なぜなら我らは彼らの頭上で、彼らを俯瞰しているしヤツらの行動など案外想像しやすいからだ。
白く汚れのないビルディングの壁面があり、緑に覆われた神社の林もある。背の高い屋根のある高速道路の影は我らの格好の住処だ。そこから朝日の中に飛び立つと、世界は我らのものだとおもえるのだった。
実際、都市は我らの森だ。
地面に這いつくばった「あれ」たちや他の動物たちは我らのしもべではないかとも思える。 ふと、屋根の上に光るものを烏はみつけ、寄ってみると、屋根の上にガラス板を張った太陽熱温水の機械だった。ガラスはかなり汚れていて、騙された自分が滑稽だった。笑い、落胆し、近くの枝に身を休める。
二階建てのガラスからは「あれ」の影がいくつも見え、活動していた。それは小さな家。小さな庭がついている。
首を揺らして周囲を見渡したら猫は見あたらず地面に降りてみる。また住居の中から子供が泣いている声が聞こえる。
ちいさな女の子。苺柄の肩から下げるスカートに、白いシャツを着ている女の子。耳の上で左右に髪の毛を分け、これまた苺の髪留めで留めている女の子。
女の子は両手を目のあたりに当て、狭い部屋の奥にしゃがんで泣いていた。やがて大きな人影が部屋の中に入ってきて、オレンジ色のワンピースの女性が怒りを含んだ声で少女を引っ張り、抱え上げて隣の部屋に連れてゆく。庭の梵天の赤い実が緑色の茂みに映えていた。背の高い草が壁際に一面に伸び、狭い庭を更に狭くしている。イチジクの木が茂る。下草の茂みに光る目があり、カラスは羽を広げて退散することにする。
猫
がっかりと草むらから這いだし、まあ、カラスなどという「大物」はよっぽどのことがないと手に入らないのだとおもう。基本的に手に入りやすいものは蛙やネズミとかの躯のちいさなものたちだ。この家は、あの小さな子供しか餌をくれない。たいして旨いものじゃないから他の家に厄介になることが多いし、あの子供の母親は、自分を見ると嫌な顔をして追いかけてくるので嫌いだった。
壁の穴を抜けて隣の家にゆくと、そこは芝のあるのんびりした家だ。日差しの中はぽかぽかとして心地よいし、この場所はお気に入りの一つ。時たまこの芝の上で日中を過ごすが、普段人がいた試しはなく、時々、使用人らしき人がやってきて庭の手入れや古い屋敷風の家屋の手入れをしているだけだった。屋根の上に逃げ、ここには基本的には誰もいなくて、彫像でも飾っているのだろうとおもう。
豊かな水を湛えた大きな池には錦鯉が何匹もいて、いつかこの手で掴んでやりたいのだが、かなり深くてうっかりと手を出してしまうと、きっと溺れてしまうに違いない。くわばらくわばら暗く沈んだ苔の浮かんだ池。水面には蓮の葉がいくつもうかび、蜻蛉が降りてきてとまる。
そろそろ夏がやってくるので、蚊も増えるだろう。あいつらはウザくて芝の上までやってくる。縁の下はちょっとした隠れ家で心地良いが、それももう少しの間だろう。夏用にどこか涼しくていい場所に引っ越さねばなるまい。いろいろ面倒だな。
隣の坊主がいる家は、年がら年中人がやってきて、砂利を荒らしてゆく。それを坊主が、毎朝掃いて綺麗にするのだが、砂利じゃなくて別の道にすればいいのにと、壁によじあがって、黒いアスファルトの道路に身をおくと、道路向かいの玄関沿いにブルドックが繋がれていた。そして、猫をみると、うるさく吠えだすのだった。
犬
この感情に最も近いのは嫉妬ではないか。異種に対する攻撃心のよう分析はするものの、その実、種に植え付けられた嫉妬だろう。そしてそれを覆い隠すために多きな声が存在するのではないか。狭心な種の業。攻撃力は個を殲滅し全体を粉砕する。犬は吠えながら、これは俺が俺でなくなってしまう熱さだと考えていた。いったんその熱さに感情が流されてしまうと、もう留めることができなかった。
嫉妬するが成り代わろうとはおもわない。そこがキモだ。我等の仲間ではあるが、野良という階層は猫にちかい。食餌を用意する主人の不在が不安をあおる。うつろで始終定まらぬ視線はやつらのうろつく理由だ。不安だからこそうろつくのではなく、うろつくから不安になる。犬でもなくネコでもなく、定まる場所を探して旅する彼らは永遠の旅行者だろう。
朝飯のハンバーグは脂身が舌の上でとろけるように旨く、ソースの匂いが胸を高ぶらせた。こういう味を知ることはない。いや、知っていたのだが、やむにやまれぬ理由によって放棄させられたのではないか。
駄々をこねた息子のものなのか。
はん=ばーぐとは奇妙な名前だ。ぶる=どっぐ。主人は自分のことをそのように呼ぶ。そして由来と微塵も関係もないが、いくらでもハンバーグが欲しい。いくらでも欲しい。欲求を抑えられない。
玄関先で、ずっと道を眺めていた。ずっとずっと眺めていた。
退屈だがその場にいるだけでも様々なものがみえる。早朝のあわただしい女学生の姿。スーツ姿に身をやつしたサラリーマン。セカセカと歩いてゆく。彼らは時間の神様に仕えているのだろう。自動車が狭い住宅地を行ったり来たりして、道に迷ったか、迂回路を探しまちがってしまったらしい。
白い車が左から右へ行ったかとおもうと、しばらくすると逆方向に向かう。
買い物帰りだろう中年女性がはじめの往復は緩やかに、二度目は慌てた様子で走ってゆく。時間を凝集して見てみると世界はコミカルなものだ。彼らの生活を想像するのが楽しかった。
訪問者でもなければ、犬は自らの役割を忘れていただろう。嬉々として声をあげて主人に報告するのだ。自らの使命は警報と保護と安全な基準のある日常を維持することにある。予定外の行動より日常が最も大切であり安定した日常が全てだ。
だが突如訪れる非日常な瞬間。
ああ。時にその邂逅は、あの少女だけだ。自分の醜い姿を全く躊躇もせず近寄り「可愛い可愛い」と頬を撫で頭を撫で癒してくれる少女は、そして天使だ。
主人と目が合うたびに醜いと顔を顰められてしまう我が身を、絶望から救ってくれるのは、彼女の微笑みだけだった。彼女は子供の姿をしているが、どこか大人の匂いがして、そしてどこか悲しげな表情をしていた。犬は彼女を幸せにしたいとおもうのだった。
主婦 加代
またジョンの小屋の掃除をしなければならない。カタカタと打つノートパソコンのチャットの世界から戻らねばと何度も時計を見かえし、いつの間に時間が経過してしまったのだろうと、うんざりしてみたが、そのうんざりでさえ演技でしかないことを知っていた。そろそろ、私落ちるね。ダーリン。kiss Kiss Kiss どこの誰だか分からぬ男(だろう)に向かって投げキッスをしてパソコンをとじてひねもす時間という概念の存在しない空間から遠ざかる。
「ねえ、明日会おう。会おう」と繰り返すその男は、きっと童貞だろう。学校も行かずに部屋の中で、オタクなアニメの絵を抱いて寝てるに違いなくて、昼の日中からそうして遊んでいられる男にはぞっとするだが、その眼鏡デブの男とホテルにいる想像が浮かび上がってどうしようもなかった。
男はアニメ絵でオナニーしてるに違いなくて、やりたいの? ときくと、うん、と頷いた。まさか目の前でオナニーでも始められたら怖いなと思いながら、ちょっと滑稽な気分になる。
太って分厚い眼鏡をかけた三十近い男が、一心不乱に汗を流しながらベッドに腰掛け包茎ちんちんを動かしている。私はベッドの上で股間を開いたまま男の背中を蹴とばす。直接触れるのなんてもっての他なのでストッキングを巻いて強く引っ張ってやる。男の首が絞まって、やがて声が絶え絶えになって、間が抜けたようなタイミングで男の自慰が終了したのを知る。どろりとした白い精液がゆっくりと流れて、男の手の平からシーツの上にぽとりと落ちた。
空しい。
馬鹿げた想像をして気分が悪くなり、タイムリミット。隆史がそろそろ小学校から帰ってくる時間だとおもいなおす。おやつでも必要かもしれない。昨日買った麩菓子では誤魔化されないだろう。三件隣の石塚さんの娘はいつも市内の三河屋の洋菓子がおやつだと言っていた。老舗のおやつを用意するには及ばないのだ。隆史は最近、服を汚して困る。お風呂も掃除しなきゃね。
──涼子ちゃんのおっぱいをもみもみしてやるう〜
──いやあん。くすぐったい〜。
──おっきいね。いくつ?
──ないしょ
──ねーねー
空疎な会話の記憶が脳裏でふわふわ浮いていた。パソコンは頭じゃなくて脳味噌の後ろの方で、変な熱に浮かされながらだらだらと静かに感情が揺れてゆくようで、脳のどこかが緩やかに麻痺してゆくような気分になる。
あらゆることが遠い。
感触がない。
もしかして世界はここにあるのではなくて、もっと別の場所にあって、自分は鏡に映ったその映像を見ているだけなのかも知れないし、全てが嘘の世界に存在してるのではないかと錯覚を感じる。
玄関を出たところで、犬小屋に子供がいた。
ああ、またあの子がやってきているだわ。近所の坂田さんちの娘だ。ヤヨイちゃん、だったかしらと頭を傾げて思い出そうとする。ヤヨイちゃんにはジョンは決して吠えない。またやってきてるのだけど、この子、ちゃんと学校に行ってるのかしら? 服もいつも汚れて、ちゃんと洗ってやってるのかしら? でも坂田さんはちょっとヒステリックで私、嫌いだわ。関わり合いになりたくない。みんな関わりたくない。なにもかも嫌い。
弥生
犬はずっとどこにも行けないので可哀想。ねえ、今日は何食べた? 今日は私、なにももってないけど、今度ママに隠れてパンを持ってきてあげるね。
分かってるのかわかってないのか。ぶさいくな顔をした犬は弥生の膝に擦りよってくる。
「こんにちは」
「こんにちは」
怖い顔をしたおばちゃんとあいさつ。悪いことでも考えているような目つき。躯が硬直する。
「もう学校から帰ってきたの?」
うん。
うちのジョンは誰にもなつかないのに、ヤヨイちゃんにだけはなついてるのよ。
おそるおそる顔を上げておばさんをみる。私の友達はわんわんとにゃんにゃんしかいない。みんなが言うようにわたし、みんなの友達じゃないといいたい。
ジョンのお友達になってね、という意外な言葉に弥生は嬉しくなって「うん」とこたえ、おばさんはいい人だ。なんていい人なんだ、とおもう。じゃあね。私ちょっと買い物に行って来るけど、ジョンをよろしくね。
「はい」弥生はほっとして答える。
そうだ、と声をあげて、おばさんが門のところで振りかえって「隆史が帰ってきたら、ジョンを散歩に連れていってやってって伝えてくれる?」という。わかりました。伝えます。
おばさんの姿が消える。
弥生はほっとし、時間を稼ぐことができたとおもう。だが帰宅する前に逃げねばならない。お気に入りのキティの時計のバンドがかなり痛んでいるのを悲しくおもい、一時間ぐらいだと確認する。
ジョンが手を舐める感触は優しさに満ちていてとても好きだったが、ジョンはうちの犬じゃないし、誰かに監視されてるような気がして恐ろしかった。誰にもみられないでジョンとずっと遊びたい。誰かの視線を感じない遠いどこかへ消え去りたい。誰もいない場所を想像して、開放感と共に恐ろしさを感じ、とても心細くせめてジョンやあの三毛猫(にゃんにゃん)さえいなければ、いったい自分はどうなってしまうだろうかとおもう。ジョンのまん丸な目をみると、ちょっと潤んで泣いているのか夕方の日光がまぶしいのか、無垢で何も知らない赤ちゃんのようで、そして。みんな居なくなってしまえばいいんだ。
玄関で驚く声が聞こえる。
隆史
なんでこんな所にいるんだよ、と声をあげて、うんこヤヨイはいつも暇そうだとおもう。学校には時々しかでてこないので、頭の足りない子のクラスにいた。ヤヨイをみるとみんなで石を投げつけるのが慣例だ。
ジョンと仲がいいのはきっとうんこ臭いからなんだろう。醜いジョンは短い足で地面を掻く。玄関先にいくつも穴が空いている。自分勝手に歩くので散歩に連れくのが嫌だ。伊沢君の所みたいにシェパードとか、大貫さんの所みたいにコリーとかだったらかっこいいのに。ジョンを嫌だとおもう。犬は面倒だし、人間のいうことを聞くというけど、こいつは馬鹿で吠えてばかりで、どこの誰が来ても吠えることしか知らないで、芸のひとつも覚えるわけじゃない。
吠える犬。
吠えるだけの犬。
ヤヨイは臭くないのか。臭くてすえた匂い。やはり犬の糞とお似合いなのだ。
「なんだよ。くんなよ」
ヤヨイは顔を曇らせた。哀れうんこ。
「くんなよ。臭いの、うつるじゃねーか」
ヤヨイは泣きそうな顔をし、バイキン扱いされているのだから仕方ない。隆史は苛立ちがつのった。蹴らなかっただけでもありがたいと思え。無視してやろう。
「あ」とヤヨイが声をあげた。
なんだよ
おばさんがね、ジョンを散歩に。はぁ? ご、ごめんなさい。おばさんがそう言えってあー。わかったよ。後でやりゃあいいやと、手を振ってヤヨイを追う。さ、散歩してあげないの? いいだろ。そんなこと。後からやったって言えばいいんだよでも/でも。でも糞もあるか。知るかよ。でも。
「じゃあ、お前が代わりにやるか? いや、やれよ」
「え」といってヤヨイは俯いた。
が、すぐに満面の笑みをして、いいの? やらせて。
しまった。隆史は罰としてヤヨイにやらせようとしたのだが逆効果だった。ああ、行けよ。一時間で帰ってこい。うん、と嬉しそうなヤヨイは馬鹿だ。臭い犬はこれからあいつにやらせればいいんだ、とおもう。散歩用にこきつかってやる。
猫
そしらぬ風に鼻歌混じりで犬が悠々とあるいている。紐を引いてるのはいつものあの子だった。猫はショックをうけた。我ら猫種にのみ親密ではなく犬種とも親密な間柄なのか。これだから人間は信用がおけないとおもう。都合の良い風にその場その場の気が向くままに、だが、善良な彼女ならありえる事態で、当然予測していなければならなかったことだと考え、猫は少し腰を引き気味にコンクリートの壁の上にしゃがんだ。彼らが通りを渡り、大通りへの道へ進むのを眺める。
猫は頭に何かが止まるのを感じ、足を上げて掻こうとするとそれは居なくなり、ふとするとまたやってきて耳の後ろあたりに気配があった。塀の中から木の枝が垂れ下がってブロックに引っかかっているのは柳の木だ。青々としたその葉が簾のように広がって塀の上に広がっていて、小蠅が目の前を横切った。葉と塀がぶつかったあたりで子蠅はしばらく佇み、一瞬だけ緩慢な動作で身を捩ってからおもむろに飛びたつのだ。
塀の中の小綺麗な庭の隣に例の小汚い庭がある。庭と庭でへだたれていて、家屋の距離はちょっとあり、その家だけは、周囲を立派な屋敷に囲まれていて、かつてその家に爺さんがいた時には確かもっと綺麗だったとおもう。もう爺さんの顔も思い出すことができない。
人が変われば庭も変わる。
あの爺さんはよくしてくれたはずだと猫はおもいだすが、さてはて、それは自分が子供の頃の話だったのか、他の猫から聞かされた話なのかわからない。記憶の混乱に猫は少々苛立ちもし、自分には、やはり人間たちの世界の仕組みはよくわからないなと、あくびをする。
先程、首筋をうろうろしていたヤツがまたやってきたので手を伸ばすと、からくも逃れられてしまう。ソイツはふらふらと道路を横切ってゆく。犬よ、そのふらふら揺れるものを捕まえろ、と猫は胸のなかで望んでしまう。
蝶
道に迷い出て犬の鼻先を掠め飛ぶとあやうくその大きな口に閉じこめられてしまいそうになった。子供が連れた醜いブルドックの脇を通り過ぎると、草が茂った公園だった。公園といってもただの空き地に、どこから持ってきたのか錆び付いたブランコと雲梯(うんてい)が置かれているのだが、雲梯の方は草に覆われてしまって誰かが使っている風情ではない。ブランコの足下は幾分草が削られて地面がみえている。蝶はブランコの椅子にとまって羽を休める。
どこへ飛んでいくことができるかと目を巡らせ、視野の端に三毛猫が見えた。塀の上から降りて道路を渡って広場の方に近付いてくる。
草の中には蛙でもいるかもわからない。鳥も居るのかもしれない。花の蜜が欲しいなと躯の真ん中が軽くはなったが、今度は疲労が激しかった。そろそろ、何か養分になるものでも必要なのだろう。飛ぶのが疲れてしまったのはひとえにこの街に植物が少なすぎるというのはあるだろう。
いや、植物は存在しているのだが、そこに蝶や虫たちにとって心地よい環境であるのかどうか、ということまでは自分にとっては、実はどうでもよいことなのかもしれない。環境によって生育し、環境によって淘汰されるのは、人も魚も鳥も蝶もそういう意味では同じだ。だから環境が全てだ、ということではない。環境は空間によって左右される。それを逸脱することができるのはすべからくあらゆる生き物にとって同じことでもある。
蝶は躯を起こして風を羽にたわめて風に乗ろうとする。
幾度か羽を動かすと徐々に躯の重みが軽くなってくるのがわかり、躯が浮きはじめてわくわくする。やがて風がきて、ふっと離陸する瞬間がやってくる。広場を離れ、電信柱を巡って道路の上に流れてゆく。
電信柱
左右の手を伸ばせば遠くまで、どこまでも届くようだ。隣同士の仲間を伝って一つの出来事が伝播され、共有するのが我等。そうして遠くまでの景色がみえるけれども、我らにはみたものを口にすることはできない。ただ伝え、傍観するのみだ。世界中のあらゆる場所の景色を伝えたいという思いとそれが可能ではないとおもうジレンマに悩まされて、ただその場に立ち続けるのは正直苦痛ではある。
神はすべての事柄を知っているという。だが、我らは知ってはいても伝えることのみで、口がきけない、表情もない、他者の存在しえぬ同族同類のみの共同体に過ぎないと考えるのだが、我々は神ではなく、神の使者でもなく、やはり伝播することがのみ役目を持つただの柱に過ぎない。
いや。それほど自己を抑制しなければ我は神であると勘違いしてしまう場合が存在するからだ。仲間のうちで時々奇妙な妄想にとりつかれてしまうのもいる。その意識が必然的に伝えられてきて、そうしたおもいが幾重にも詰まってくると、うんざりし、いたたまれなくなるのだった。
そうして「あいつウザイよね」と仲間に感じられないように、電信柱は自己を律するのがもうひとつの勤めなのだともおもう。
ただ風景をみる。木々が生え、家々が様々に彩られ、その隙間に長い腕が伸びてゆく風景は、電信柱がその場所にたてられてから放棄されるまで、長い期間に徐々にだがドラスティックな変化を持つ。だが、長期のスパンで思考をすることが出来ない人間達は人々の姿が変化してゆき、全く変化もなくやってゆけると錯覚をしているようだ。変化を愉しむためには語らぬ感じない忍耐が必要であり、自己の生を基準としない、全く別の俯瞰的な思考の基準が必要なのだ。
いま、足下を少女が駆けてゆく。
その少女が涙を流しているのを電信柱はじっとみてみぬ振りをする。少女は先程他の電信柱の報告から川縁の広場に向かったはずだったが、少女は犬と辿った道を一人で戻っていた。顔の必死さによって(彼女の中での)事態の深刻さがおもいやられる。やがて少年の家に駆け込む報告がやってきてくるだろう。電信柱は少女の日々を知ってはいるが語ることはできない。伝え聞いてはいるが、それと現在少女が走る姿に関連もなさそうで、それより、少女の頭の苺の髪留めが揺れるのがトントンと弾んだボールのようにみえて、それはとてても可愛らしいとおもえる。あれが銀色の玉で光るものであればカラスにでも襲われるのではないかとも心配する。やつらは光るものに目がないのだ。
カラス
少年と少女はその家から走りだした。道中、すれ違った買い物帰りの母親に駆け寄り、やがて三人共があわててるのだった。電線の上で仲間と駄弁るのも悪くはなかったが、興味をひかれて烏は追跡をすることにする。なあ、電信柱よ。何が起こったのか教えてくれないかと烏は問うが、彼らは沈黙したままだ。家の上のアンテナ達はおのおのの宿主のことで係り切りで彼らは周囲に関心はなく、彼らの関心は遠くの場所に限られ、近隣には興味をもたない。だから烏は聞くのをやめ、近くを飛ぶ仲間に話を聞くことにした。
やがて彼らの川縁の草原の声がきこえて烏には事態を把握することができ。、どうやら犬を見失ったようだ。少女が川縁を歩いていると少年達に石を投げられて慌ててうっかり手を離してしまったらしい。少女は自責の念に駆られているだろう。少年は少女に腹を立てているだろう。母親は少年に腹を立てて、少女を残酷な目で見ているだろう。
烏は川を渡る鉄橋の上に移動した。彼らは犬の名前を呼びながら、草の広場でちりじりになる。長く成長した草の中で黒い頭がみえ、ガタガタと足下で電車が走ってゆくのをながめ、カラスはまだ海を見たことがなく、仲間の話から想像するに、川をさかのぼる船の波紋はまるで小さな海のようではないかとおもう。そして八の字に広がってゆく波紋に対してm下流から吹き上げてくる夕方の風が草の頭を波立たせる様子は、水面が広がっていき草の原も飲みこんでしまったようにみえた。
犬を探す彼らは、水面に浮く黒い玉のようだった。と、川縁の道をゆっくり移動する小さな点があった。その隣を見覚えのある赤い軽自動車がすれ違った。カラスは、あ、お迎えがきた、とおもう。
犬
「あっ」とおもう。天使の声が聞こえたような気がしたのだ。振り向いた瞬間、首に強烈な圧力がかかり、後ろ向きに躯が引っ張られた。アスファルトが勢いよく流れてゆき、ごいんごいんと打ちつけられるのだった。あまりの苦しさに仰天して犬は声を上げたが、いったい何が起こったかおもいもかけずに起こってしまった事態に仰天していた。
我が天使が少年達に虐められ、彼女のために少年達を追うつもりだった。自分は間違ったことをしていたはずはない。だが、天使とはぐれてしまった。自分が居なくなったということで彼女は罪悪感を感じているのだ。嗚呼、なんという罪悪をしでかしてしまったのだろうと犬は悔恨する。
だからこそ、これは何かの罰が与えられているのではないか。自分は罰によって死んでしまうだろう。ああ。ダメだ。首が強烈に絞められてゆく。もうすぐ死ぬのだ。絶望だ。とおもう。あとひと目、少女の姿をみてみたかった。この目に焼き付けたかった。
白くなってゆく視界の中で助けを呼ぼうとするが、声を出しているのかどうかさえ不明だった。じたばたしてるうちに、この首が絞まってゆく理由が解けた。通り過ぎた車のどこかに紐が偶然にも引っかかったのだ。
理由が判別するも、それは死刑宣告に近かった。自分の力ではどうしようもないことなのだ。耳をつんざくような音を立てて車がブレーキを踏んでいた。
だが、もう息が出来ない。涙が──絶望だ──意識が飛ぶ。。。
強い衝撃で躯が地面にぶつかるのがわかった。ドアが開かれる音が聞こえた。ああ、自分は助かったのだとため息をつくが、首は絞められたままだった。躯に力が入らない。
「なによ。この犬!」
腹が割れて中身が溢れてしまうような痛みに犬は自分が蹴られたのだと知る。憎らしいその足は赤いヒールを履いていた。尖った部分が何度か顔に当たり、助かったのに殺される、と犬は思った。
「なによ。なによ。なんでこんなのが引っかかってるんだよ!」
憤怒の声だった。女のポケットからナイフが取りだされ、犬は戦慄した。
と、その瞬間、悲しみに満ちた天使の声が再びきこえた。
「じょーん」
隆史の声もきこえた。
ご主人様の声もきこえた。
犬は天使に向かって発せられる「ヤヨイ!」という殺犬者の声をきき、自分を殺そうとしていたのが天使の母親なのだとしった。天使と悪魔だと顔を上げると、悪魔の顔はやはり悪魔の表情で天使を叱り、時間なのよ。どこほっつき歩いてるんだ。馬鹿。と頬を交互に叩く音が響いた。
母親 遙
「やめてください」と少年の母親らしい女が怒っていた。
「だれだよ。あんた」
「ヤヨイちゃんはうちの犬が迷子になったのを一緒に探してくれてたんですよ」
どんくさい格好の女だな、とおもう。はっきりいって不細工でデブでヒステリー性。欲求不満の固まりのような女だ。最近セックスしてないだろう。旦那はきっとこの女をみても勃起したりしないはずだ。
「これはうちの問題であんたが口を出す必要はないだろ」ウザいんだよと付け加える。
「うちのジョンを轢きそうになったのがあなただけの問題ですって」
ああ、この不細工な犬は不細工な女の犬だったか。と犬と女を見比べてみるとおかしさが溢れてきた。
お似合いだよ。と思うと同時に女が怒っているのが茶番めいた気分になり、それより、と時計を確認して「客を待たせてるんだ」とおもうと、こいつに関わりあう必要はないと判断を下す。
「悪いけど、ロープは切るよ。あとで弁償させて貰うからね」と、車の後輪に絡まったロープを切る。
その時になって女は犬に駆けよって「ジョン。怪我をしてるじゃないの」と犬をみる。
女は五月蠅いと母親は思う。
「こっちだって車に傷がついただろ」
「命より車が大切だっていいたいのですか」
その女は逆上してるようだ。馬鹿馬鹿しい。
「ヤヨイ、帰るよ」
おどおどとしているヤヨイの手をひくと、生意気に逃げようとしていた。もう一度強く引く。
「嫌がっているじゃないの。離してあげなさいよ」
「てめぇには関係なんだよ」
ヤヨイの顔を見ていると殴りたくなる。どうして私をそこまで恐怖するのだ。お前は、お前は、と思い、無理矢理に車に連れ込みエンジンをかけながら小声で脅す。
「お客が帰ったら、お前、折檻してやる。覚悟しな」
と、それまで事態におののいていた少年がヤヨイに声をかけた。
「またジョンに会いにきてやって」
ヤヨイはガラスにびったり顔をつけた。そして頷いている。頭を叩き、この色ガキがと罵ると泣きだす。うざい。車を発車させるとヤヨイは目も合わせようとはしなかった。五月蠅いよと頭を叩くと、余計に泣きだして苛立ち、黙れと叫ぶとすすり泣きに変わり、やがて静かになる。
どうしてこの子は私のいうことをきいてくれないのか。なぜ、なにもかも上手くゆかないのか。私だけが私だけが不幸を背負っていると思い、この子の父親の顔をおもいうかべて、こんな子を生むべきではなかった。
時計を見るともう約束の時間より一時間も経過している。早く帰らなきゃいけないとおもう。馬鹿、馬鹿、馬鹿、邪魔しやがって。この子を一人で外に出すのではなかった。ちょっとした慈悲心が厄介を生み出すのだ。あの不細工女が、また私のことを悪口を言うだろう。近所がどのように私のことを言ってるのかは分かってるのだ。こんな街、みんな死んでしまったら良いのに。
腹が立つことばかりだ。私の一生はむかついてばかりだとおもう。ハンドバックからミニボトルをだして口をつける。
弥生
玄関を抜けると応接間に太った隣のお坊さんがいた。母は私の頭を叩いて、挨拶をしなさいと言った。私はこのおじさんは嫌いなのだと思う。どうしたの、どうして泣いているの? おじさんに話してちょうだい。怖いママがいないあっちで。
もし自分が神様だったら、意地悪な人たちと大人をみんな殺してしまって子供と動物だけの世界をつくるんだ。きりんさんに乗ったり、犬をいっぱい飼うんだ。にゃんにゃんといっしょに丸くなって日溜まりで眠るんだ。ずっとずっと。
猫
そろそろ寝床を探さないといけないなと屋根の上で起きあがると、ガラス越しに少女と目があい、そして微妙な笑顔をして奥の部屋に消えた。人間ていうのは表情がややこしくてかなわないな。厄介な動物なんだ、とおもうが、ヤツらは自分勝手だからどうしようもないよね、とあくびをして、腹が空いたな、と街をみおろした。屋根屋根があり、人々が住んでいる。木々があり、鳥が住み、烏が生息し、ネズミや猫や犬達が生息する。家々に明かりが点り、彼らは身勝手にもこの世が自らのものだと思っているだろうが、どっこいそうじゃない。誰も何も見ていない。いや、それぞれが何かを見て何かを感じているはずだが、それぞれが全く別の世界に生きていることを──そうだ。特に人間達はその事実を知らないのだとおもうと、なんだか彼らの世界も自分たちの世界も、ちっぽけなもののように感じた。
それより、まあ、猫としてはだ、腹が減った。
カラス
ケラケラと空の上から世界を嘲笑し飛翔する。
了
- Profile
 サイキカツミ(さいきかつみ)
サイキカツミ(さいきかつみ)- はてな仮眠室
- 一日中眠い病をどうにかして欲しい今日この頃。遊びすぎとは言わないでください。夜型万歳。
- Trackback
- Ping 送信 URI: